- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
がん遺伝子発見のノーベル生理学・医学賞は1989年だが,関連する動物の発がんウイルスの遺伝子研究は1960年代後半からである。当時東京大学医科学研究所の豊島久真男先生の「化学と生物」における1983年の総説には,“発癌機構の一元的理解も真近かか”と記されている。私自身の1987年初めての日本がん学会ポスター発表会場で平井久丸先生と2人で立っていたら,豊島先生がいらして,じっくりポスターをご覧になり,Ephのエクソン境界に関するアドバイスをいただいたことがあった。オンコジーン・がん遺伝子というと最近ではやや陳腐に聞こえるため本特集のテーマはあえて疑問形にした。私自身の答えは,「進歩を持続的なものとし,また障壁を明確化した」である。
ハリケーンのように絶大な力で発展し,1970年ごろから始まった血管新生,最近では炎症なども巻き込みマージしてきた。第一に診断,第二に治療,は医療の基本である。がんの遺伝子診断が保険収載され,ガイドライン策定で学会を,またがんゲノム医療拠点病院の設置などで行政をも動かしている。この第二の視点では,BCR-ABL標的薬の成功が分子標的薬という言葉さえつくり出したと言っても過言ではないが,すべての薬は標的となる分子が,また薬剤耐性が,最初から存在するのは歴史的事実である。重要な分子標的が決定していても開発が困難で科学の進歩に依存しなければならないものもあるが,薬ができたからといって優れているとは限らない。薬は分子ではなく病気を標的にしなければ優れた創薬とは言えないからである。第三は,実験技術の進歩を誘導し分子生物学へ貢献した。シグナル伝達,その代謝との連関,エピジェネティックス,遺伝子組換えによるモデル動物の開発,創薬を目指した結晶構造解析,などである。そのなかで,がん遺伝子の機能が多様であるために,神経,免疫,発生などがん生物と一見異なる分野への進展や貢献を見せてきただけでなく,がん抑制遺伝子,悪循環,ダブルフィードバック,逆説的作用,補完,分解・消失など細胞内分子論におけるロジックの発見を誘導した。第四は,凄まじい発展がゆえに,がん生物学における障壁も明らかになってしまった。がん転移などである。Signatureがいまだに存在せず,生体の全身における炎症を基盤としている。
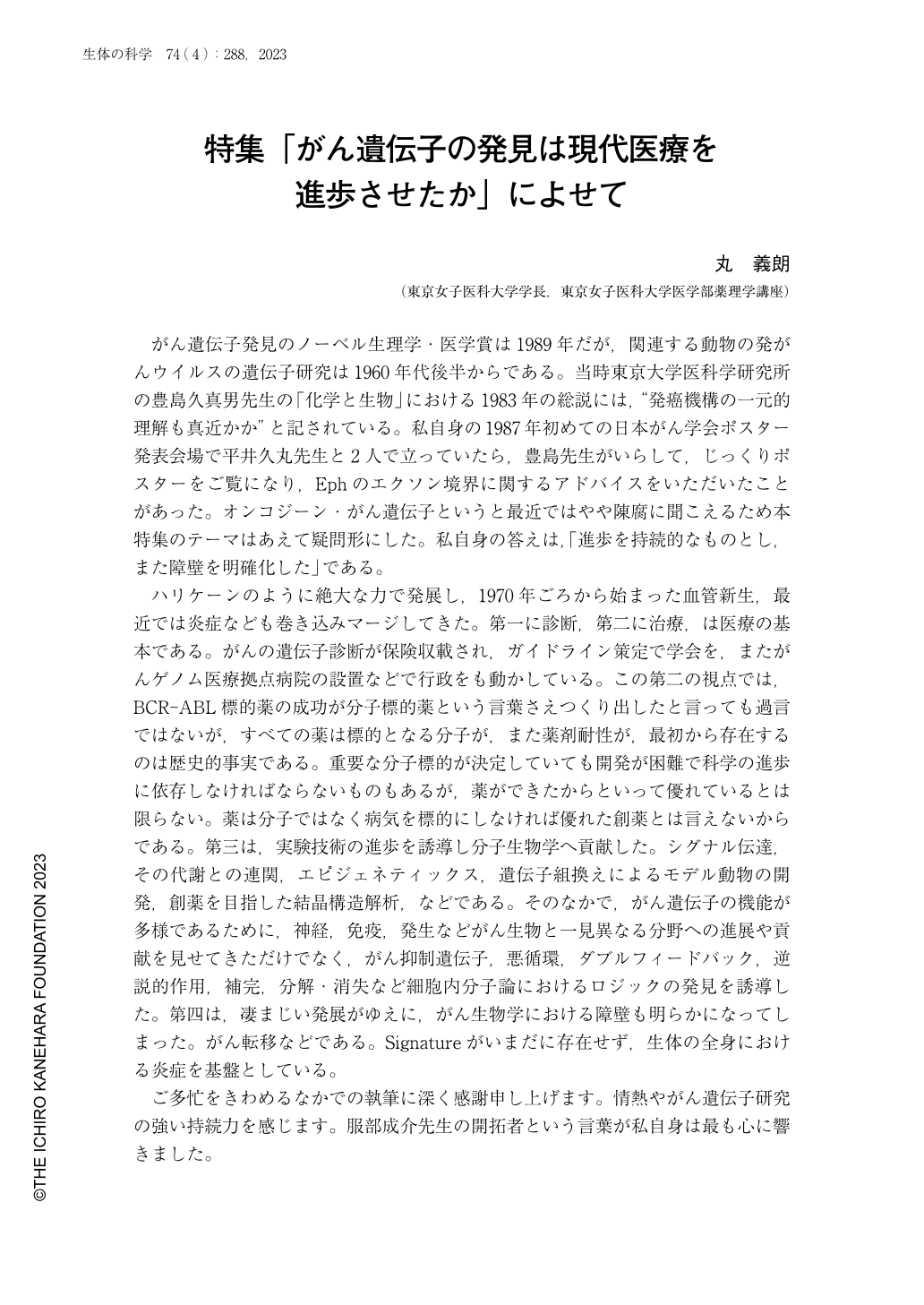
Copyright © 2023, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.


