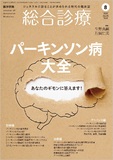- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
パーキンソン病は進行するに従って、ウェアリングオフやジスキネジアなどの運動合併症を生じる。これは、目標治療域が狭まってしまうことが一因で、通常の内服薬を用いた治療では十分な治療が困難となる。この状態で症状を安定化させる治療として、デバイス補助療法(device aided therapy : DAT)が考案されてきた。
歴史的には、まず頭蓋内に刺激電極を留置する脳深部刺激療法(deep brain stimulation : DBS)が考案され、視床下核(subthalamic nucleus : STN)や淡蒼球内節(internal globus pallidus : GPi)を標的とした治療が行われてきた1)。DBSの有効性については十分なエビデンスが構築されてきたが、DBSには認知機能や耐術能などへの問題が生じる懸念があった。ここで、経口治療薬では数十年にわたってドパミン受容体への持続的刺激(continuous dopamine stimulation : CDS)と呼ばれる、目標値領域における適切で持続的なドパミン補充が目標とされてきた。そしてCDSを達成するための持続的なドパミン送達(continuous drug delivery : CDD)を実現するべくポンプを用いた治療が開発され、レボドパ/カルビドパ持続経腸療法(levodopa-carbidopa continuous infusion gel : LCIG)や、ホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注射療法(continuous subcutaneous infusion : CSCI)を用いた治療が臨床応用された2,3)。そのため現在は、DBS、LCIG、CSCIという3種類の選択肢が存在する。
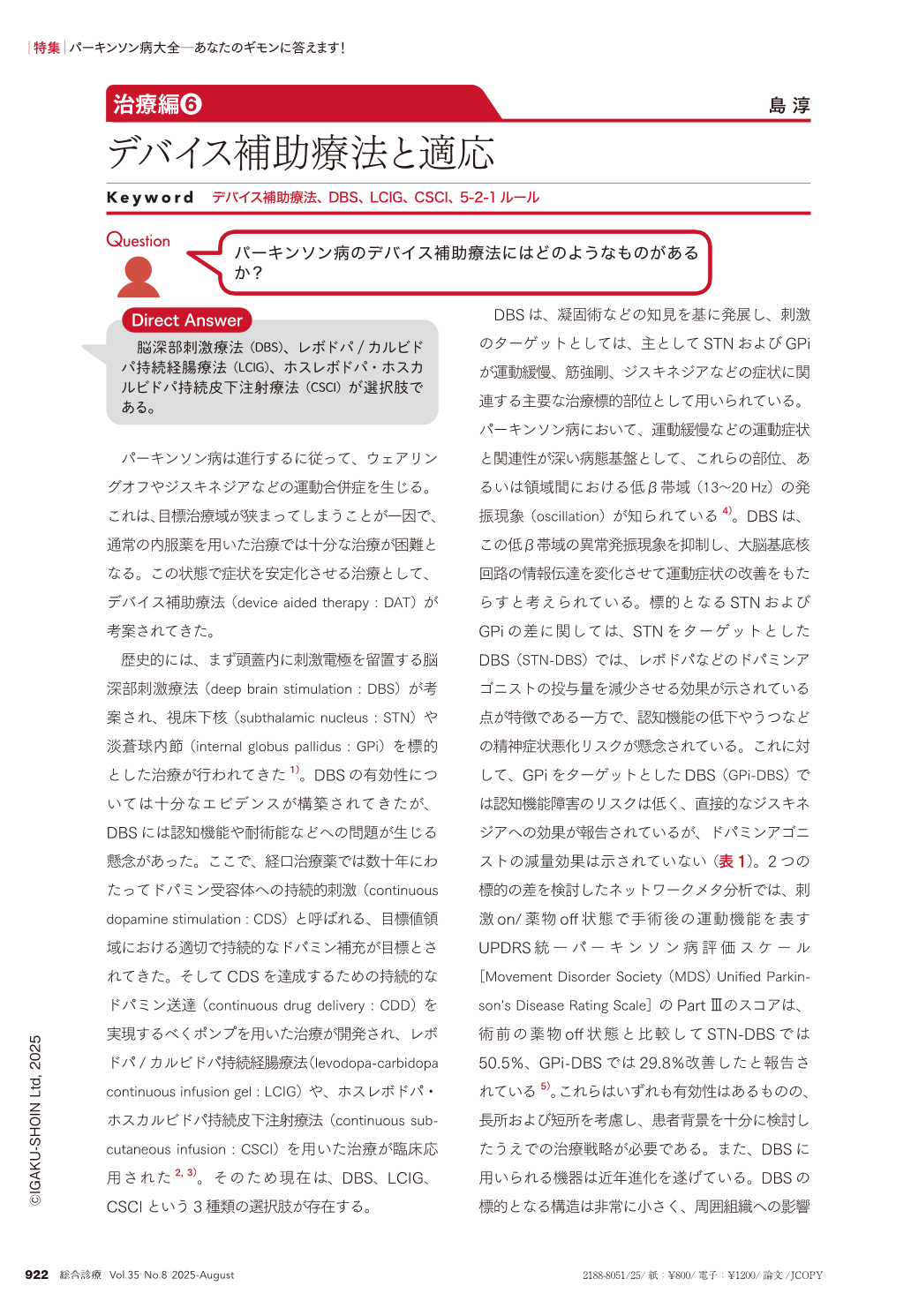
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.