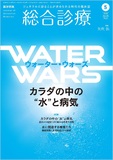Editorial
〔エピソードⅡ〕カラダの中の“水”と病気
矢吹 拓
1
1国立病院機構 栃木医療センター
pp.471
発行日 2025年5月15日
Published Date 2025/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.218880510350050471
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
紀元前5世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスは、体を構成する基本的な要素として「四体液説」を唱えた。血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の4つである。これらのバランスが健康を司り、その乱れが病を引き起こすという理論は、その後、近代医学に至るまで長く影響を与えた。ヒポクラテスも「カラダの中の水」に大いに着目していたのである。
ヒトの体重の約60%は水分であり、その多くが細胞内液と細胞外液に分かれて分布している。体液は電解質や蛋白質、ホルモンなどを運びながら全身を循環し、物理的な支持と化学的な均衡を保っている。通常は均衡が保たれている水分のバランスが一度崩れると、さまざまな病態が姿を現す。人体において水は、単なる「液体」ではない—それは、生を支える場であり、病を媒介する存在でもある。本特集『ウォーター・ウォーズ』はエピソードⅠ『ストーン・ウォーズ』に続くシリーズ第2弾として、「カラダの中の水と病気」にスポットをあてたものである。
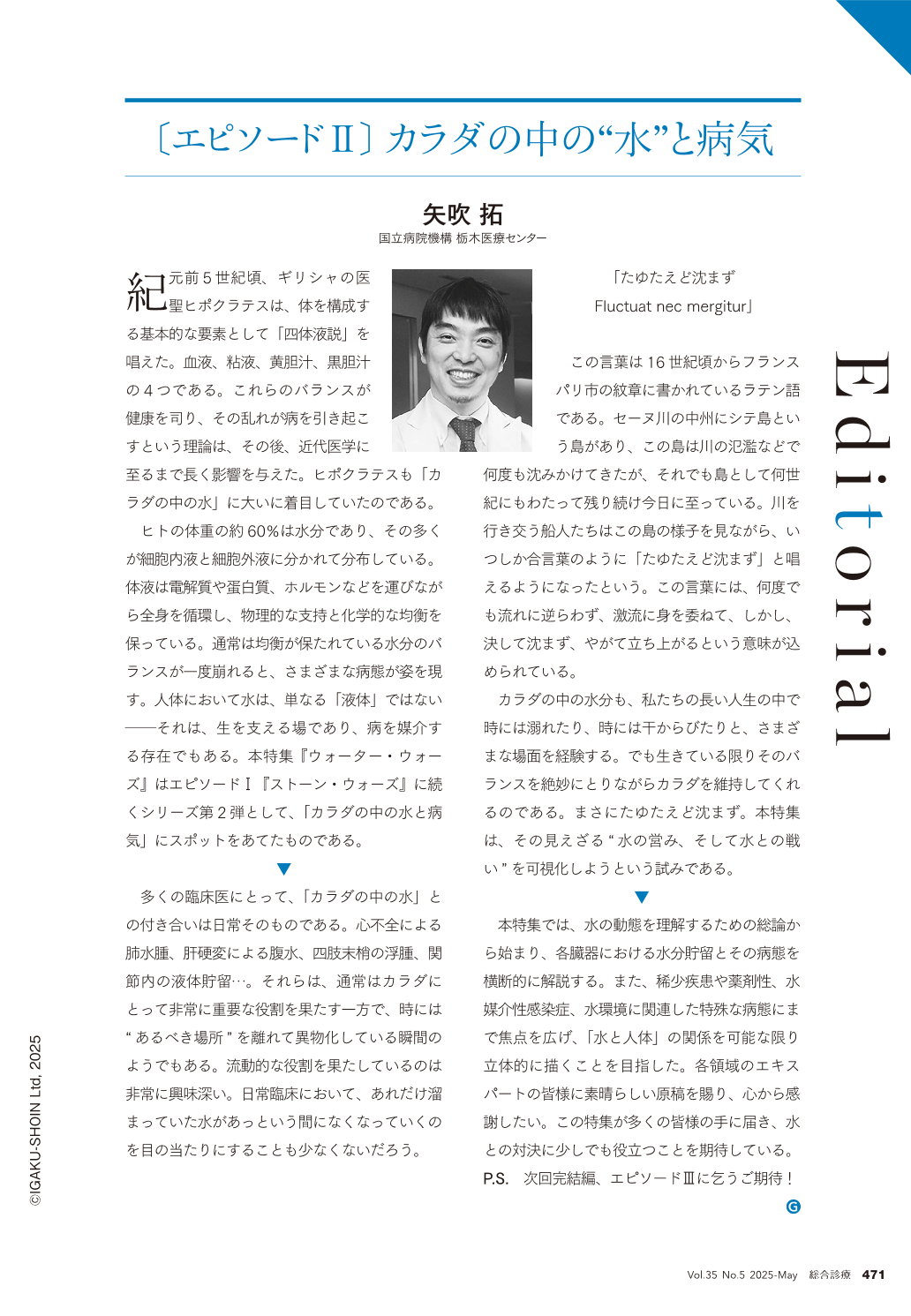
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.