特集 薬物治療の質向上
はじめに|質の高い患者ケアを支える処方マネジメントのエッセンス—質向上とそのための協働,さらに先にあるもの
榎本 貴一
1
Kiichi ENOMOTO
1
1練馬光が丘病院 薬剤室
pp.205-208
発行日 2025年3月1日
Published Date 2025/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.218804090120020205
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
なぜ薬物治療の「質」なのか
「同じ疾患の患者でも,担当医によって患者ケアのプラクティスが異なることに違和感がある」。当時同じ病院に勤務しており,本特集でも第1章の執筆をお願いした小坂 鎮太郎先生からのその言葉に,はっとさせられるとともに強く共感したことを今でも覚えています。
例えば,脳梗塞の二次予防のための抗血小板薬やスタチンに関して,どの薬剤をどの程度の用量で使用するかは,担当医の裁量に任せられています。確かに,同じ病名でも患者ごとにその病態や背景,周辺を取り巻く環境,価値観が異なるため,医療は個別化が必須であり,担当医の裁量で標準治療をアレンジすることが求められます。しかしながら,開始された処方がその後も見直されず漫然と継続されていたり,日本での(もしくは施設,個人での)慣習を理由に標準治療と異なるものが患者に提供されていたり,処方内容に合理的といえる根拠がなかったりする例も,筆者はしばしば経験していました。それまで筆者は,担当医のポリシーや経験,裁量などに忖度をしながら薬剤師としての臨床業務を行うことにほとんど疑問を抱いてきませんでしたが,冒頭の小坂先生の言葉から気づきを得てからは,目の前の薬物治療の「質」に着目するようになりました。そしてさらなる理解のため,「医療の質・患者安全」という領域を自発的に学ぶようになったのです。
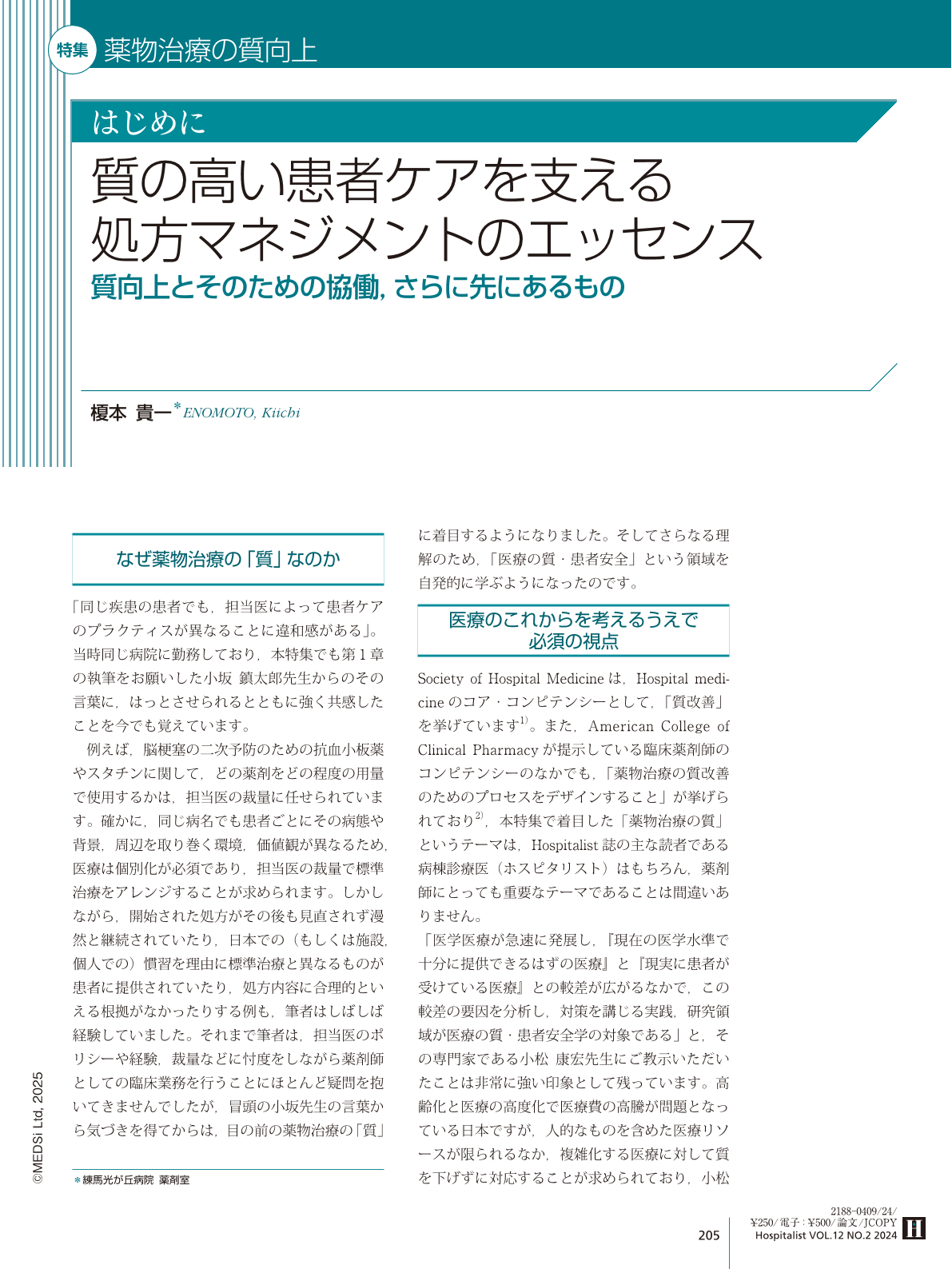
Copyright © 2025, MEDICAL SCIENCES INTERNATIONAL, LTD. All rights reserved.


