連載 原著・過去の論文から学ぶ・12
分離脳
酒井 邦嘉
1
1東京大学大学院総合文化研究科相関基礎科学系
pp.383-385
発行日 2025年4月1日
Published Date 2025/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.188160960770040383
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
原著との出会い
Sperry RW: Cerebral organization and behavior. Science 133: 1749-1757, 1961
ロジャー・スペリー(Roger Wolcott Sperry; 1913-1994)は,神経科学の基礎を築いた先駆者の一人である(Fig. 1)。特に分離脳(split brain)に関する一連の研究は,左脳と右脳の機能差として一般にもよく知られる。分離脳とは,脳梁線維(corpus callosum)の切断あるいは未形成によって,両半球が分離した状態のことである。スペリーは,「分離脳は多くの点で2つの別々の脳のようにふるまい,新たな研究の可能性をもたらす」1)と明快に述べている。
この原著を私が初めて目にしたのは物理学専攻の大学院生時代で,脳という不思議な世界に興味を持ち始めた頃だった。脳の高次機能を研究対象とするにあたって,まず記憶の痕跡(「エングラム」engram)が脳のどこにあるのかという問題を明らかにしなくてはならないと私は考えた。もし記憶が脳全体に広がって保存されるなら,脳のどこを研究の対象としたらよいかわからなくなってしまうからだ。この論文はそうした素朴な疑問に正面から答えるものであり,博士課程で大きくテーマを変えて医学部の生理学教室に移るという一大決心を後押ししてくれた。
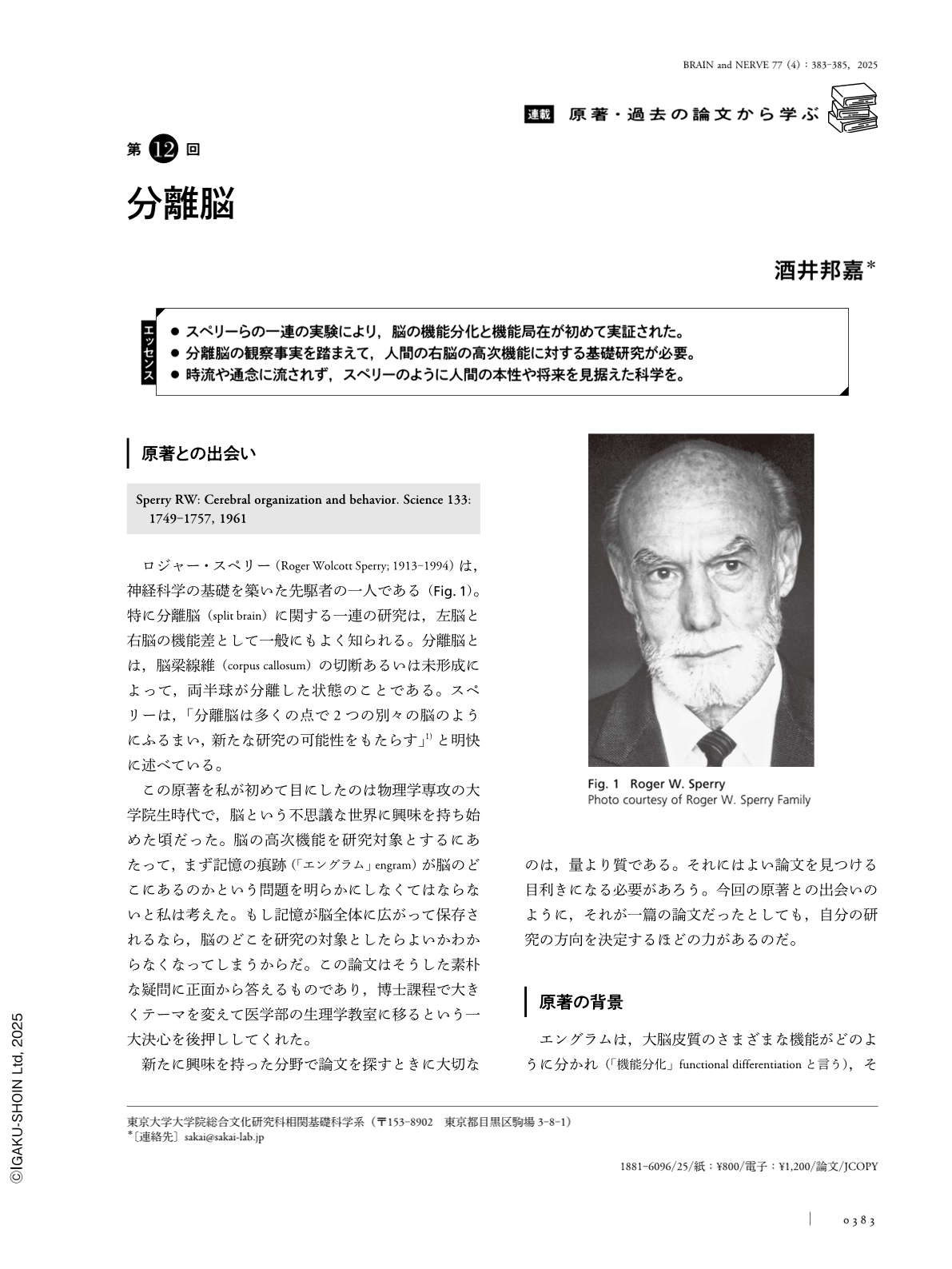
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


