緩和ケア医のひとり言・6(最終回)
住み慣れた家を離れるとき
藤井 勇一
1
1埼玉県立がんセンター・緩和ケア病棟
pp.1020-1024
発行日 2000年12月15日
Published Date 2000/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688902529
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
この連載の話をいただいてちょうど1年が経過し,あっという間に最終回を迎えてしまった.この間に,僕が働いている緩和ケア病棟は満2歳を迎えた.2年間のうちにのべ400人近い方々が入院し,200人弱の方々が旅立っていかれた.“家へ帰りたい”と希望された患者さんの多くは,外泊や一時退院という形でその希望を果たしたが,在宅での看取りとなったのはわずか数人に過ぎない.もちろん,在宅で看取れたからよくて,病院だからよくないというわけではない.しかしながら,患者本人が自分の家で最期を迎えたいと願ったら,それを支えてあげたいと思っている.
“家で最期を”と願う患者が,家にいられるためには何が必要なんだろう?逆に,家を離れなければならないのはどんなときだろう?“入院が必要”と考える基準は,病院と地域の医療者の間で,また,家族と医療者の間で,時には家族と患者自身との間でも微妙に食い違っていることが多かったように思う.
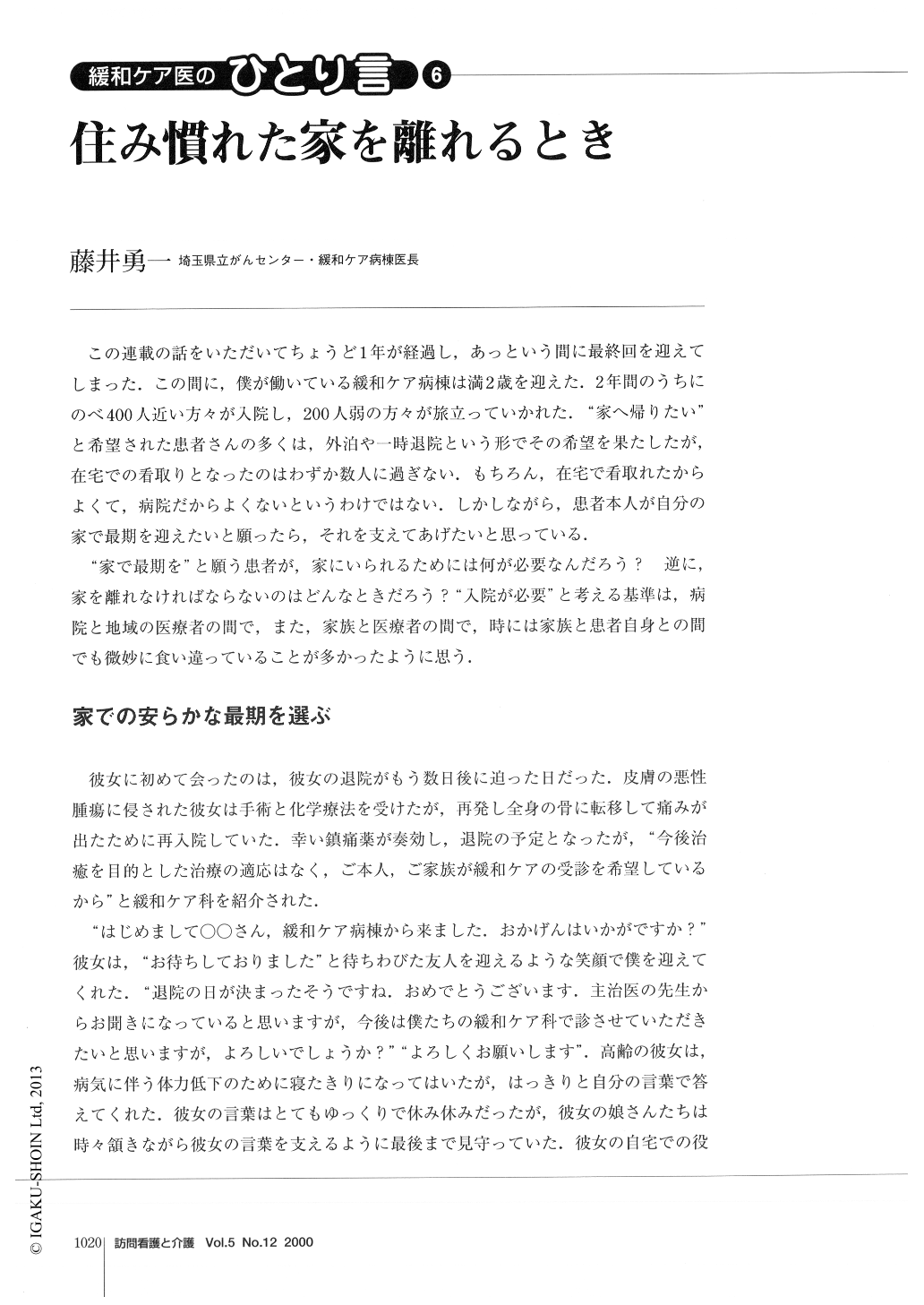
Copyright © 2000, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


