発行日 1950年5月15日
Published Date 1950/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906649
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
こんな歌とも“ぬた”ともつかぬものを日記帳の端に書いた。いまから29年前筆者がサナトリアムで療養中のことである。“朝の風吹く”で大にサナトリアムの實感を出したつもりだつたのである。Bridgeof weirというのはグラスゴーから北方に汽車で數時間の處にある小邑である。その郊外の原野に立つているのが私の數カ月を過したサナトリアムである。スコツトランドの冬は寒い。この大高原に風は容赦なく吹きまくる。サナトリアム療法は“風とともにある”療法といいたい。毎朝容態を聞きに來ろ看護婦は外套を深々と着ている。室内で外套を着ることはいまの日本ではあまり珍らしいことではないが外國では非常な異例である。手袋だけは脈を取る必要上はめるわけに行かない。晝夜開け放しの窓から遠慮なく吹きこむ風に忠實な看護婦の手は總毛立ち折角たしなみよく束ねた髪の毛も亂れるようになびく。そこで“看護婦の髪に朝の風吹く”である。こう長々と注釋を要するようでは筆者の歌もはなはだ心細い。
グラスゴーの大學に通つていた私は始めてのスコツトランドの冬にあてられたのかそれとも柄にない勉強が崇つたのか風邪を引きこんだ揚句微熱がどうしても除れない。朝は平熱であろが夕方になるときまつて體がだるく頭が重くなる。測つて見ると7度3,4分ある。臥床するほどでもないが寒いのがいけないのだろうと思つてマスクをかけ窓を閉め切りストーヴに首を突きこむようにして毎夜を過したがどうしても癒らない。
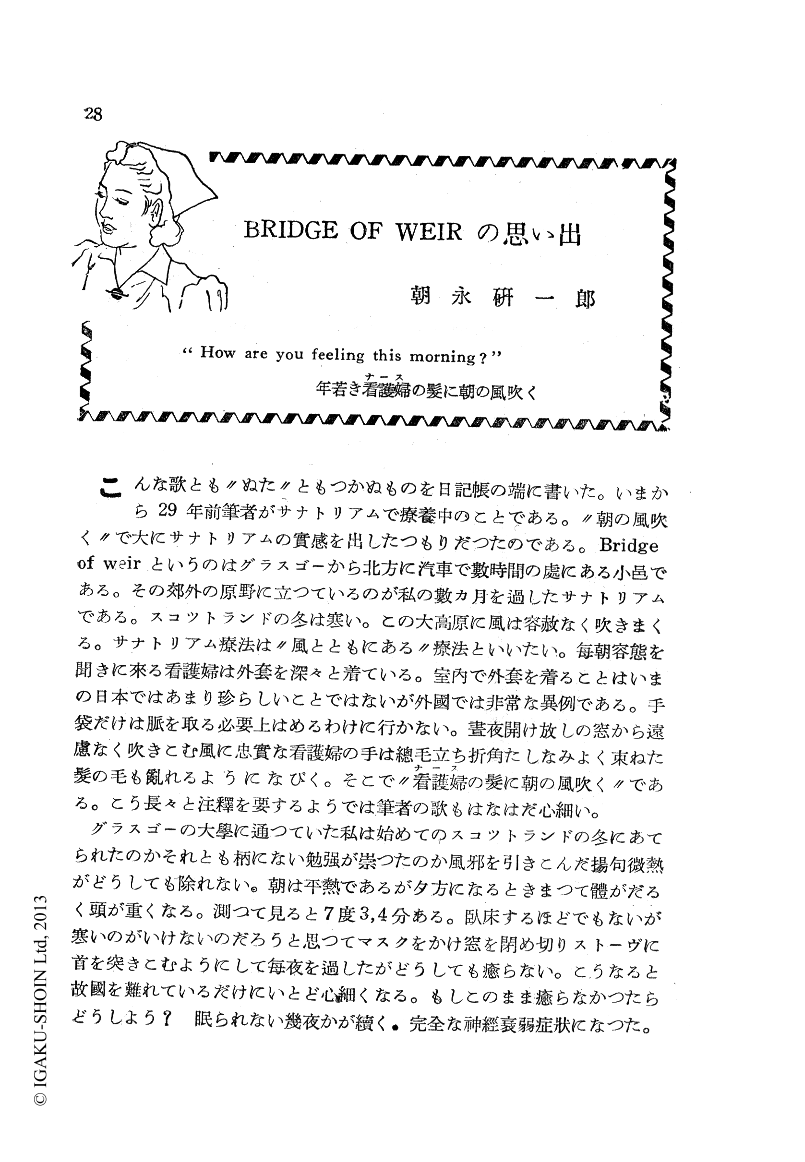
Copyright © 1950, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


