Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
Ⅰ.はじめに――治療方針の決定をめぐって
本誌前号において,麻痺性構音障害(1)と題して麻痺性構音障害の診断学的基礎ならびにリハビリテーションの基本方針について述べた.今回は,とくに代表的な疾患群をとり上げ,言語機能を中心としたコミュニケーション機能のリハビリテーションの問題について,できるだけ具体的なアプローチを目指す立場から述べてみたい.
これに先立って,多少前号と重複するが,治療方針の決定と,それに関わる要因をもう一度整理しておく.
前述のとおり,麻痺性構音障害のタイプは,主として言語病理学的な評価によって鑑別できるが,これと並行し,時には先行して医学的側面の評価が不可欠である.これには,発声・構音に関与する各器官別の機能の現状を把握し,さらに各器官同士の協調性を含めて綜合的な評価を与えるものである.その指針については,これまでの文献1)を参照されることが望ましいが,いずれにしても治療方針の決定には,的確な評価が必要であることをあらためて強調したい.なお,全身的な背景を含めた神経学的評価がすべてに先行すべきであることはいうまでもない.
治療方針の決定にはいくつかの段階があるが福迫2)あるいは柴田3)は,これを臨床に則した立場から整理して述べているので,これらの記載を参照しながら考えてみたい.
まず,患者あるいは疾患の種類によって,医学的治療の可能性がある場合には,その適用について積極的に考慮するという段階がある.たとえば薬物療法が有効な場合としては,パーキンソン症候群に対するL-Dopa製剤などの投与がその例であろう.このほかにも特殊なものとして重症筋無力症に対する抗コリンエステラーゼ剤,ウイルソン病に対するペニシラミンなどの投与がある.さらに最近では小脳変性症にTRH(Thyrotropin releasing hormone)の投与が試みられている4).
医学的治療としてさらに積極的なものに,手術的療法の適用がある.このうち最も有名なものとしては,口蓋帆挙上障害による鼻咽腔閉鎖不全に対し,咽頭後壁の粘膜筋弁を翻転して口蓋帆に縫着する,いわゆる咽頭弁形成術がある.この手術は,原則として進行性の疾患には適応が少ないが,仮性球麻痺,眼咽頭ジストロフィーの症例の中には有効例も認められている.また,直接コミュニケーション機能に関わるものではないが,生命の維持,さらには発声・構音を妨げる分泌物(唾液を含む)処理の促進のために,輸状咽頭筋切断ないし部分切除術を施行して,食道への交通を改善する場合もある.また,筋萎縮性側索硬化症の重症例(進行例)に気管切開を施行することも,全身管理上の必要性を先行させて適応決定に踏み切るべきであろう.なお,さらに特殊な手術として,仮性球麻痺で強い喉頭絞扼(声帯過内転)を示す例に支配神経である反回神経内転筋枝の1部を切断する試みもあるが,その適応については今後の検討が必要であろう.
このほか,医学的治療とリハビリテーションの中間的なものとして,補装具の使用がある.これは後から述べるコミュニケーションの補助器具あるいは代行器具とは異なって,あくまでも構音機構を補助するもので,その例としては,口蓋帆挙上障害による鼻咽腔閉鎖不全に対して用いられるpalatal liftや,下顎の脱力降下を防ぐchin capなどがある.これらについては,後からあらためてふれる.
次の段階として,実際に構音訓練を施行すべきか否かを判断する必要がある.この判断は,当初なかなか困難な場合があり,暫く治療的訓練を行った後に最終決定が下されることもある.しかし一般には,次のような例を除けば,ほとんどすべての麻痺性構音障害症例に,構音訓練の適応があると考えられている.その除外例としては,
1)訓練に対して拒否,無関心,意欲低下などの反応を示したり,あるいは全身状態不良で訓練に耐えられなかったりする例で,訓練実施が不可能である例.
2)精神機能低下(痴呆を含む)が著明で訓練効果が期待できない例.
3)発症後からの期間に他施設などで十分な構音訓練が施行されており,とくに訓練を追加する必要がないと考えられる例.
などである2).
以上のような段階を経て症例の選択と最終的診断がつけられ,ここで始めて個々の症例についての治療方針が樹てられることになる.
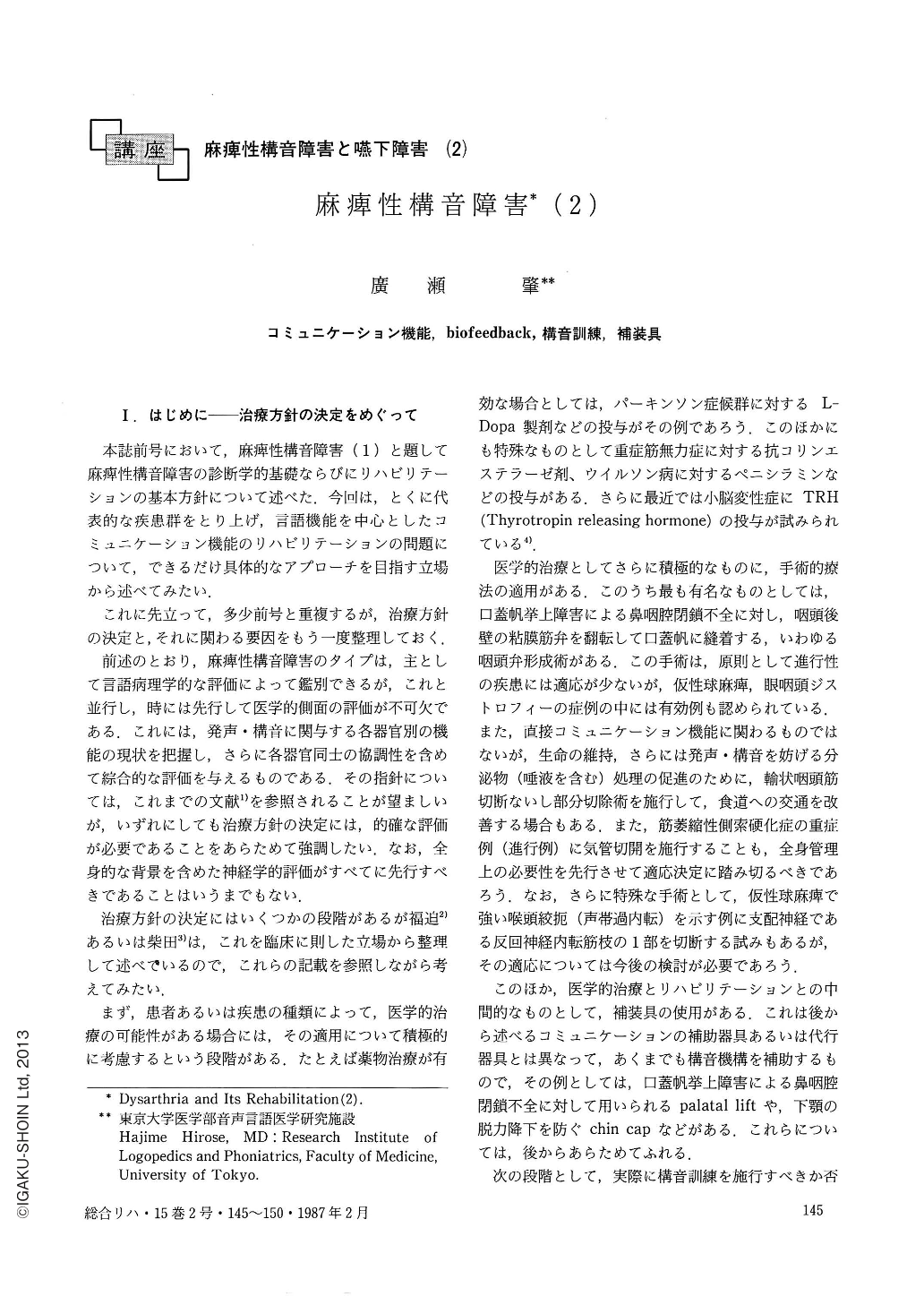
Copyright © 1987, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


