Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
はじめに
最近,脳性麻痺(以下CPという)など中枢性の運動疾患に対し,神経生理学的な概念にもとづく治療が,多くの施設で採り入れられてきている.それまで主流となっていた整形外科的な治療訓練にとって代りつつあるのは,中枢性の運動障害の性質についての認識がなされてきた結果であると思う.即ち整形外科的疾患あるいは,末梢性の運動障害に於ける,筋力の低下,関節可動域の減少などの量的な障害は,中枢性の疾患に於いては,二次的な障害としてとらえられ,運動の質的な障害に問題を置いている.
ボバース法による評価も,こういった中枢性の運動障害の特徴をとらえた上に,なされるものであり,整形外科的治療訓練に際しての評価にみられるような,単なる運動機能レベル,筋力テスト,ROMテストといった量的評価よりむしろ,運動の質的障害についての情報を与えるように意図されている.
評価はあくまでも,治療に際して,正確な情報を与え,治療の目的,プラン,テクニックに指針を与えてくれるものでなければならない.評価と治療は密接に関連されるべきもので,単に検査のための検査に終ったのでは,意味がない.患者の運動機能を全体として,とらえるのではなく,疾患部位の運動障害の性質,程度,原因をよく分析することによって,治療との結びつきがなされるのである.
ボバースは,CPなど中枢性の運動障害を運動の協調性に問題があるとしており,従って評価の中心は,筋緊張の異常に伴って起る姿勢・運動パターンの異常性を分析することである.これらについては,治療中も常に注意深い観察が要求される.その際,身体各部の個別的な観察でなく,身体全体の運動の協調性の異常をとらえていくことが,ボバース法による評価の原則である.
ここで,ボバース法による評価内容のみを述べたのでは,意味がないと思うので,評価の基礎となる,ボバースのとらえるCPの運動障害の性質と,治療概念について簡単に述べたいと思う.
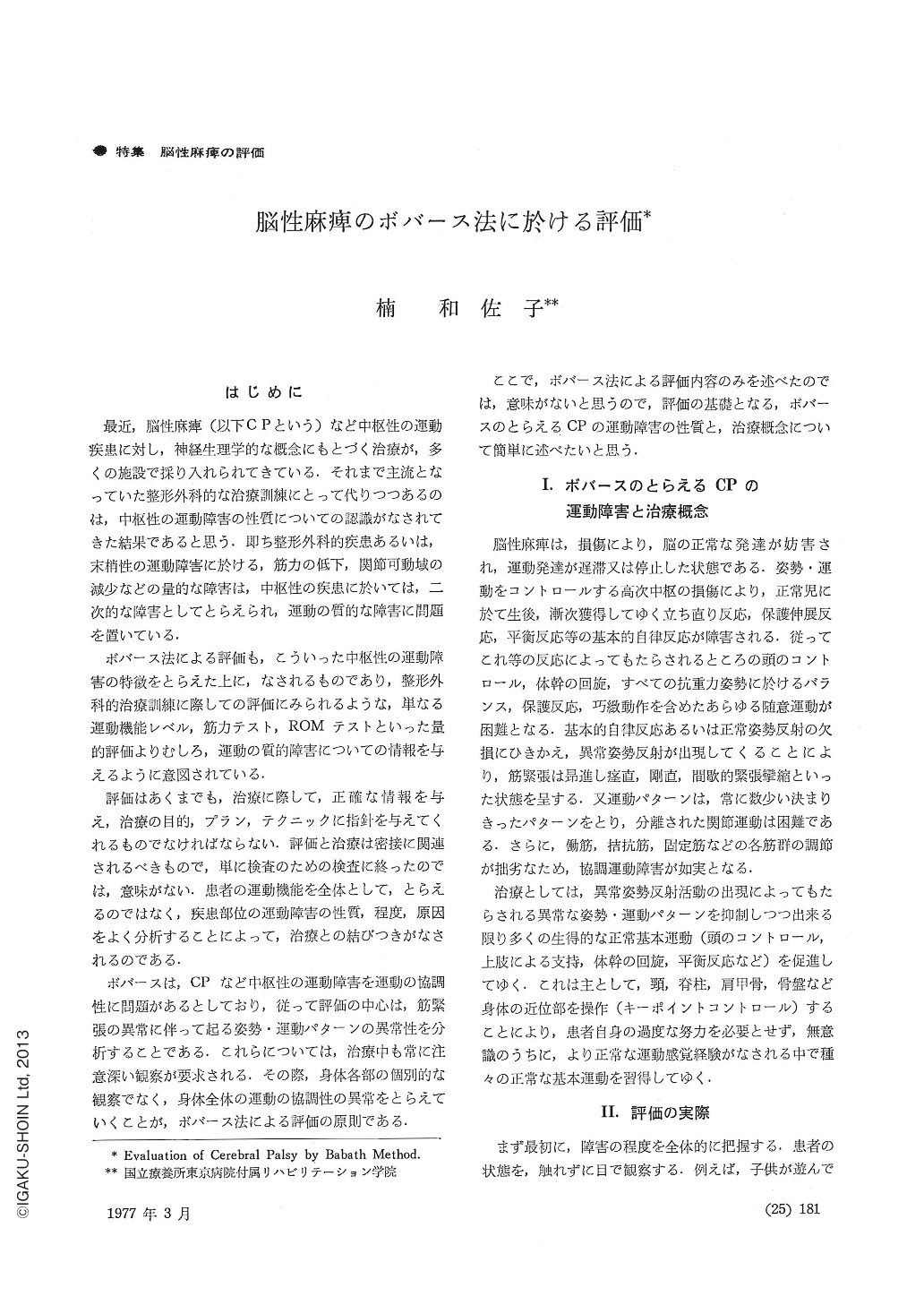
Copyright © 1977, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


