Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
Ⅰ.はじめに─小児虐待の診断の特殊性─
小児虐待による頭部損傷は致死率も後遺症の頻度も高く,大きな社会問題であるとともに,われわれ医療者にとって診療上も,子どもの保護という点でも重要である.しかしながら,医学生の時代から習ってきた臨床医学の診断プロセスである「まず問診をして,理学的診察をし,異常部位や鑑別疾患を考慮したのちに,それに沿って画像診断を行う」という方法では小児虐待の診断をつけることができないことが多い.なぜなら,この王道の診断プロセスは患者あるいは代わりに状況を説明する保護責任者は医師・看護師などの医療者に対し嘘をつかないという患者─医師間の信頼関係に基づいているからである.考えてみていただきたい.虐待を行った保護責任者がその子を病院に連れてくる場合に「私がいついつこのように虐待して具合が悪くなりました」と最初から正直に話すことがあるであろうか? ある英文の小児画像診断の教科書によると小児虐待はそのほとんどが6歳以下に起こり半数以上は1歳以下に起こると記載されている16).つまり半数以上は自分でほとんど言葉を話せず,ほとんどの被虐待児が状況を的確に説明できるとは考えられないのであり,たとえ話せる年齢であっても初対面の医療者に親の行為を伝えることはまずないのが現実である.つまり,問診で正しい病歴が得られることはほとんどないのであり,どんなに善良そうに見える両親であろうとも,けがをした子どもを見たわれわれ医療者が「少しでも虐待の可能性はないだろうか?」と毎回疑わない限り小児虐待の発見は前進しないのである.また,医師は児童福祉法25条により,被虐待児(疑いを含む)を診療した場合には児童相談所に通告する義務がある.疑いがあれば通告しなければならないのであり,虐待でない可能性があるからという理由で通告しないのは厳密には違法なのである.
画像診断は客観的であり,虐待診断の契機にも証拠にもなり得るとともに虐待以外の鑑別疾患を診断するためにも有用である1).前述の教科書では被虐待児の2/3は放射線学的に何らかの有所見をもつとも書かれており,正確な病歴を得ることがほとんど不可能な小児虐待の診断における画像診断の意義は大きい.
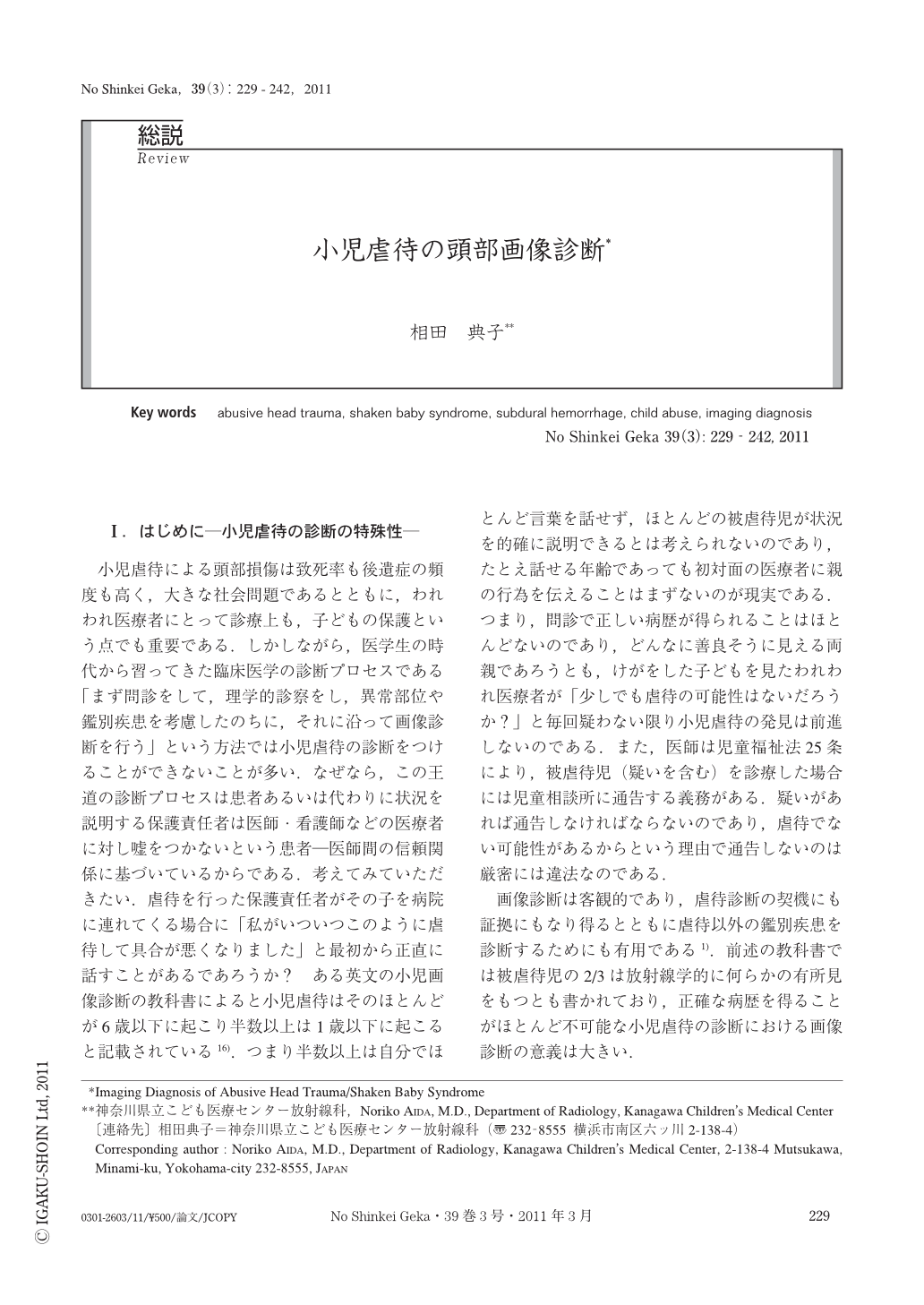
Copyright © 2011, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


