特集 流早産の原因と治療の問題点
妊娠初期習慣性流産原因における着床部位異常と外科的治療の可能性
官川 統
1
Osamu Hirokawa
1
1東京大学医学部附属病院分院産婦人科
pp.721-725
発行日 1967年9月10日
Published Date 1967/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409203761
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
習慣性流早産の治療として10年前までは薬物療法(主として黄体ホルモン)が効果判定のはなはだあいまいのまま,惰性的に行なわれていた感がある。しかして,頸管無力症の概念の提出から現在の頸管縫縮術が漸次完成され,その成績も目ざましいものがあり1)〜9),とにかく妊娠4ヵ月以降の流早産はこの治療法の手に委ねられるようになつている。したがつて習慣性流早産のうちで今後問題となるべく取り残されている病型は妊娠2,3ヵ月に繰り返し流産するもの,および流早産時期が一定しないもの(ただし後者でも妊娠4ヵ月まで幸運にも維持されれば,その後は頸管縫縮術が引受けることになる)の2者である。
さて妊娠2,3ヵ月の流産の原因は今まで数多く示されているがいずれも一般の賛同を得ていない,また切迫流産の予後についてもはつきりした指標が同様得られていない。腟脂膏検査,尿中ゴナドトロピン,同プレグナンヂオール,その他のステロイド測定による所見は胎内死亡,不全流産の2次的結果であり,原因ではない,ゆえに以前提唱された,尿中プレグ値の低下をもつてする黄体ホルモン治療の合理性は現在否定されている。実際的に臨床経験からいつて現在の切迫流産の予後を正確に卜することは不可能に近く,俗諺ではあるが"妊娠が維持されるものは維持されるし,維持されぬものは維持されぬ"という言葉がまことにあてはまる感がある。
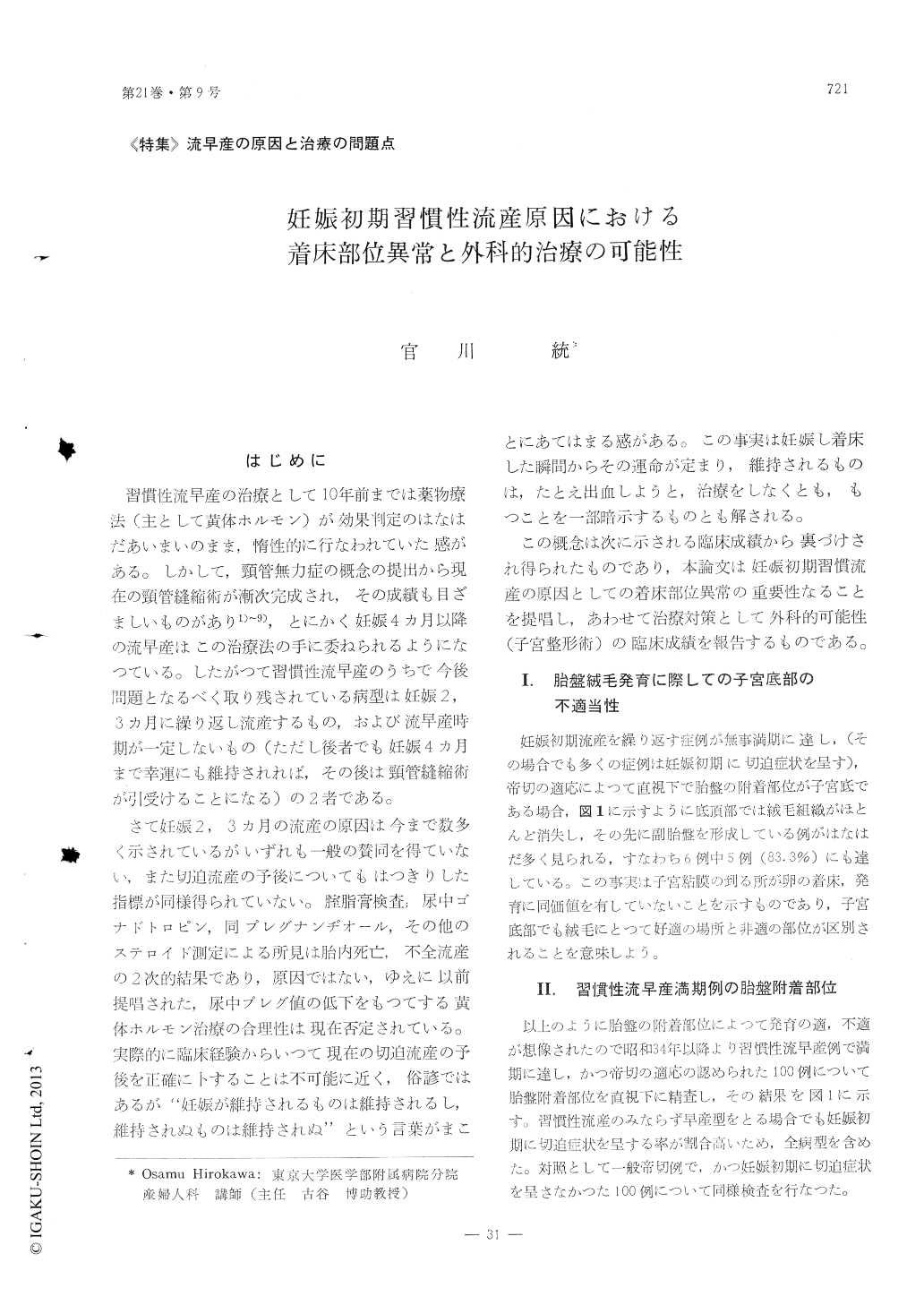
Copyright © 1967, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


