特集 新生児の研究と臨床--第1回新生児研究会シンポジウム
新生児黄疸
〔追加 1.〕黄疸計による新生児黄疸の逐日的観察,他
山村 博三
1
,
清水 藤市
1
1聖バルナバ病院
pp.158-161
発行日 1964年2月10日
Published Date 1964/2/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409202990
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
新生児皮膚黄疸と血清ビリルビン値との関係について,本年4月の医学総会において発表したが,すなわち日本色彩研究所発行の「色の標準」より5色を選び,日本人新生児に適合する「Icterometer」をつくり逐日的にその黄疸度を測定すると,Color No.の大なるに従つて,血清ビリルビン値も上昇することを知つた。例えばNo.3以上になると,血清ビリルビン値は20mg/dlを越すものが増加するのを認めた。今回は逐日的に測定したIcterometerの読みを集めて,その平均値を求め,427名の新生児,すなわち成熟児,巨大児,未熟児,骨盤位娩出児について,黄疸度の推移および母体のキニーネ投与,非投与群の影響を調査した。その結果,投与群も非投与群も(我々は0.15g×4,総量0.6g投与している)黄疸度の推移は変らず,この程度の投与では影響なしと思われた。大体黄疸度は5〜6日がピークでその後は漸時消褪し,同時に血清ビリルビン値も下降にむかうようである。しかるに未熟児は,そのピークも7日目以後に移動し黄疸がながく血清ビリルビン値も黄疸度も他より高い値が得られた。これはさらに黄疸の追求に細心の留意が必要なることを示していると考えられる。骨盤位は他のものと同様の経過をとり骨盤位だから黄疸が強くなるという結果は得なかつた。
以上,黄疸度を逐日的に観察,記録することにより各々の児に対する黄疸の大凡の傾向が知られ得るものと考える。
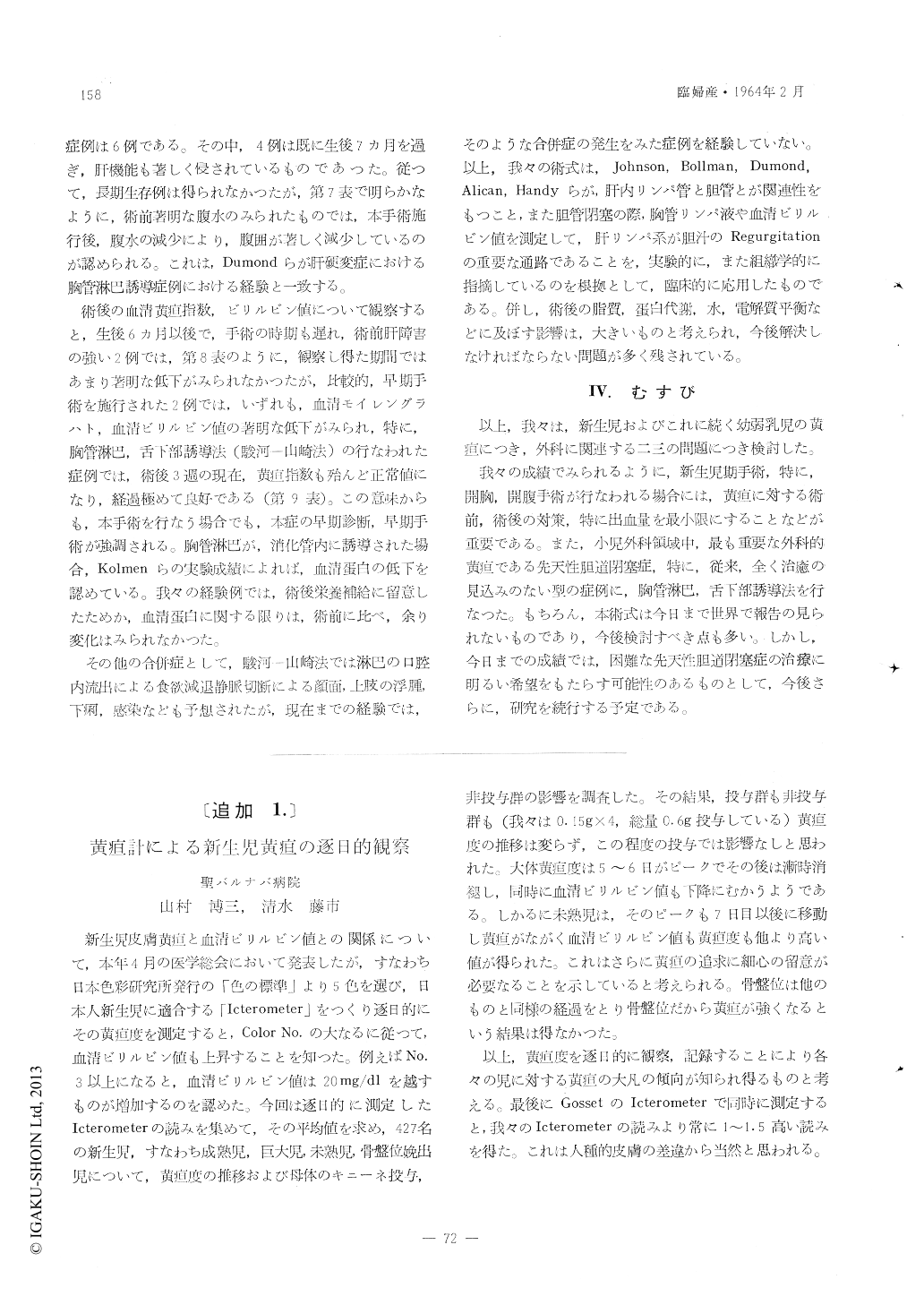
Copyright © 1964, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


