- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
子宮体癌の術後補助療法のこれまでの経緯と現状
子宮体癌は比較的予後良好な癌で,約90%が子宮内に限局した早期癌(I, II期)であるため手術療法が治療の主体ということもあり,術後治療についての明確な指針はなく,各施設が独自の基準で放射線療法あるいは化学療法を行ってきた.欧米では従来より放射線療法が術後補助療法の標準であった.FIGO annual reportによると体癌術後の治療は放射線療法が化学療法に比し約7対1と圧倒的に多くなっている1).特にIc~II期の早期症例では化学療法は約1~2%にしか行われていない.NCCNガイドラインでもI期ハイリスク症例に放射線療法を行うことが明示されている2).これに対しわが国では,放射線療法の副作用に対する懸念や,早期癌であっても遠隔転移が少なからずみられることから化学療法がより多く選択されてきたのが実状である.
子宮体癌の化学療法では従来よりdoxorubicinがkey drugと考えられており,その単剤での奏効率は30%前後とされてきた3).その後,卵巣癌に対するプラチナ製剤の優れた治療効果が確認されるようになり,プラチナ製剤が子宮体癌にも使用されるようになった.プラチナ製剤の単剤での奏効率は約30%と同等であり,anthracyclin系薬剤と同様にkey drugと考えられるようになった4, 5).さらにこれらを組み合わせた多剤併用療法が試みられ,doxorubicinをkey drugとしてCDDPやCPMを併用する方法が一般的となり,CAP療法では50%前後の奏効率が報告されるようになった6~8).これらの報告を受け,わが国でもプラチナ製剤を含む多剤併用療法を術後補助療法とする施設が増えることとなった.
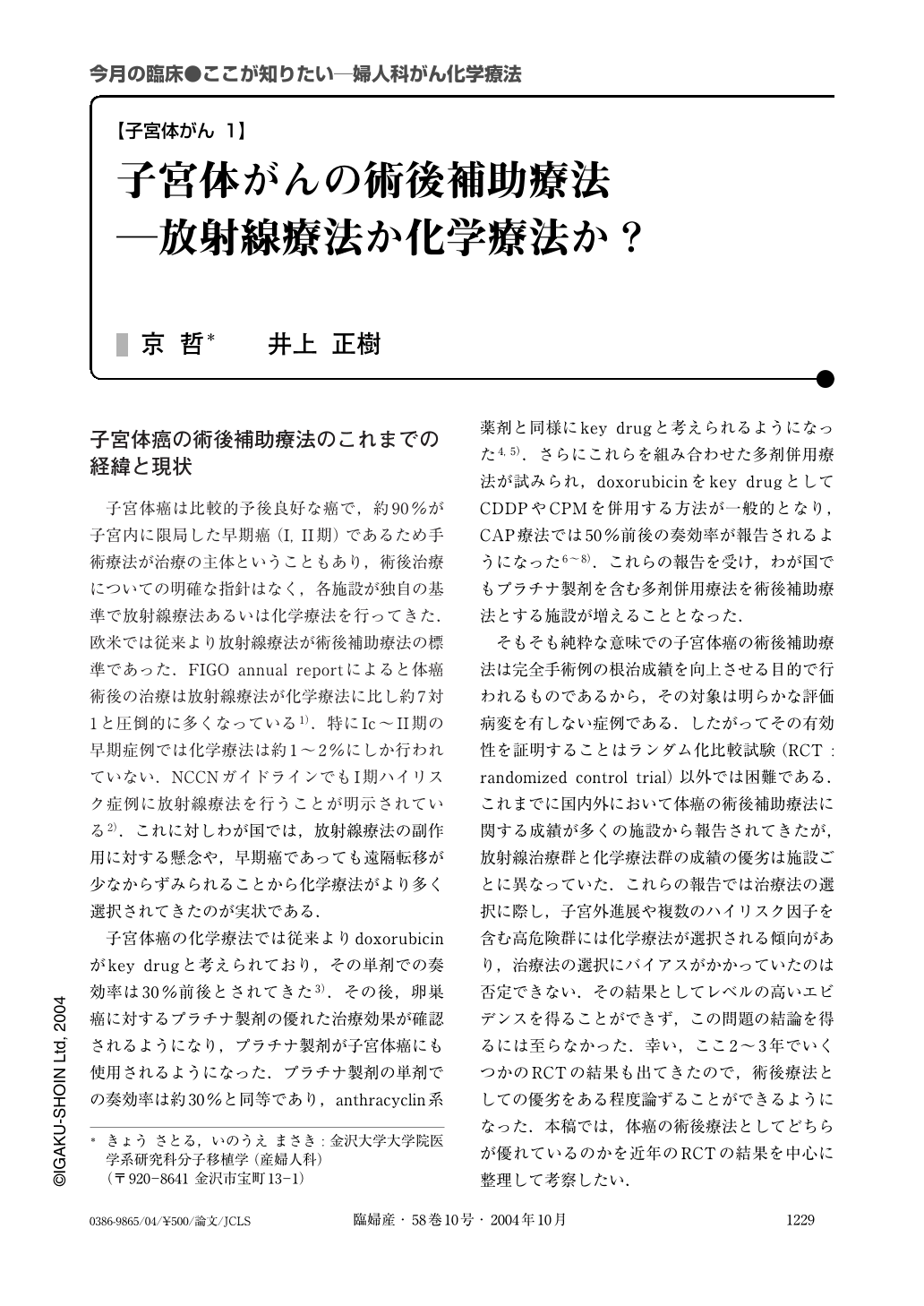
Copyright © 2004, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


