- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
種々の新しい抗生物質化学療法剤の開発,環境予防衛生の発達,栄養管理の向上等々により,古典的な強い全身反応—敗血症状,高熱,動脈血培養にて起因菌の検出—を伴う骨髄炎の例は今日においては激減の傾向にある.他方,全身症状は比較的緩やかで,倦怠感,易労感等の不定の愁訴にとどまり,局所症状も皮膚発赤,熱感,腫脹,圧痛—という古典的局所炎症徴候および症候がすべて揃うことはむしろ稀であり,この一部をのみ見出しうる様な非定型的な例が増加する傾向にある.
この様な全体的傾向の中で,患者の側に注日してみると,前述の不定の初発症状に気づいていながらも,それをかなりの時間放置しておき,疼痛が激化したり,局所熱感—腫脹が明らかになつた時点で初めて医師を訪れる場合が多い.また医師の側からみてみると,患者にあまりこれといつた定型的所見がみつからない場合が多いため,単なる関節痛ないしは関節炎とか神経痛として軽く診断を下したり,患者がこどもの場合には成長期の骨端炎として処置を施したりする.またたまたま学童期,思春期の年齢で高熱—関節痛が認められた例にはリウマチ熱を疑つてステロイドの局注,あるいは全身投与を施したり,関節穿刺にて膿液を認めた場合は化膿性関節炎を疑つて抗生物質の投与をするため,基礎疾患の症状がかえられたり,一時にかくされたりして,正確な診断の時期がより遅れてしまう結果となる.しかし数週から数カ月の治療の試みにもかかわらず,臨床症状の改善がみられなかつたり,悪化したり,またX線上に骨の変化を示してきた時に初めて骨の疾患として新たに注目を受け,種々の姑息的治療に抵抗する疾患として,慢性骨髄炎と骨腫瘍が臨床医の頭に浮かび,その鑑別を強いられるのである.この様な長い臨床的経過をもつて骨腫瘍とまぎらわしいX線像を呈した骨髄炎の症例に関する診断上の問題点を若干提起してみたいと思う.
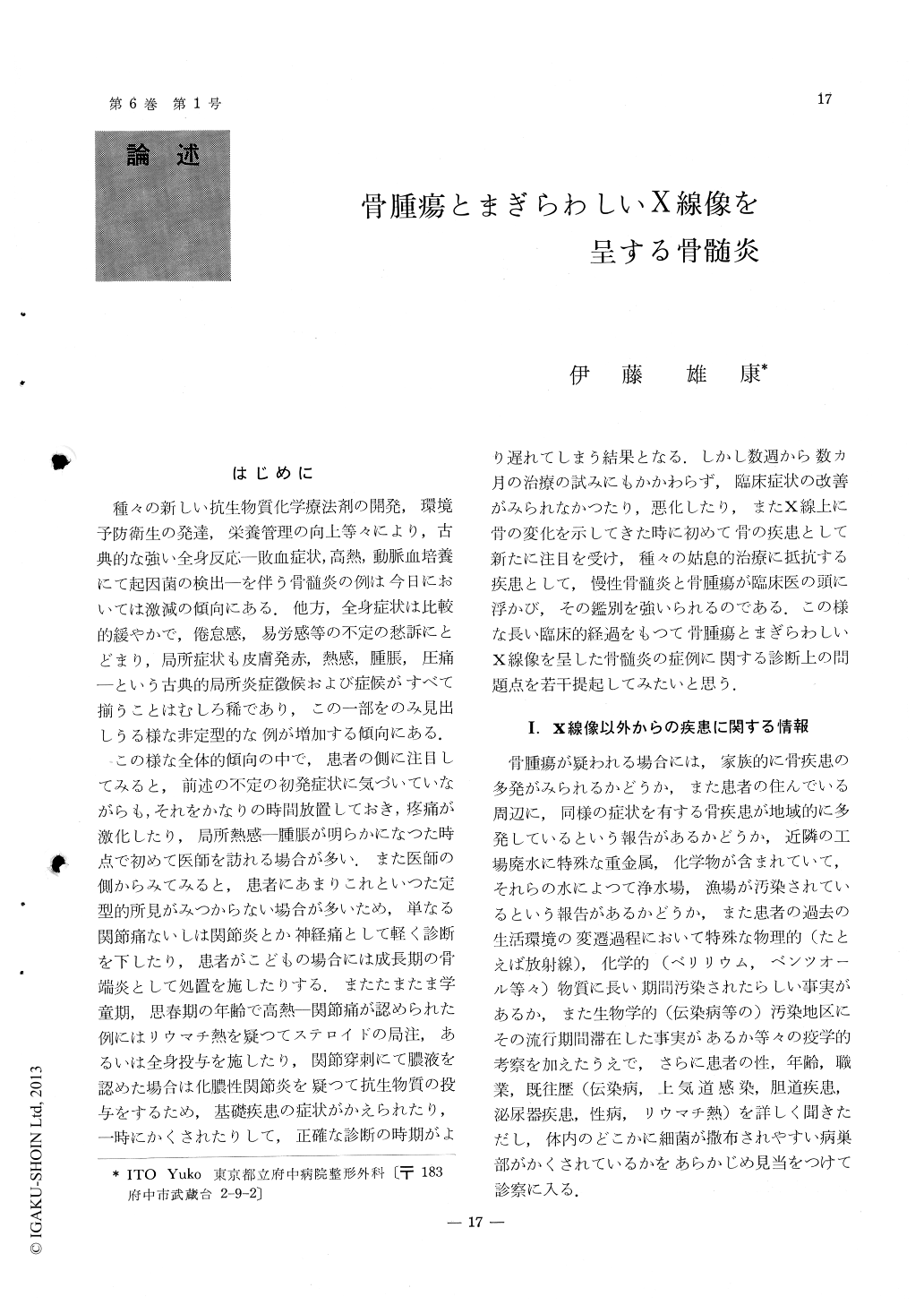
Copyright © 1971, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


