Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
はじめに
癌治療の対策は種々の方面より行なわれているが,その主題となすところは早期発見であり,病巣の外科的処置としておることは周知のとおりである.然るに現実に臨床家が直面する癌患者はその大部分が進行癌の状態にあり,発見と同時にその治療に苦慮せざるを得ないところである.もちろんこれらの進行癌に対してでもコントロールしようと図り,これまで外科的,化学療法的および放射線医学的に多大の努力が払われ,それなりに幾多の改善法が見出されてきた.著者等は癌対策の根底の一つとして,担癌生体内の癌組織を縮小化するかまたは排除するような生物学的反応系を導入させることが必要と考え,その開発に努めてきた.周知のごとく,古くから多くの研究者より,細菌学の分野より発展した免疫学を基礎に,腫瘍の自然排除を惹起させようとして努力し,実験腫瘍の面で多くの業績がなされてきた7-17).しかし単なる自動免疫および他動免疫の導入によつては,人の腫瘍に用いた場合は良い結果が得られなかつた18-20).それはLudwig等21-24)が示したように人の進行癌患者においては細胞性免疫反応が低下しており,それ故に感染症患者の免疫効果と異なり,免疫反応が生じ難くなつているものと推定される.われわれはこれらの担癌生体の反応系を配慮しつつ,臨床応用に入る以前にまず担癌動物を用いて種々の方法を考案し,腫瘤排除機能の賦与法について検討した.そのもつとも基本的な考え方としては次の2つの問題の解決がまず必要条件と考えられた.その1つの問題は担癌生体内に抗癌活性を生ぜしめるような有効な腫瘍抗原をいかにして求められるかであり,他の1つはすでに抗癌免疫体の生産系がブロックされている生体に,どのような方法により癌免疫因子産生系を賦活させ得るかの問題であつた.この2つの問題の解決方法として種々の基礎的検討を重ねたが,これまでのところ次のような事実が得られた.すなわち,組織培養した新鮮分離腫瘍細胞に対し,その分裂増殖速度に応じて3,000〜6,000RのX線照射を行なうとその培養液中にマクロファージおよびリンパ球を感作し得る因子が遊離してくることがわかつた1-3).もちろんこの液を用いて試験管内でマクロファージ,リンパ球または骨髄細胞等を培養すると,それぞれ感作され,試験管内において標識細胞の増殖を抑制する活性をもつようになる4).そこでこの感作細胞を担癌体の免疫監視系の刺激因子として用い,さらに腫瘍局所に放射線照射を行ない,腫瘍抗原の遊出を図り,両者の相互作用で担癌体に腫瘤排除作用が生じるかどうかが検討された.その結果,感作細胞の静注以前に1,000Rという比較的少量の放射線を局所に照射しておくと著明な抗腫瘍作用が発現し,腫瘤が著しく縮小消失した4).この作用機構を臨床的に応用し得るように配慮し次の実験を行なつた.すなわちin vitro感作細胞を用いる替りにin vivoつまり担癌生体内で感作細胞が生じるような系を試案し同時に腫瘍局所より抗原が遊出されるような照射法を導入してみた.その結果,あらかじめ適量の放射線を腫瘤局所に照射しておき,ついで同種動物の正常リンパ球の静注投与を行なうと著明な抗腫瘍効果が現われ,さきのin vitro感作リンパ球と照射との組合せ結果と同様の効果がえられた5).これらの結果から,この実験系に準じて行なえば人の癌治療にも応用しうると考えられた.臨床的には腫瘤の一部よりまず放射線またはある種の抗癌剤を抗原誘導の目的で使用し,適量に達した時点で免疫担当細胞として健康人末梢血より得たリンパ球を移入する方法を導入してみることにした6). 1971年6月以降種々の末期癌患者について症状に応じ多少の方法を変え前述の原則に準じた治療を行なつてきた.今回は紙面の都合もあり,その一部,胃癌の治療成績をとりあげ臨床結果について述べる.
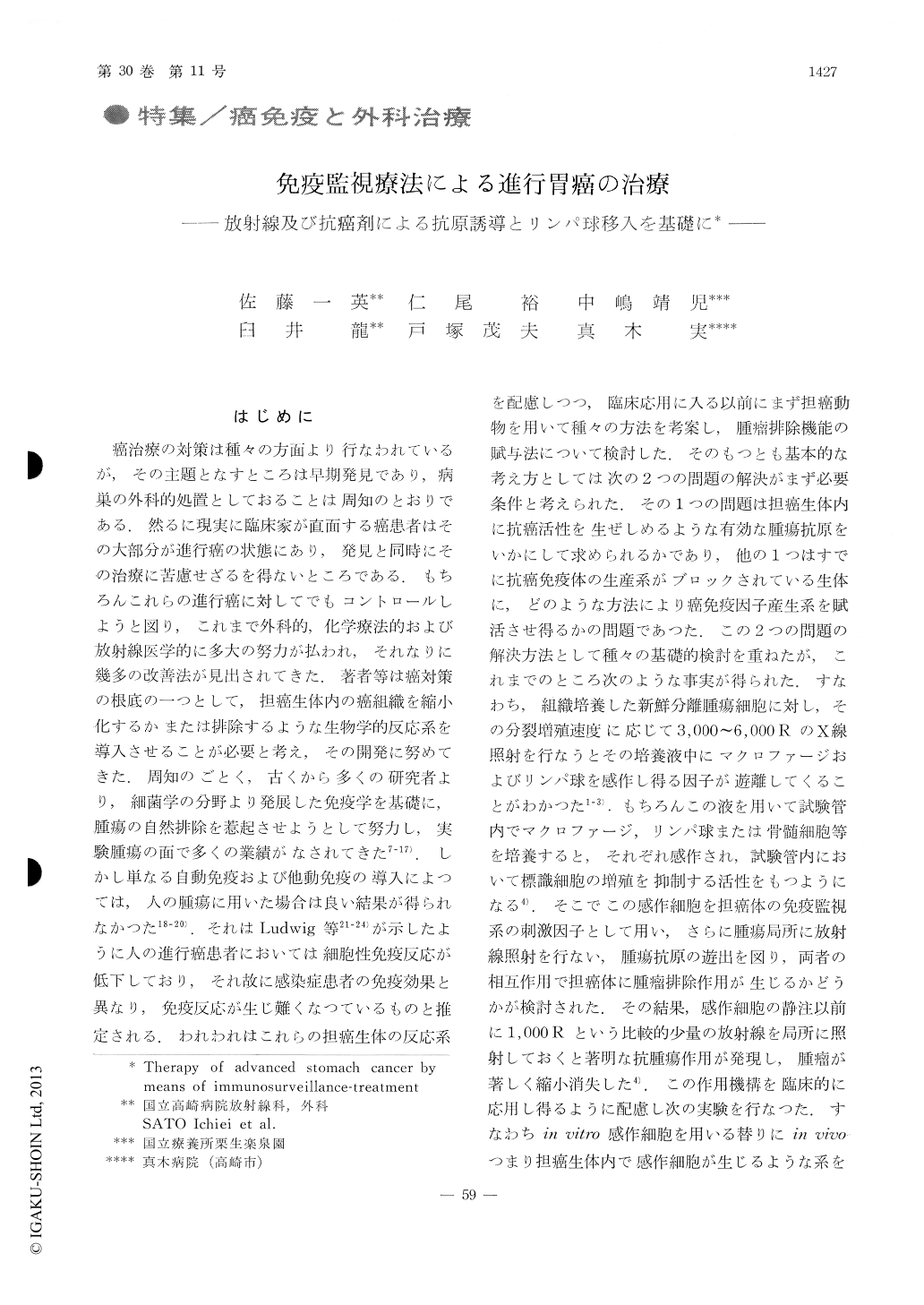
Copyright © 1975, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


