- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに—摂食障害とパーソナリティ障害の関係
DSM-Ⅲが日本の精神医学に入ってきて以来,私が専門とする摂食障害は,パーソナリティ障害と隣り合って論じられてきた印象がある。DSMの導入前,摂食障害は「神経性食思(食欲)不振症」であった。これは心療内科が得意とする領域であり,私も,学生時代に,心身医学の講義で神経性食思不振症については詳しく習った。しかし,過食症については詳しい講義があった記憶はなく,パーソナリティ障害については全く触れられなかったと思う。しかし,卒後数年たって摂食障害の臨床研究を実施するようになり,大学病院を受診する摂食障害患者にDSMの診断基準を当てはめてみると,過食症の診断も多く,また,パーソナリティ障害の診断もしばしば伴うので驚いた記憶がある。
当時は人格障害という訳語が用いられていたpersonality disordersの診断法を最初見た時には,違和感も感じた。「人格:personality」とは「人となり」のことであるのに,一人の人物に,境界性人格障害,自己愛性人格障害など複数の診断が下せるのか。また,人格障害の診断がついて,追跡面接時にそれが消える場合があるというのも「人となり」の診断としては不思議であった。しかし,摂食障害の病勢が激しい時に,境界性人格障害の診断基準を満たす状態だったにもかかわらず,病勢が落ち着いた5年後にそれが消えているというのは,大変興味深い現象に思われた。
当時,いわゆるAxis Ⅰの精神疾患とAxis Ⅱの人格障害についての関係はさまざまに論じられた。精神科医が操作的診断基準を手に入れ,患者に当てはめてみると,うつ病と境界性人格障害の両方が当てはまるケースなどは珍しくなかった。ここから,人格障害の併存がある場合,うつ病の回復が遅いのではないかなどが論じられた。一方で,うつ病の最中に人格障害の判定をしようとしても,本人に聞くパーソナリティの特徴は,うつ症状の影響を受けて偏っているかもしれないという批判もあった。もちろん,うつ病の病期には,無力感や罪悪感の影響を受けて人格のあり方が一時的に変わるのかもしれないという見方もあった。摂食障害についても,摂食障害,特に過食症の症状が激しい場合,対人関係が不安定になったり他の衝動性も伴うなど,境界性人格障害的になることはしばしばあった。このような場合,境界例らしさは,state(摂食障害が激しいという状況によるもの)か,trait(本来の性格傾向)かという議論が行われた。当時最新の方法論であった半構造化面接であるDiagnostic Interview for Borderlines(DIB)2,5)を使って,境界例らしさを点数にしてみると,ある大学病院初診の摂食障害患者の約半数はDIB高得点者であった。しかし,数年後に再面接すると,3分の2は低得点となっており,これらのほとんどで摂食障害症状は軽快していた。摂食障害になることで,一時的にパーソナリティが退行するのではという解釈4)も論じられた。
当時は,境界性人格障害が注目され,stateのほう,つまり摂食障害症状が強い時だけ境界例的になる事例については,本物でないような,真剣に治療を論じるに値しない事例のようにみられる傾向もあった。しかし,「悪くなる時はこのような悪くなり方をする」「悪くなる時はここまで悪くなる」という現象を知っておくことは臨床上有用であった。このような事例は,摂食障害の症状が強い時は,うつ病やパニック障害などのAxis Ⅰ疾患も伴うことがあり,人格の底が抜け,病理が花開いたような状態であった。病理が花開くのは,ほとんどの場合,対人関係の問題を引き金としていた。たとえば,交際相手と別れるなどである。このような状態は,次の交際相手を見つけると一時的に収まることもあったが,もちろんこれだけでは根本的な解決には至らず,治療者としてはさまざまな限界設定をしながら,底抜け状態が収まることを願って対応をしたものである。そのような中,退行して境界例的になっていたものが,病前の状態に戻る場合は戻り,戻らない場合は,これはtraitとしての境界例なのだという判断をしていたと思う。
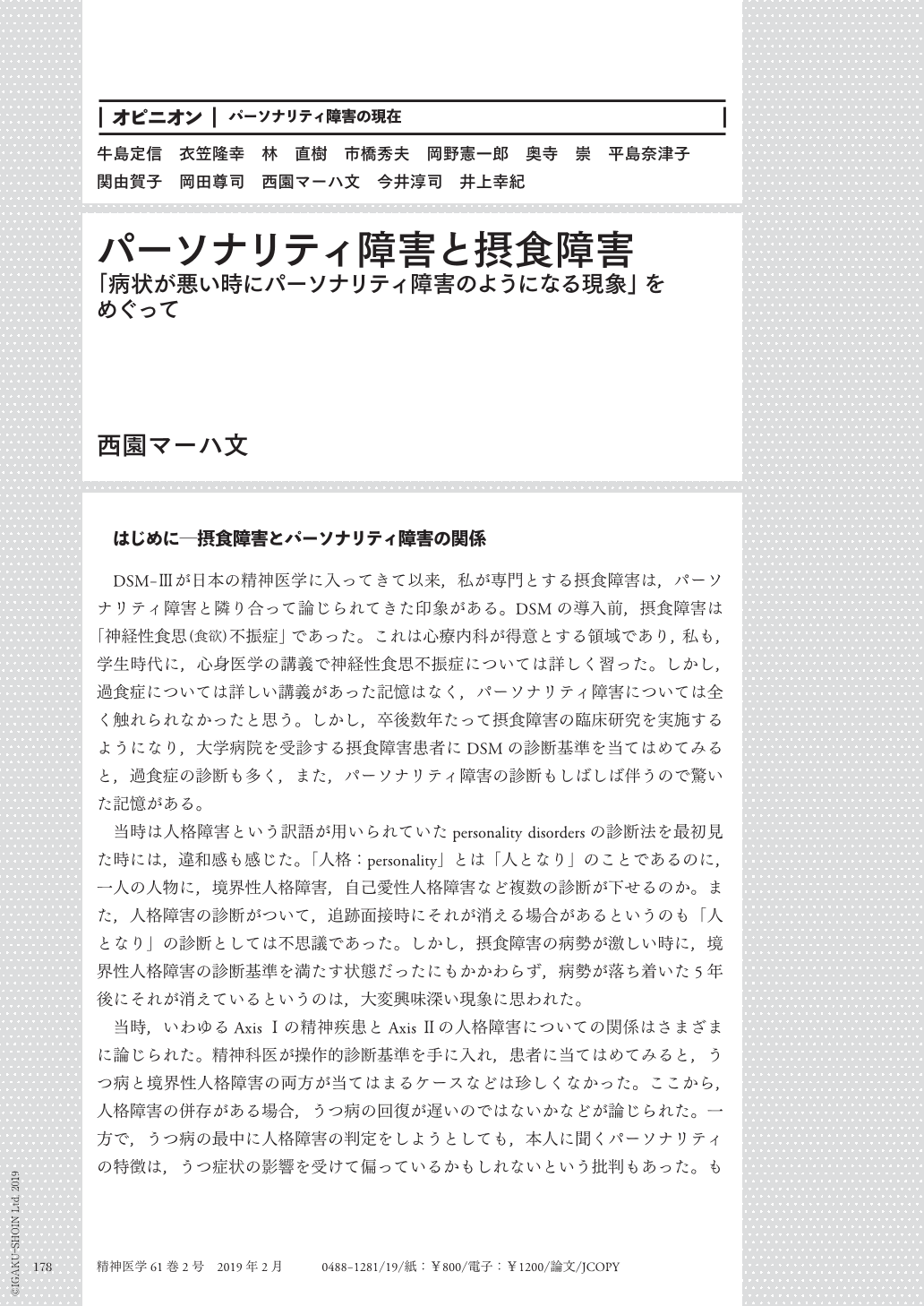
Copyright © 2019, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


