Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
- サイト内被引用 Cited by
はじめに
認知行動療法について筆者の一人である大野がはじめて知ったのは,米国留学中の1986年のことだった。精神分析療法や精神力動的精神療法を勉強しに留学したコーネル大学医学部附属病院本院の外来部長だったAllen Francesが,せっかく米国にまで来たのだから多くの治療法を身につけるのが良いと勧めてくれたのがきっかけだった。
その頃,米国の精神医学は生物学的精神医学一色で,ジョンスホプキンス大学のレジデント・トレーニング・プログラムから精神療法が削除されたことが話題になっていた。精神医療の医学化が強く押し進められ,脳科学が進めば精神疾患が解明され,根本治療が可能になると信じられていた時代だった。精神療法などしなくても,薬物療法などの生物学的治療で精神疾患が治療できるようになると考えられていた。
しかし,それから30年あまり,そうした生物学的楽観論は次第に勢いを失ってきたようにみえる。薬物療法の開発も,ブレークスルーと呼べるような成果はみられていない。バイオマーカーを診断の基本に据えようと意図して始まった米国精神医学会の『DSM-5精神疾患の診断統計マニュアル』作成委員会のパラダイムシフト構想は,信頼に足るバイオマーカーが一つもないことを世に示しただけで,従来の症状に基づくカテゴリー診断に戻らざるを得なくなった。
こうしたDSMの改訂に否定的な米国精神保健研究所(NIMH)によって始まったResearch Domain Criteria(RDoC)研究は,ディメンジョンを用いて精神疾患の生物学的背景を解明しようとしたものだが,はたして成果が出るかどうかが,それが分かるまでに10年単位の時間が必要だろう。
こうした動きは,精神医療の医学化の行きづまり10)のように思えるが,そうしたこともあってか,再び精神療法が注目されるようになってきた。中でも,認知行動療法は,効果に関する実証的研究が積み重ねられたこともあって,広く関心を持たれるようになり,米国精神医学会も研修用の書籍12)を出版するようになっている。そこで,本稿では,我々の認知行動療法の効果研究を基に,認知行動療法のわが国の精神医療への貢献と今後の展望について論じることにしたい。
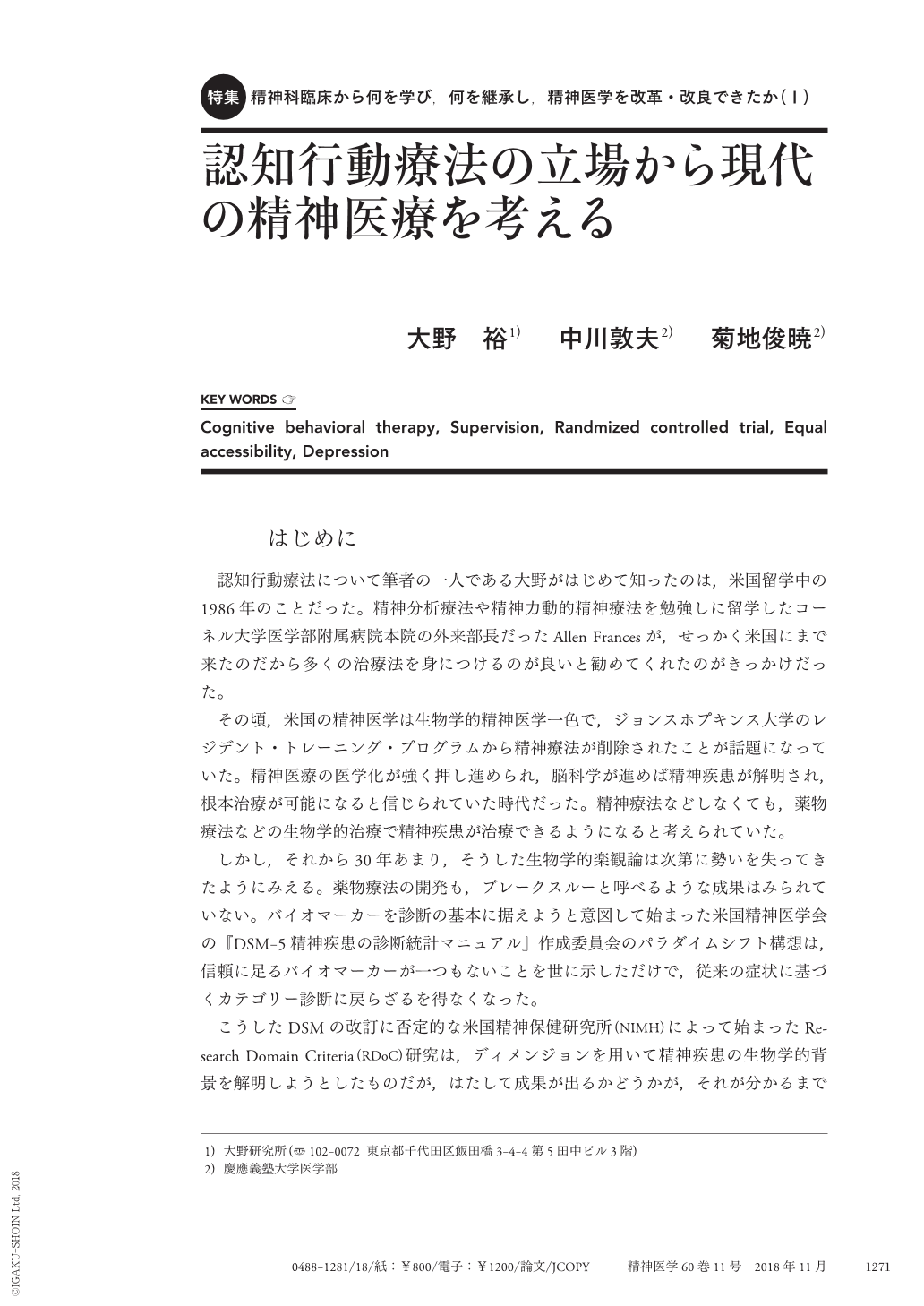
Copyright © 2018, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


