Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
1890年代に早発性痴呆という概念を提示したクレペリンは,統合失調症の進行性脳病態を想定していた。以来,死後脳を用いた直接観察により,側頭葉内側部の体積減少や,神経細胞の数や形状の異常が認められていた。しかし,神経病理学的に脳の変性疾患を特徴付けるグリオーシス,すなわち脳組織がダメージを受けてグリア細胞が増生している所見が統合失調症の脳にはみられないことから,“schizophrenia is the graveyard of the neuropathologist.(統合失調症は神経病理学者にとっての墓場である)”と言われ,1952年の第1回国際神経病学会では,“there is no neuropathology of schizophrenia.(統合失調症に神経病理所見はない)”という結論が出され,しばらくの間,死後脳を用いた統合失調症研究が注目されない時期が続いた。一方で脳組織にみられる異常は,脳が完成する前の胎児期に生じたものであると考えられ,ウイルス感染などの周産期の合併症により統合失調症の発症危険率が上昇するという疫学研究に裏打ちされるように,まず胎児期の神経発達の障害が素因となり,思春期に外的要因により神経伝達物質のアンバランスを生じて統合失調症を発症するという神経発達障害仮説が生まれた。
1980年代の脳画像技術の進歩に伴い,統合失調症における脳の形態学的変化に関する研究が進み,特に側脳室の拡大や側頭葉内側部の体積減少が繰り返し報告されるようになった。また機能画像研究により,幻聴と関連すると考えられている上側頭回の機能異常が報告され,これらの部位の脳組織で実際に何が起きているか再び興味が持たれるようになってきた。現在までに脳組織を研究する手法は進歩し,顕微鏡下での観察だけではなく,免疫組織学を利用し,コンピュータを用いた画像処理・統計を駆使した研究の所見が蓄積されてきている。一方で分子生物学的な研究手法が飛躍的に発展し,脳組織における遺伝子発現を調べられるようになった。
このように,統合失調症という病態の根幹を神経学的基盤に求める場合,それを直接観察する手法である死後脳研究は極めて重要な地位を占めると同時に,統合失調症に関するさまざまな生物学的研究の集約点であると言える。しかし,統合失調症にかかわる研究者のみならず,多くの臨床医にとって,患者の臨床症状がどのような神経学的基盤に基づいているのか,そしてできればどのように治療につながるのか,興味のあるところであろう。
本稿では,まず死後脳研究の手法を概観し,次に現在までに死後脳研究が明らかにしてきた所見が統合失調症の病態仮説をどのように支持しているか,臨床症状や臨床検査所見との関連において論じる。
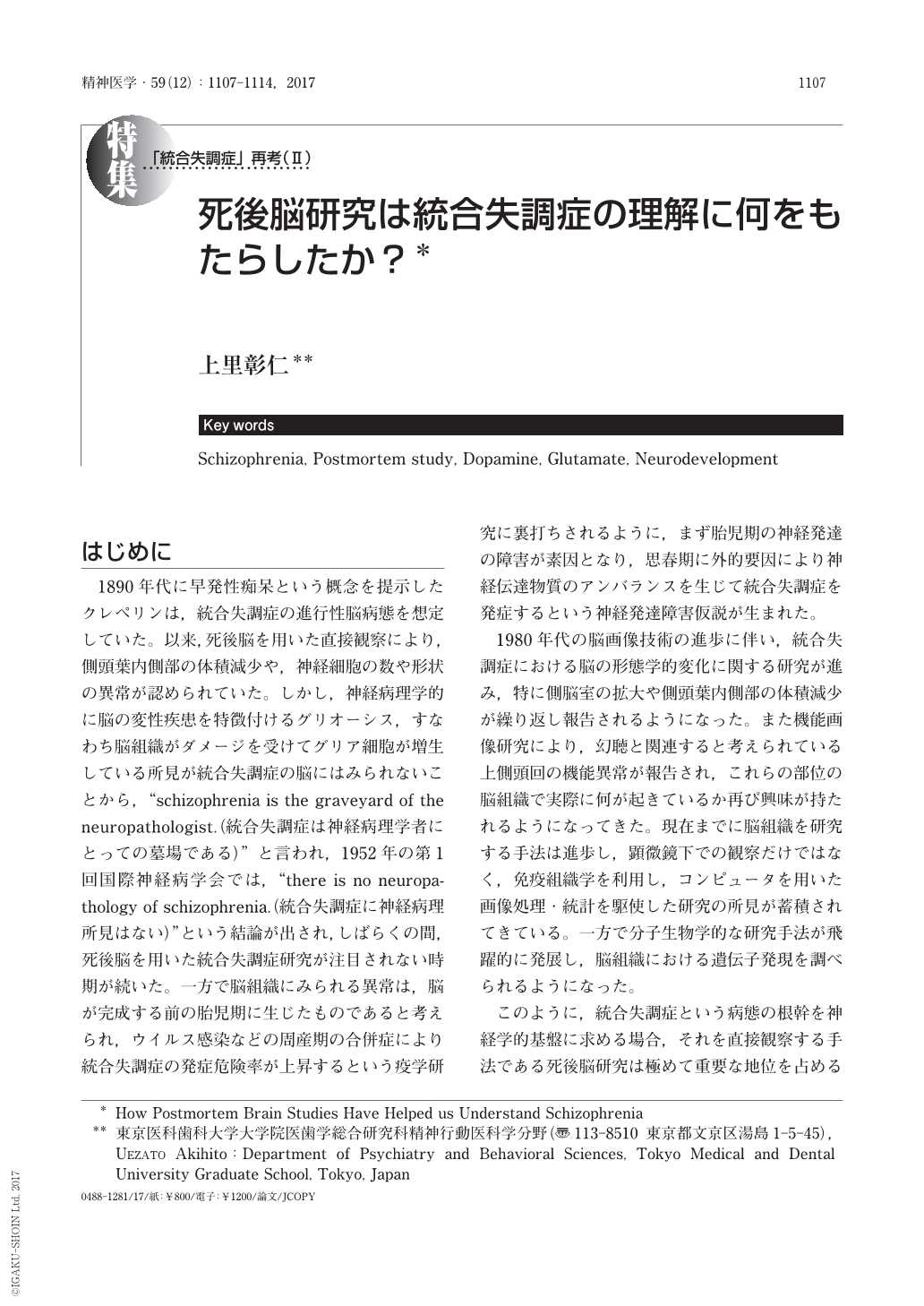
Copyright © 2017, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


