Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.はじめに
分裂病の薬物療法は数多くの抗精神病薬の開発と臨床応用により道が拓かれたことは周知のとおりであるが,その後は多くの期待に反し,この疾患を制圧するまでに至らず,難治例,慢性移行例がなお多数存在している現状である。
近年分裂病の生物学的側面に関する研究が行われた結果,いくつかの,疾患の発症機序を示唆する現象が認められ,また仮説が生まれたが,治療薬である抗精神病薬の開発の経過は当初はこれらの事象に準拠して進められてきたものではなくて,試行錯誤と経験的実証を繰り返しながら治療薬としての応用が認められてきたものである。
インドの治療薬rauwolna serpentinaからreserpineが,抗ヒスタミン薬のpromethazineからchlorpromazineが,臨床経験,化学構造から着想された抗精神病薬療法の夜明けより,動物の行動薬理プロフィール,たとえばラット抗アポモルフィン作用,抗アンフエタミン作用,カタレプシー作用その他から既存の抗精神病薬と比較して臨床効果を類推する方法が採られて多くのphenothiazines,butyrophenonesその他の化合物が治療薬として開発された。
抗精神病薬がドーパミン受容体を遮断することが一方では抗精神病作用を生じ,また他方では錐体外路症状を起こすという考え方がなされるに至り,これがまた分裂病のドーパミン活動過剰仮説の傍証になるかというように考えられ始めて久しいが,最近また分裂病の成因に関する神経伝達異常仮説としてドーパミン以外の物質の介入が論じられており,抗精神病薬の作用機序も単一なものでないとして,後述のごとく各抗精神病薬をそれぞれ抗ドーパミン,抗ノルアドレナリン,抗セロトニン作用その他の強さの相違から区別して,分裂病の症状群をドーパミン性(幻覚,妄想,思路障害,常同症),ノルアドレナリン性(不安,焦燥,妄想気分,運動興奮)およびセロトニン性(自閉,接触性障害,感情,意欲鈍麻)に分けてそれぞれに適応する薬物の選択をするという考え方もなされている23,24)。しかし分裂病の薬物療法の現状を知るにはまず,現在の使用状況の実態にふれてみる必要があろう。
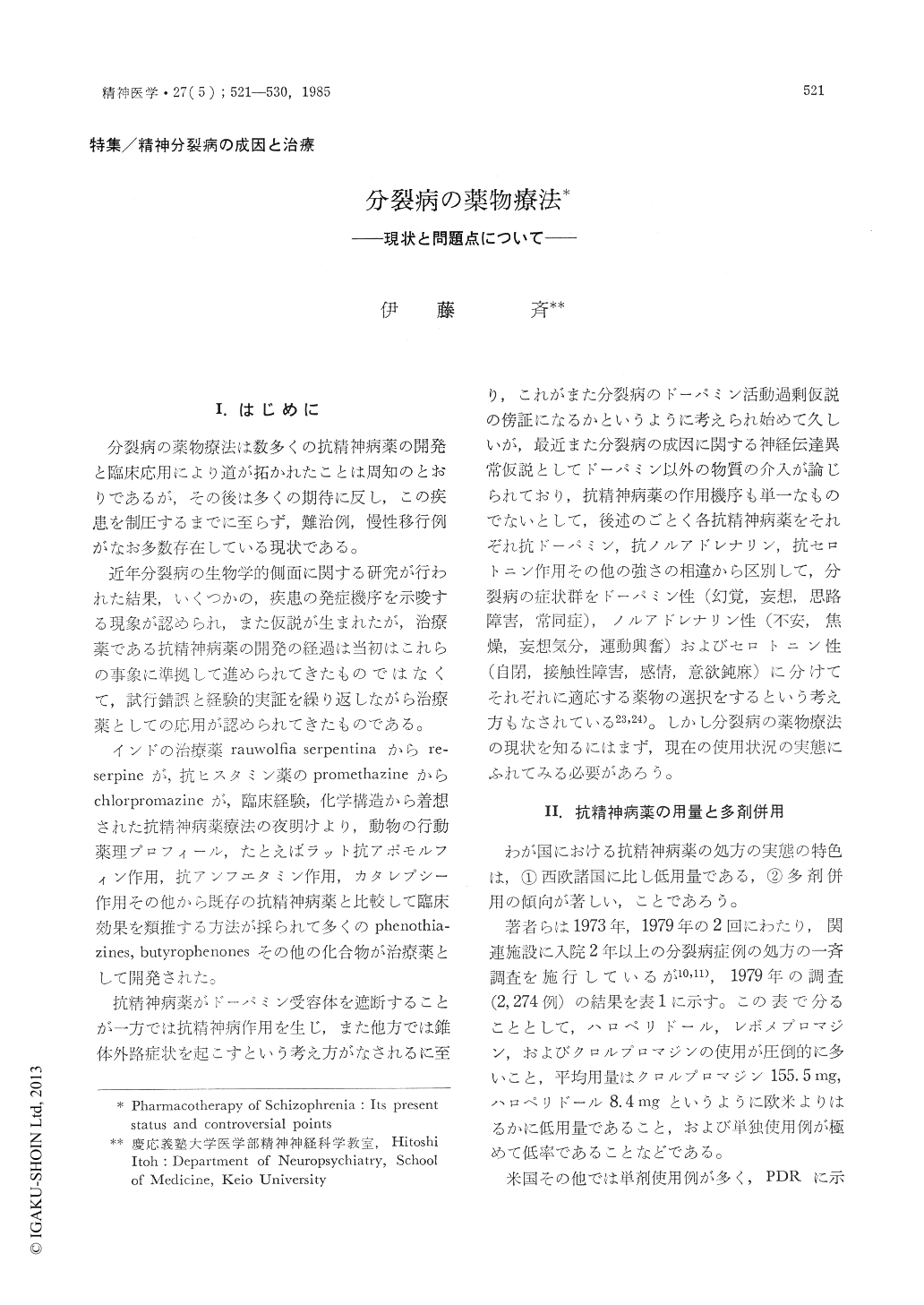
Copyright © 1985, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


