Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
Ⅰ.
Reilは1800年にすでに異常心情状態(abnormer seelischer Zustand)と疾患過程を区別したし,1820年にはJ. F. Friesがethisch Verwilderte und Verkümmerteについて記載しているが,精神病質人格についての本格的な研究はJ. L. A. Kochから始まるといつてよいであろう。Kochはdie psychopathischen Minderwertigkeitenの名のもとに「先天的のものであろうと後天的なものであろうとその個人生活において人間を左右するような精神的異常性であり,そのもつとも悪いものでも精神疾患でないが,しかしその人間はもつともよい場合でも完全な精神の正常さと行為能力をもつていないもの」を総括した。したがつてその中には精神薄弱も,脳の器質的損傷や炎症後の欠陥状態も含まれていた。こうした広範かつ不定な概念規定ではこの概念が精神医学の集壼(Binder)とか紙屑籠(Bohm)とかいわれるのも当然であろう。かくして精神病質という名称はドイツ精神医学から発生したものであるが,ドイツ精神医学はそれをフランスのdégénérescenceという概念から導入したものである。もともと変質とはMorelが系統的に記述したことから始まつた遺伝的概念であり,家系がいくつかの世代を経るうちにとくに精神的領域での疾患素質が増加し,それがしだいに重症となり,ついにはその家系が滅亡してしまう現象を指している。この変質学説がその後Magnanによつて受け継がれたことは周知のことであるが,Magnanは急激に多型,かつ不規則に経過する"Délire des dégénérés"あるいは"Bouffée délirante"をDégénérescence mentale(Déséquilibra tion psychique)の定型的なあらわれであるとしているが,こうした精神病との関連においてとらえられたDégénerescenceもしくはDéséquilibreという概念はその後もフランスにおいては生き続け,H. EyはDéséquilibreを精神病の候補者と定義づけている。ドイツでは変質とは遺伝概念であるから用いないほうがいいといい(Bleuler),また精神病質と変質の関係は不明であるとされ(Gruhle),あまり用いられていない。
さてドイツの精神病質概念においても古くはZiehen,Kraepelin,Birnbaumのごとく精神病質を精神病と正常者の中間状態とみなす考えかたも存在したが,最近ではKretschmerが分裂病質,循環病質をそれぞれ精神分裂病と躁うつ病との関連においてとらえている以外はほとんど精神病とは無関係にもつぽら性格の生来姓の偏倚として考えられている。そしてこんにちまで多くの研究があるとはいえその概念規定や類型の命名法はKochによつて用いられた「低格」という概念やKraepelinそのほかによつて用いられてきた社会学的名称(Haltlose,Antisoziale,Gesellschaftsfeinde等)から漸次社会的,道徳的価値判断を洗いおとし,心理学的,性格学的なものに純化しようとする方向に向けられてきた。
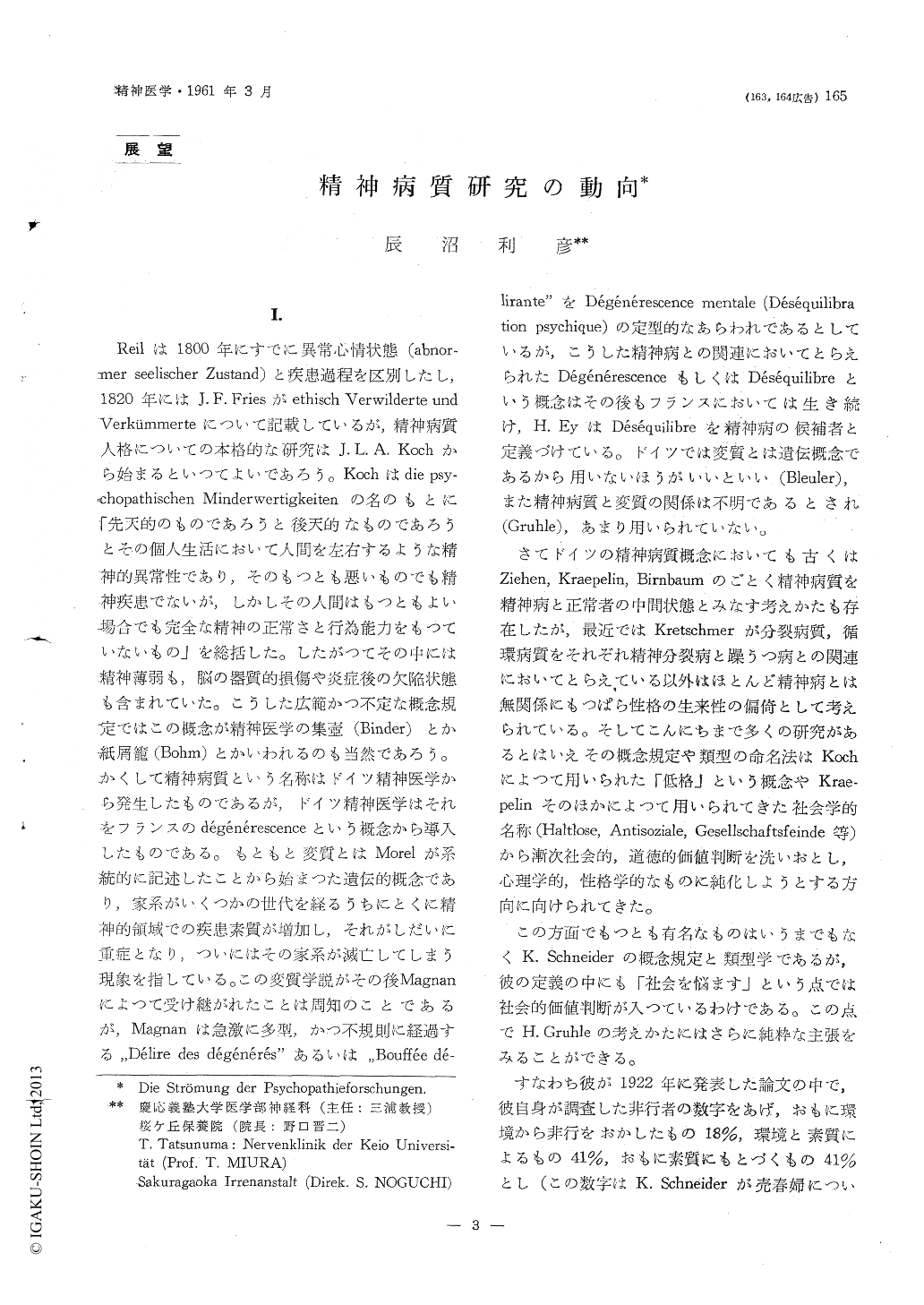
Copyright © 1961, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


