- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
20歳前後から60歳前後を対象とする成人期の保健事業を行う時、この年齢層へ適切なアプローチができず、困難感を抱えている担当者も多いのではないだろうか。成人期の多くは働く世代であり、平日の日中は仕事をしている人が多く、健康支援をしたくとも、その周知すら難しい。
一方で、わが国の企業数の99.7%は中小企業が占め、産業医や産業看護職等の専門職が雇用されている企業は一部に限られていることから、充実した健康支援を受けられないまま40年以上という長い期間を過ごす人が多いと推測できる。
働く世代の健康支援に着眼して保健活動を展開し、働く世代の健康度を上げることは、地域の健康課題を解決する上で、とても重要な要素である。そして、地域・職域連携は、その取り組みにおける効果的な手段の一つであると考える。しかし、国が進める地域・職域連携は、都道府県や二次医療圏という広い範囲で協議会を開催するものであり、現時点では、市町村単位で職域との連携を推進するものではない。また、2005(平成17)年に、最初の地域・職域連携推進ガイドライン1)が示されてから15年以上が経過しても、実践的な連携を行うことが難しく、多くの課題を抱える地域が多い2)。
このような状況の中、秦野市・伊勢原市(以下、当地域)では、市保健師が直接、市内に所在する事業所の事業主や安全衛生担当者等と連携しながら、働く世代の健康づくりに関与すべく実践を重ねている。この連携活動は、日々、直接的な保健サービスを住民に提供し、住民の身近な存在として活動する市保健師だからこそ、担当する地域住民の未来を思い描き、取り組むことができると考えている。
本稿では、県保健所と2市の保健師、そして大学教員が運営主体となって開催している地域・職域連携活動を報告する。また、市保健師がどのような思いの変化を遂げながらこの連携活動に携わってきたかという点にも焦点を当てる。当地域における職域との連携活動や、市保健師の思いの変化を紹介することで、他地域の市町村保健師が職域との連携を始める場合や、停滞している地域・職域連携活動の方針転換を図りたい場合などに役立つことがあれば幸いである。なお、本稿でのデータ公表の可否については、「地域・職域ネットワーク〜秦野・伊勢原で働く人の健康と安全を考える会」(以下、本会)の登録者の承諾を得ている。
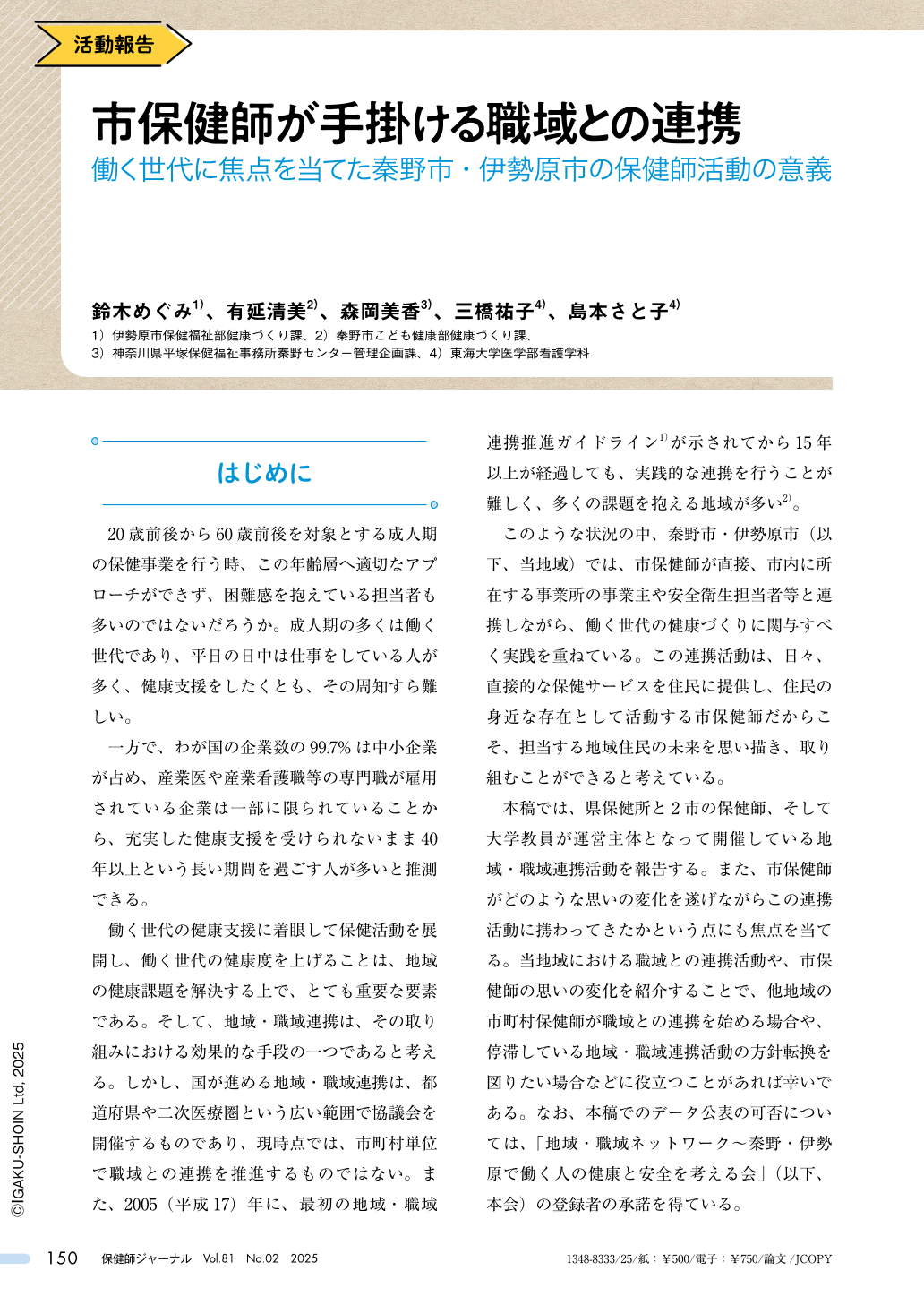
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


