- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
近年,超高齢社会の進行による外出難民や買い物難民の増加が社会問題となっている中,どのように地域の移動を支援するかが大きな課題となっている.移動については,日本国憲法の第22条において,“何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する”と,いわゆる「移動の自由」が定められている.そのような中で,交通手段としては通勤・通学に自家用車が46.9%1)と,自動車の利用が大きな割合を占めている現状がある.
自動車運転にかかわる障害者や高齢者への支援については,医療機関を中心に全国で取り組みがなされているが,診断の結果や加齢により免許を返納せざるを得ない対象者も少なくない.2024年(令和6年)の運転免許の自主返納件数は約42.7万人2)となっている.そういった背景から,医療・福祉専門職が地域包括ケアの一環として移動支援・外出支援にかかわる重要性が高まっている.
地域の移動手段は電車,バス,タクシーの他にもレンタカーやカーシェアリング,電動車いす等,多様にあるが,デマンド型交通〔DRT(demand responsive transport:需要応答型交通システム)〕を導入する自治体が増えている3).
このような中で昨今注目されているのが,「支え合い型交通」というモビリティの形態である.地域住民同士で移動を支え合う互助の力を引き出せるよう,自治体や業種を超えたさまざまなステークホルダーの方々と協業することで,まちぐるみで自分たちの移動を考える風土が醸成されていくと期待されている.
筆者がかかわる東京都町田市では,高ヶ坂・成瀬地区を走る地域巡回バス「くらちゃん号」をはじめとした,住民主体の支え合い型交通が点在し注目されているが,今回は町田市で行われている取り組みを3つ紹介する.
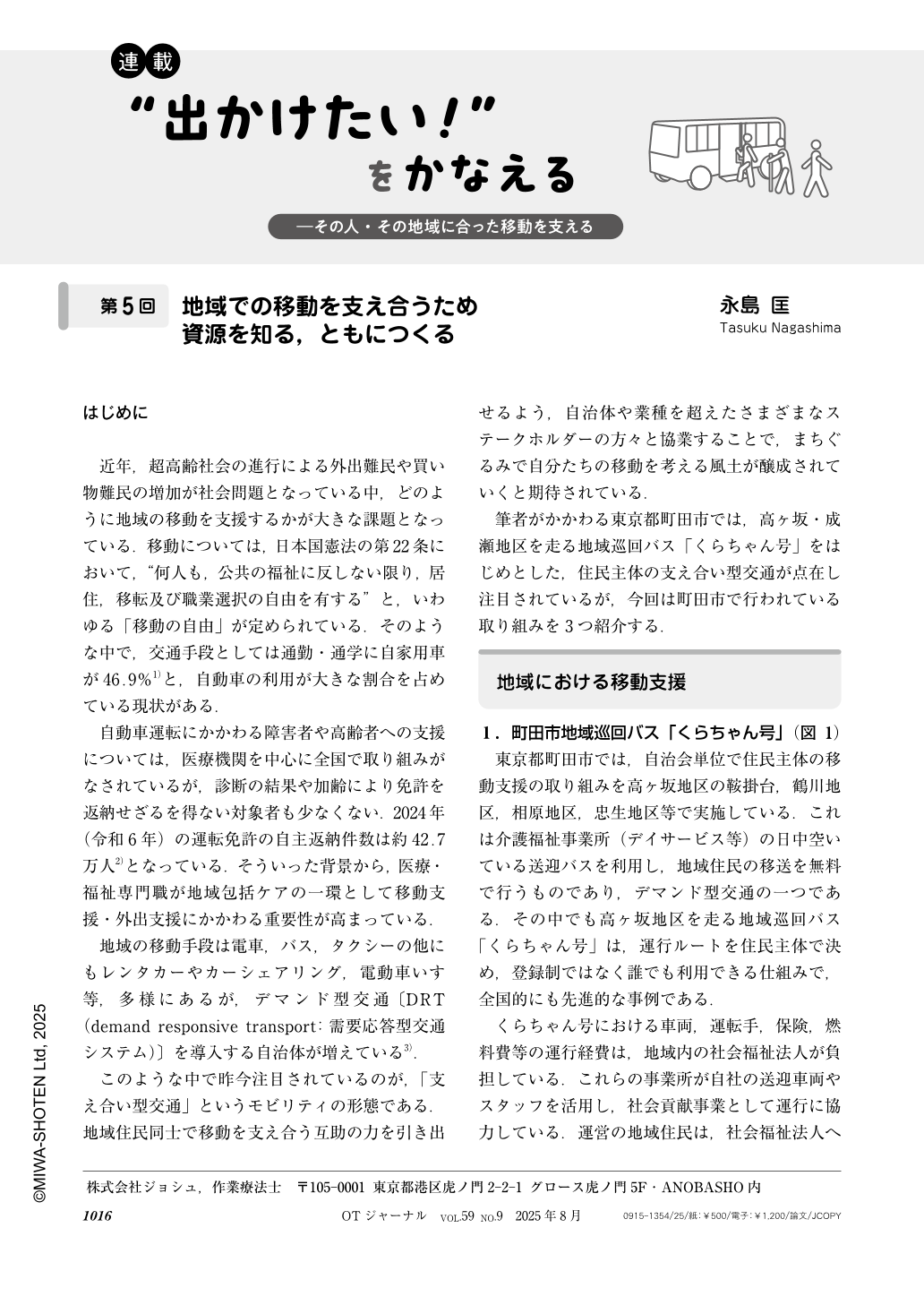
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


