Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
Key Questions
Q1:重症心身障害児および医療的ケア児に対する緩和ケアとは?
Q2:小児緩和ケアにおけるリハビリテーションの役割とは?
Q3:重症児に対する緩和ケアは医療の枠組みに収まるのか?
はじめに
小児医療に携わるものにとって,「緩和ケア(palliative care)」がどれだけ浸透しているだろうか.WHOは1989年に国際的な緩和ケアに関する定義を公表し1),その後,改訂もしている.また1997年に英国小児緩和ケア協会と英国小児科学会が,世界で初めて小児緩和ケアの定義を公表した2).その内容は,「生命を脅かす疾患のある子どものための緩和ケアとは,身体的,精神的,社会的,スピリチュアルな要素を含む積極的かつ全人的な取り組みである.それは子どものQuality of Life(QOL)の向上と家族のサポートに焦点を当て,苦痛を与える症状の管理,レスパイトケア,終末期のケア,死別後のケアの提供を含むものである」3)とされている.
わが国においては少子高齢化が深刻な社会問題とされ,2024年(令和6年)の出生数は過去最少の68万人台4)となり9年連続で最少を更新した.一方で高齢出産や不妊治療の進歩と保険適用,さらに周産期医療を含めた小児医療の発展を背景に,医療的ケア児の数は年々増加している.2023年(令和5年)の統計によれば,その数は2万人を超え,15年で約2倍に増加した(図 1)5).医療的ケア児とは,「日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む)」と定義され6),医療的ケアとは,人工呼吸器管理,喀痰吸引,経管栄養等を指す.医療的ケア児には歩行可能な児や肢体不自由児,知的障害のない児など,さまざまだが,そのうち約6割が重症児と報告されている7).重症児の約8割の介護者が在宅生活の継続を希望している8)ものの,2020年(令和2年)に報告された「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査」9)では,主介護者および家族に関するさまざまな課題と困難が明らかになっている.
また,重症心身障害児(者)とは「重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態」とされ,「児童福祉法」上に設けられた定義である10).細かな判断基準は明確に示されていないが,運動機能と知的機能の評価に基づいて評価される「大島の分類」11)を用いて判定されることが一般的である.重症心身障害児の数は,2014年(平成26年)の推計12)で5万1,143人(対人口比0.04%)と報告されている.
こうした背景のもと,日本は独自に重症心身障害児および医療的ケア児に対する医療的・社会的制度を構築してきたとされる.「緩和ケア」がどれだけ浸透しているかは明確ではないが,われわれがこれまで重症心身障害児に対して行ってきた医療や支援は,苦痛の軽減やQOLの向上を目的としており,これはまさに「palliative care(緩和ケア)」であるといえる.
緩和ケアの主体が当事者であるのは小児緩和ケアでも同様である.しかし,保護者の介護負担や意思決定における特殊性,子どもは発達する存在であること等,小児緩和ケア特有の課題が多く存在している3).以下に,医療的ケア児と重症心身障害児(以下,便宜上「重症児」と総称する)を含む小児緩和ケアにおけるリハビリテーションのあり方について検討する.
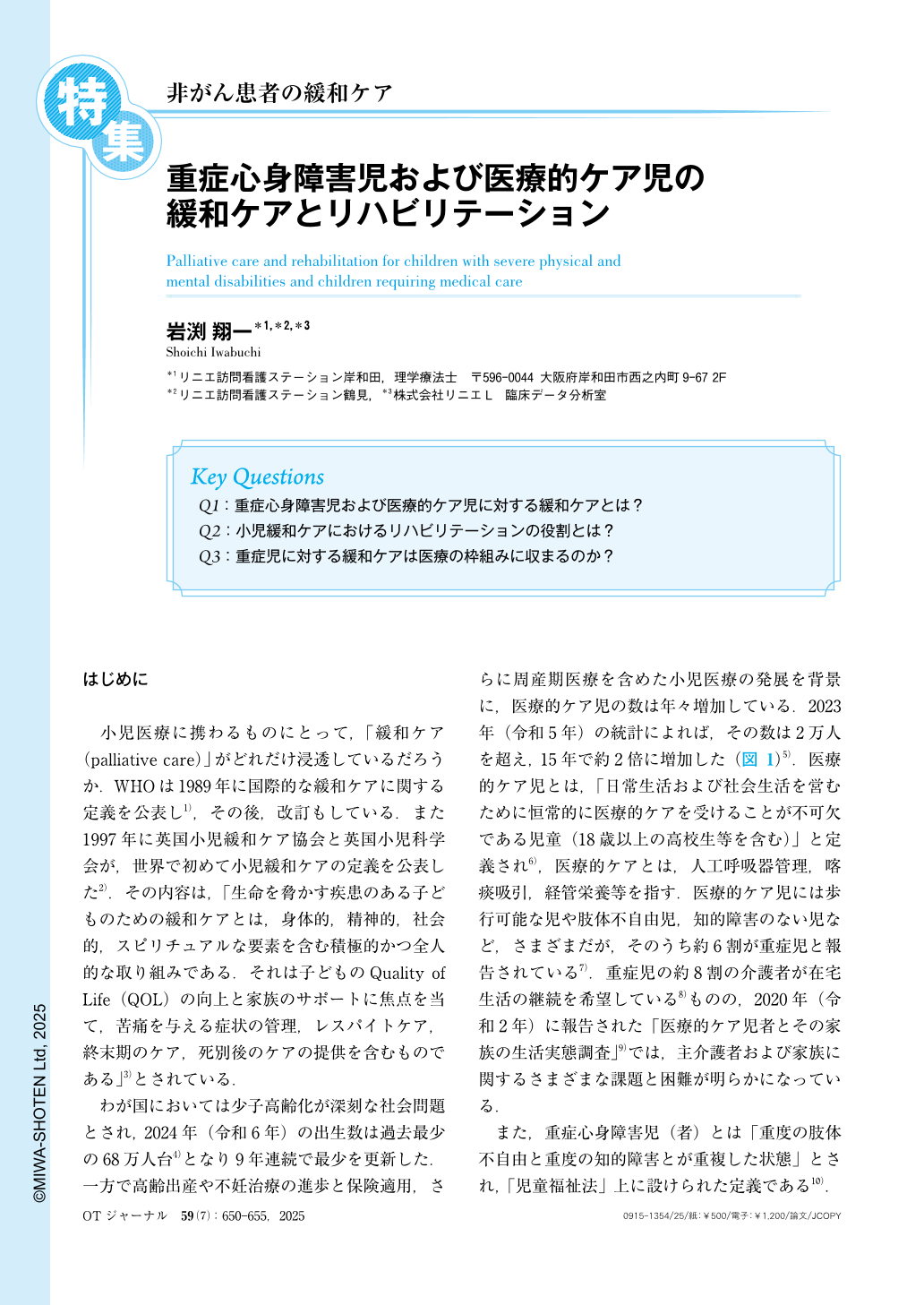
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


