- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
タンパク質は,生体にとって必須の分子であり,多様かつ精緻な生体機能を担っている。生体内の天然タンパク質が担っている機能の例として,太陽エネルギーを化学エネルギーに変換すること(ルビスコなど),小さな分子や光を超高感度に検出すること(嗅覚受容体やロドプシン),pH勾配を化学エネルギーへと変換すること(ATP合成酵素),化学エネルギーを仕事へ高効率で変換すること(アクチンおよびミオシン)などが挙げられる。また,RNAなどの核酸も,タンパク質へ翻訳される情報担体としてだけでなく,タンパク質の合成やスプライシングなどに酵素的に働くことが示されている。過去数百年の技術の進歩にもかかわらず,人間がつくった機械は,ナノスケールの生体分子の精密さや効率の良さに太刀打ちできていない。ナノマシンとして多彩で高性能な機能を発揮できる生体分子を自在に設計できるようになれば,医学・工学分野における様々な技術的課題を解決する可能性を秘めている。
特にタンパク質に注目すると,驚くべきことに,30-40億年にわたる進化の過程で生命は,タンパク質の可能性を余すことなく使いこなしているとは言い難い。200アミノ酸から成る典型的な長さを持つタンパク質について,あり得る配列数は20200(それぞれの位置について,20種類のアミノ酸があり得るため)であるが,現存する生物が利用しているタンパク質の数はわずか1012-16個程度である。また,自然界に存在するタンパク質は進化により形成されるため,全配列空間に一様に広がっているわけではなく,それぞれのファミリーがある程度かたまって分布している。つまり,アミノ酸配列空間のごくわずかな領域を進化は探索したにすぎず,これまでの進化の過程で試されていない可能性の高い,残りの広大なアミノ酸配列空間が,新奇人工タンパク質設計の舞台となる。したがって,進化の過程はその探索の助けにはなるが,絶対的な指標とは言えない。そのため,進化の過程から得られる情報に加えて,タンパク質構造,性質,機能に関する生物物理学における原理を理解することによって,“新奇タンパク質”を人工的に設計することができるはずである。
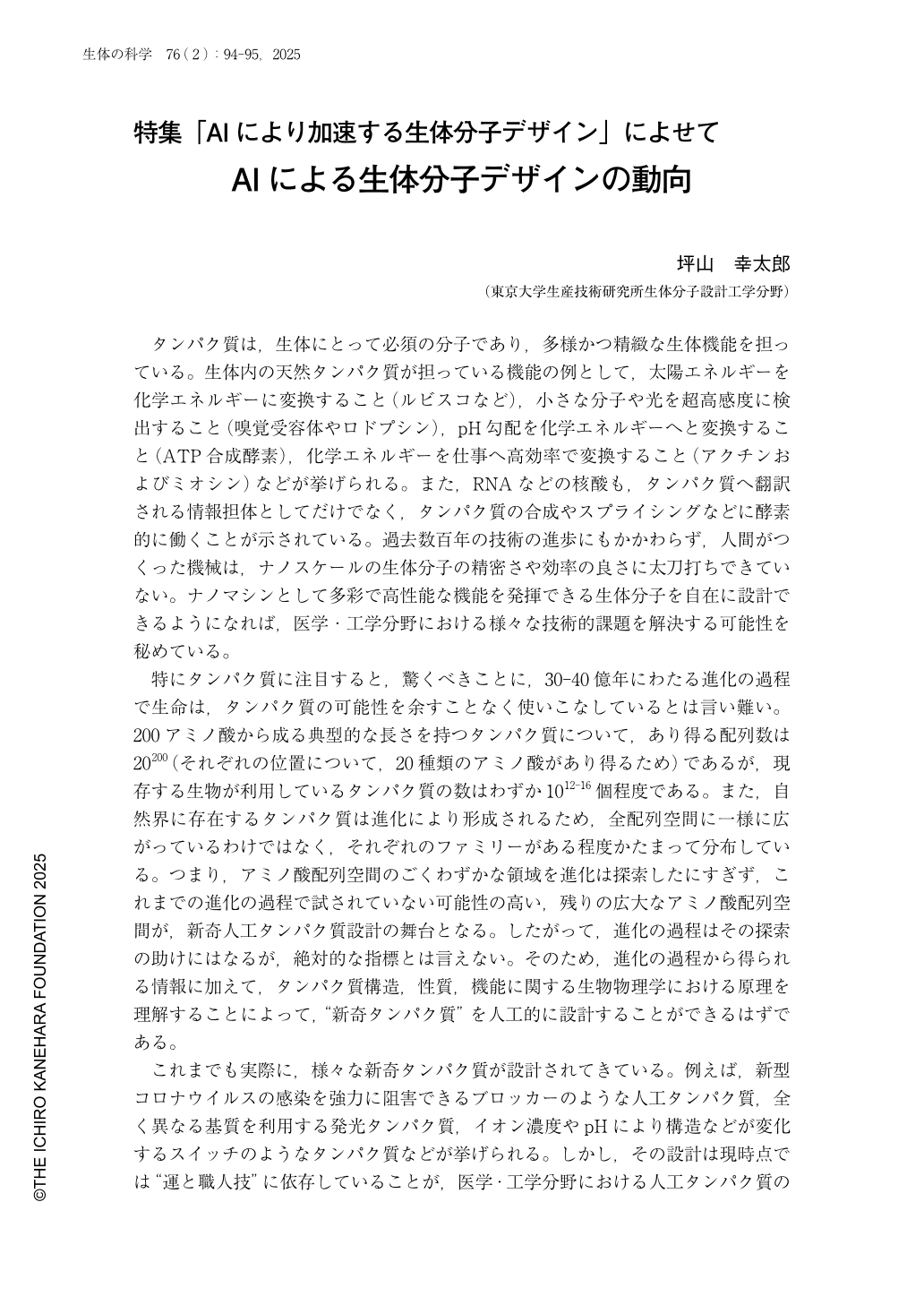
Copyright © 2025, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.


