特集 こども家庭センターの意義と現状
—座談会—多角的に開かれた連携の場へ—こども家庭センターの現在地とこれから
山縣 然太朗
1,2
,
木庭 愛
3
,
髙山 恵子
4
1国立成育医療研究センター成育こどもシンクタンク
2山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター
3こども家庭庁成育局母子保健課
4船橋市健康部地域保健課
pp.722-729
発行日 2025年8月15日
Published Date 2025/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.036851870890080722
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
2022(令和4)年6月8日に改正児童福祉法が成立した。近年増加を続ける児童虐待事例や子育て世代の孤立など、子どもや保護者、家庭を取り巻く厳しい現状に対する、児童福祉と母子保健の両面からの具体的な対応は喫緊の課題でもあった。
担当省庁として2023(令和5)年4月に新たに発足したこども家庭庁は、市区町村各自治体における対応組織として「こども家庭センター」設置を努力義務として求め、包括的な支援を行うよう整備を進めている。しかし、その活動を支える基盤法は児童福祉を主とする児童福祉法のため、母子保健活動との両立やその影響が、一方では懸念されている。各地で整備が進む「こども家庭センター」が抱える課題とは。そして、これからの母子保健と児童福祉の効果的な在り方はどのようなものだろうか。本特集の企画者・山縣氏を中心に、こども家庭庁からは木庭氏、そして、山縣氏が2018(平成30)年から母子保健連絡協議会会長を務め、母子保健計画の単独での策定や、本(2025)年度は成育医療等に関する計画の策定にも尽力するなど関わりの深い船橋市から髙山氏を迎え、お話を伺った。
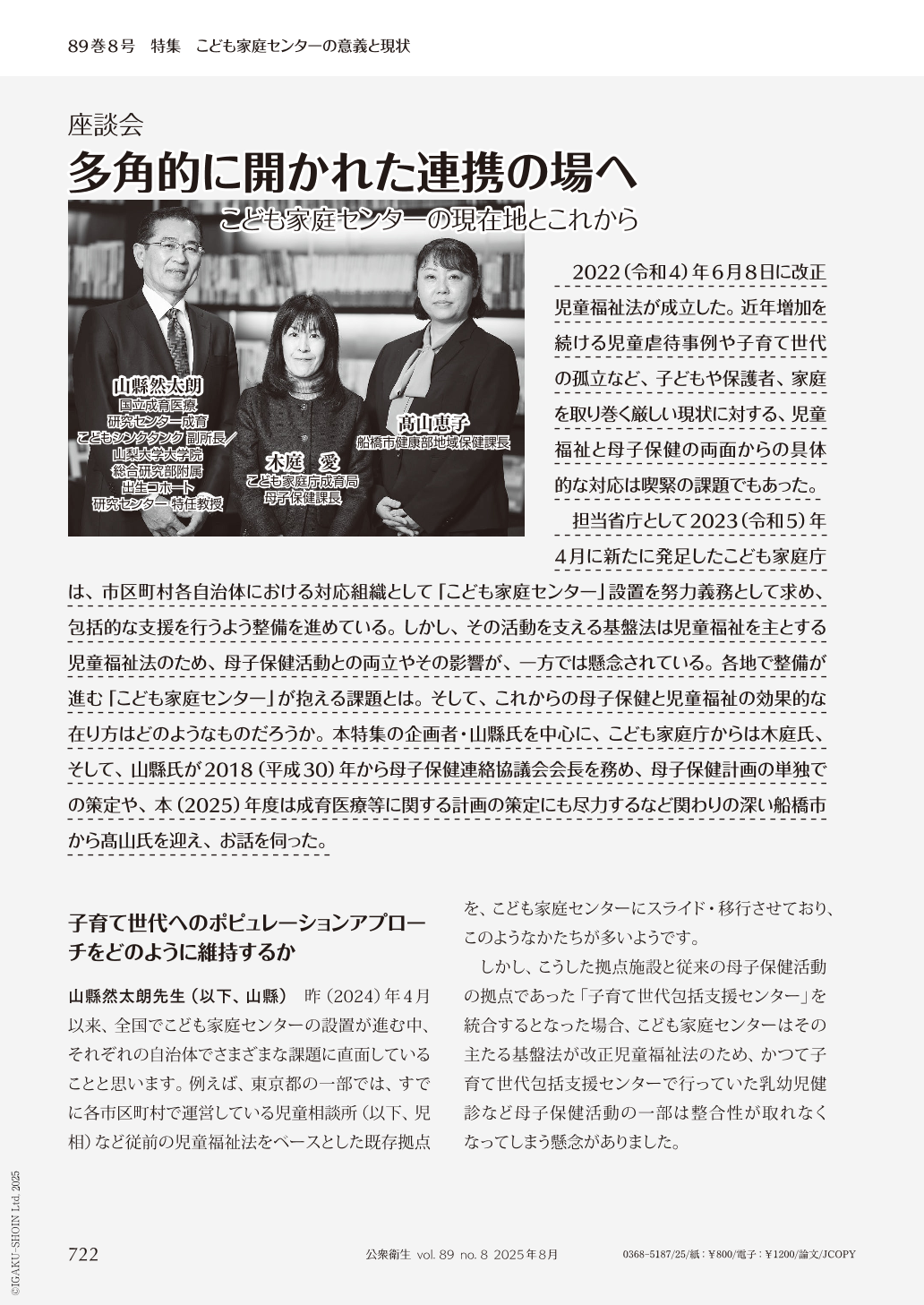
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


