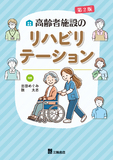書籍を検索します。雑誌文献を検索する際には「雑誌文献検索」を選択してください。
-
基礎医学系
-
臨床医学・内科系
-
臨床医学・外科系
-
臨床医学(領域別)
-
臨床医学(テーマ別)
-
社会医学系・医学一般など
-
基礎看護
-
臨床看護(診療科・技術)
-
臨床看護(専門別)
-
保健・助産
-
看護教員・学生
-
各種医療職
-
東洋医学
-
栄養学
-
薬学
-
歯科学
-
保健・体育
-
雑誌
高齢者施設のリハビリテーション 第2版
三輪書店
電子版ISBN
電子版発売日 2025年3月24日
ページ数 196
判型 B5
印刷版ISBN 978-4-89590-844-3
印刷版発行年月 2025年2月
書籍・雑誌概要
施設で取り組めるリハビリテーションを網羅!
介護職員からリハ専門職まで役立つヒントが満載
高齢者施設での寝たきり予防・認知症予防の手引き書として、初版(1995年)から30年以上も読み継がれてきた実践書が待望の大改訂!
昨今、介護の常識や法律は大きな変化を遂げてきましたが、「施設に入るのは嫌だ」というイメージはいまだに払拭されていません。施設に入ることになった高齢者が、人生におけるその劇的な変化を受け入れ、自分らしい暮らしを取り戻し、続けていくために、施設は何ができるのでしょうか。
本書は、「リハビリテーション=その人らしい生活を取り戻すさまざまな取り組み」と考え、施設生活の随所にリハを展開することで、入所者も施設も生き生きと変わっていくことを実践例とともに紹介しています。経験豊富な作業療法士・理学療法士が、専門的な知識を元に、入所者とのつきあい方、日々の介助をしながらできるリハ、認知症への対応、口腔ケア、グループ活動の運営、多職種で協力する方法など、施設職員にできる多くの取り組みを解説しています。
わかりやすい文と豊富なイラストで理解しやすく、これから介護分野に取り組む人にも最適です。高齢者介護に関わるすべての職種に役立つ知識がつまっており、施設の管理者、責任者にもぜひ読んで欲しい一冊。知りたかった施設の可能性が見えてきます!
目次
第2版 序文
初版 序文
1章 高齢者施設とリハビリテーション・・・出田めぐみ
1 高齢期の生活と入所施設
(1)高齢者が入所できる施設
(2)施設で提供できる生活
2 施設生活の長所と短所
3 施設での生活とリハビリテーション
(1)リハビリテーションとは
(2)リハビリテーションの目的は? ―自分らしい生活を再獲得していくこと
(3)生活の目的とは? ―生活こそがリハビリテーション
(4)生活支援のヒント ―入所者のタイプと理解のしかた
(5)入所者自身の「課題への対処方法」と支援の方法
4 ICF(国際生活機能分類)の活用
(1)ICF(国際生活機能分類)とは
(2)ICFを使った考え方
・症例
2章 施設生活を支援するための基本的な視点・・・鼓 美紀
1 その人らしさへの支援 ―生活を支援するための視点は? 主体性のある生活への支援のために
2 入所時の支援 ―新しい環境への適応と新しい生活の構築
(1)適応の過程
(2)適応への支援
(3)人格のとらえ方
(4)人格の偏りと接し方
3 対人関係を支援する視点 ―豊かな人間関係のために
(1)信頼関係
(2)訴えをいかに聞くか
(3)アクティブ・リスニングのすすめ
(4)訴えの内容と対応
(5)入所者同士の人間関係
4 前向きな生活への支援
(1)欲求を満たすこと
(2)意欲を阻害するものとの対処の仕方
3章 運動機能に応じたアプローチとマネジメント・・・明道知巳
この章の見方
1 歩ける人
(1)観察すること
(2)目標とするところ
(3)自立支援のために ―QOLの向上を含めて
(4)生活の中でのリハビリテーション
(5)歩ける人のトレーニング
・症例
2 立てるが歩けない人
(1)観察すること
(2)目標とするところ
(3)自立支援のために ―QOLの向上を含めて
(4)生活の中でのリハビリテーション
(5)立てるが歩けない人のトレーニング
3 ひとりで起きられるが立てない人
(1)観察すること
(2)目標とするところ
(3)自立支援のために ―QOLの向上を含めて
(4)生活の中でのリハビリテーション
(5)ひとりで起きられるが立てない人のトレーニング
4 ひとりでは起きられないが起こせば座っていられる人
(1)観察すること
(2)目標とするところ
(3)自立支援のために ―QOLの向上を含めて
・症例
(4)生活の中でのリハビリテーション
(5)ひとりでは起きられないが起こせば座っていられる人のトレーニング
5 なんとか起こせる人
(1)観察すること
(2)目標とするところ
(3)自立支援のために ―QOLの向上を含めて
(4)生活の中でのリハビリテーション
(5)なんとか起こせる人のトレーニング
・症例
6 どうしても起こせない人
(1)観察すること
(2)目標とするところ
(3)自立支援のために ―QOLの向上を含めて
(4)生活の中でのリハビリテーション
(5)どうしても起こせない人のトレーニング
専門的な見方・トレーニング
(1)歩行の見方
(2)立位の安定にむけて
(3)立ち上がり
(4)座位機能の向上にむけて
(5)寝返りの介助
4章 認知症の理解と対応・・・出田めぐみ・鼓 美紀
1 認知症の理解と介護の視点の全体像
(1)個人レベルで理解する
(2)生活レベルで理解する
(3)社会レベルで理解する
2 認知症状が現れる疾患と特徴、介護の視点
アルツハイマー型認知症/血管性認知症
レビー小体型認知症/前頭側頭型認知症(ピック病)
3 個人レベルで考えたときの支援
(1)健康の維持
(2)運動の保障
(3)環境の調整
(4)不安からの解放
4 生活(活動)レベルで考えたときの支援
(1)規則正しい生活
(2)健康な能力の発見とできることを生かす支援
(3)日々の生活支援
(4)能力の限界を知る
(5)生活の中で困った行動が出てきたときの対処
5 社会レベルで考えたときの支援 ―社会生活上での不都合や周囲との人間関係
(1)仲間との交流 ―なじみの関係を作る
(2)仲間との交流 ―よそ行きの顔を見せる場
(3)社会の中で役割を果たすこと
6 認知症のある人にあった作業とは
(1)なじみのある作業 ―作業歴から導き出せる作業
(2)できる部分を使ってできる作業 ―やりたいという気持ちがある人
(3)できることが見つかりにくいとき
(4)ごく簡単な作業を使った作品作り
(5)レクリエーション
5章 コミュニケーション障がい者のリハビリテーション・・・藤井有里
1 コミュニケーション障がいとは
(1)コミュニケーションの大切さ
(2)話すということ(バーバルコミュニケーション)
(3)ノンバーバルコミュニケーション
2 聴力の低下(老人性難聴)
(1)老人性難聴とは
(2)症状
(3)接し方
3 失語症
(1)失語症とは
(2)症状
(3)接し方
4 認知症
(1)認知症によるコミュニケーション障がいとは
(2)症状
(3)接し方
5 運動性構音障害
(1)運動性構音障害とは
(2)症状
(3)接し方
6 コミュニケーション障がい者のリハビリテーション
・症例
6章 生活・活動への支援 ―入所者中心の支援に向けて・・・出田めぐみ
1 生活・活動を支援するということ
(1)生活のとらえ方
(2)生活を支援する視点
2 生活・活動の大前提
3 生活・活動の支援の実際
(1)快適な居場所づくり
(2)身だしなみ、整容
(3)更衣
(4)排泄
(5)食事
(6)食事支援の実際
4 ADLとIADL
(1)ADLとは
(2)ADLの自立と生活の質
(3)QOLとは
(4)QOLの評価
(5)人間の楽しみとは
(6)QOLの支援の実際
7章 口腔ケアの実際・・・北川まさ美
1 口腔ケアと健康
(1)口腔ケアとは
(2)組織に対するケア(口腔清掃・口腔衛生管理)
(3)機能に対するケア(口腔体操・口腔機能のトレーニング)
2 日々の口腔清掃の実際
(1)自分で磨くためのサポート
(2)口腔清掃の手順
(3)清掃道具
3 口腔機能の維持・向上トレーニング
(1)口腔機能トレーニングの実際
(2)食前の口腔体操
4 チームアプローチ
(1)日々のチェック
(2)義歯のチェック
(3)認知症のある人のケア
(4)看取りの時期のケア
(5)歯科連携
(6)他職種連携の実例
・症例
8章 グループ活動の実際・・・西井正樹
1 グループ活動のとらえ方
(1)グループ活動の意義
(2)プログラム決定の要因
(3)高齢期の特性の理解
(4)身体機能面から見た活動の利用法
(5)精神機能面から見た活動の利用法
2 計画の手順と立案
(1)プログラムを考える前に
(2)プログラムを立案するときに考える要素
(3)計画の立て方・計画の手順
(4)集団の特性と利用法
3 活動の実際
(1)グループ活動の基本
(2)グループ活動のいろいろ
(3)グループ活動の実際
(4)自己表現の場
(5)役割づくり
・症例
9章 多職種協働と支援・・・鼓 太志
1 働く職種と入所者との関係
(1)職種の専門性と役割
(2)入所者からみた専門職
(3)入所者から得られやすい情報と共有の必要性
(4)情報収集のタイミング
2 多職種が協働することで何ができるか
(1)入所者支援と目標設定
(2)入所者主体の目標の設定
(3)目標の実現に向けた取り組み
・症例
3 情報交換の実際と工夫
(1)情報共有の難しさ
(2)情報共有への工夫
索引