- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
筆者は今回の特集編者の一人である。山中康裕先生の下で心理療法を学び,先生とのあいだに生まれたのが今回の特集である。しかも,特集の内容に関して一切の指示をされず,見守ってくださり人を育てる,まさに臨床的姿勢そのものであった。そして,このような一生に二度とない機会をくださり,お礼を尽くせないほどの感謝の気持ちである。お返しは本論でする他はない。
児童相談所(以下,児相と記す)は児童「虐待」注1)の専任機関であるような印象を持たれることが多いが,実際は,療育手帳の判定,育成・非行相談など子どものあらゆる相談を受ける総合相談機関なのである。また,毎年「虐待」の相談受理件数の増加は大きく報道されているが,しかし全国統計を見れば,減少している地域も毎年あるのが事実であり,「虐待」は都市的なものであるという指摘もある(内田,2009)。また,組織形態や体制・規模,担当のケース数,職員の職務経験・経験年数などは多様であり,児相として一まとめにできない現状がある。これまで児相の支援について,「なにをするか」といった児相を主体にしたものは充実してきたが,対象である利用者を中心とした支援のあり方についての論考は少なかった。それは“エビデンス”の台頭により,それを後ろ盾に目の前の人を操るかのように扱う危険性があることに盲目的であったり,“行い”ばかりに注目が集まったりし,支援者自身が主要観察用具(Sullivan, 1954)であるにもかかわらずそれが蔑まれているようにも感じる。利用者の体験に目を向け,“個”として背景を理解すること,そして利用者と支援者の“関係”をも含めて支援を考えるということは精神療法の原点である。この原点に返ることで,他機関にはない唯一組織の権限と判断で,利用者との接点を持つことができる児相だからこそ実現できる支援というものがあるはずである。
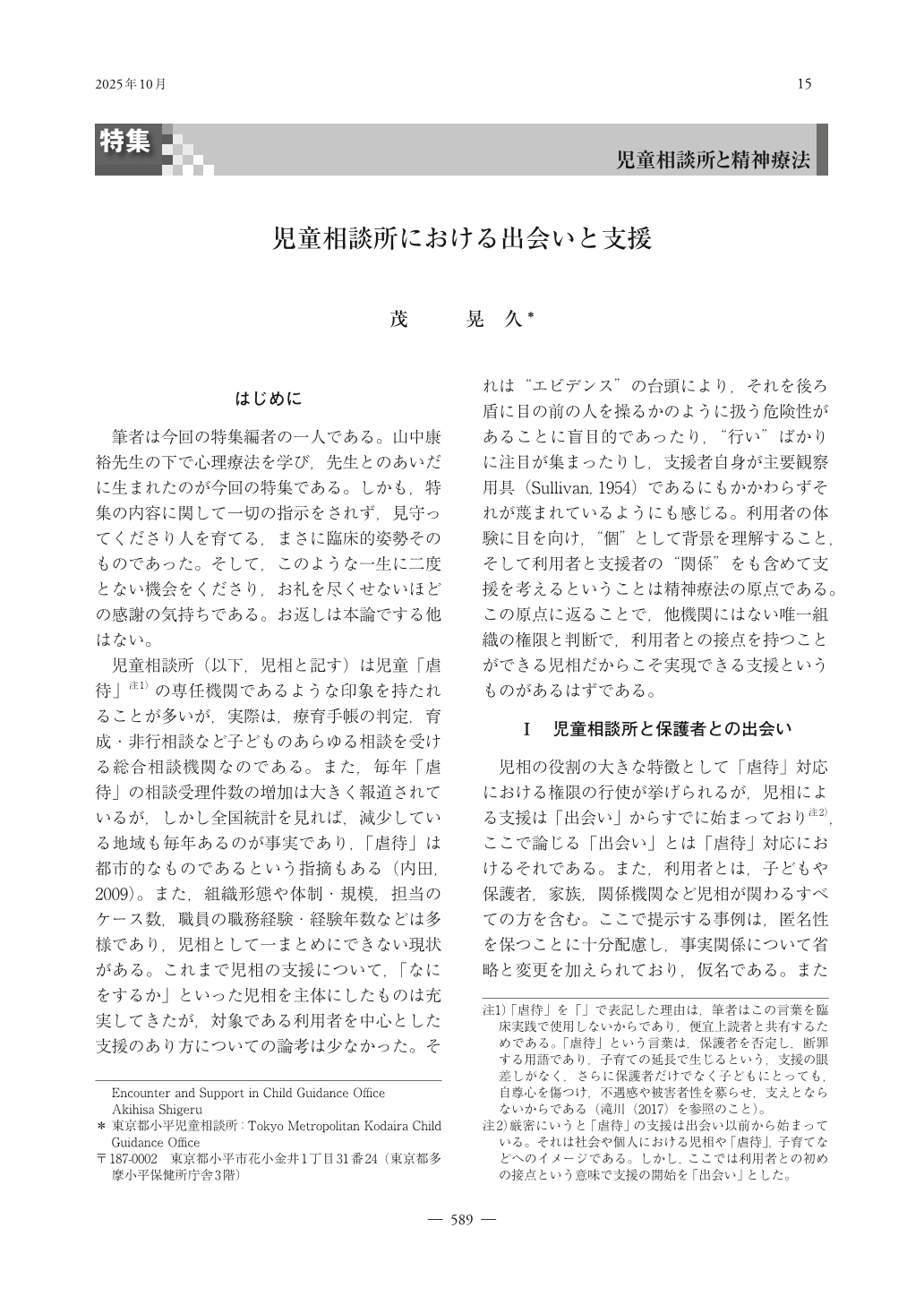
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


