- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 少年非行の心理アセスメント
筆者はかつて家庭裁判所調査官として,触法行為をして家庭裁判所に送致された少年の生育歴や家庭環境,社会的状況の調査および知能や認知特性の心理アセスメントを担当していた。多くの少年事件を担当するに従い,少年たちが,それまで想像もしなかった多くの困難を抱えていることを知った。
たとえば,家庭裁判所に少年と保護者が持参する小学校の通知表を見てみると,低学年の頃からオール1であったり,それに近い数字が並んでいる。少年に聞くと,小学校2年頃から授業がわからなくて,教室内外を歩き回り,教師から厳しく叱責され,ますます学校で暴れたりしていたというケースが多かった。その背景には,少年がADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症),LD(学習症)などの発達障害と診断を受けていたり,その傾向があるが早期発見がなされずに見過ごされ,衝動的な行動や学習不振について「しつけ不足」「勉強ぎらい」などとみなされ,結果的に自己イメージが低下し,投げやりになっているケースも多く見受けられた(熊上,2015)。
また,家庭環境を見ると,離婚家庭(主に母子家庭)が多く,その背景にDV(家庭内暴力)や子どもへの身体的・心理的虐待が見られ,経済面では,養育費の不払い,生活困窮による同居親の昼夜の仕事により結果的に子どもが夜間放任されるケースが多かった。このような事情を聞くと,保護者を責めることはできず,むしろこれまで必死に困難な状況で子どもの養育と仕事に努めながら,思うようにいかなかった保護者の思いに寄り添うことが大切であると実感した(熊上,2023)。
このように,家庭裁判所に少年事件として送致される子どもは,発達面や学力面だけでなく,家庭環境や経済面での幾多の困難を抱えている。家庭裁判所に来る少年たちは,面接室では決まって暗く,ぶっきらぼうな様子で,大人への不信感を示して,触法行為は認めるものの,家庭や学校で放置されており,自分だけのせいではない,と訴えているようであった。
そこから筆者は,少年非行を理解して子どもと家庭を支援するため,少年たちの発達,家庭環境,心理的状況をしっかりとアセスメントし,その結果を本人および保護者,学校などの支援者と共有し,支援体制をつくることが重要であると考えるようになった。
そこで本稿では,ある少年非行事例の心理アセスメントを紹介し,非行という行動だけに着目するのではなく,背景にある知的・発達的側面や心理社会的側面を理解し,心理アセスメント結果を本人および関係者にフィードバックして共有・協働する必要性について述べる。なお,事例は実際のケースを個人が特定できないよう加工したものである。
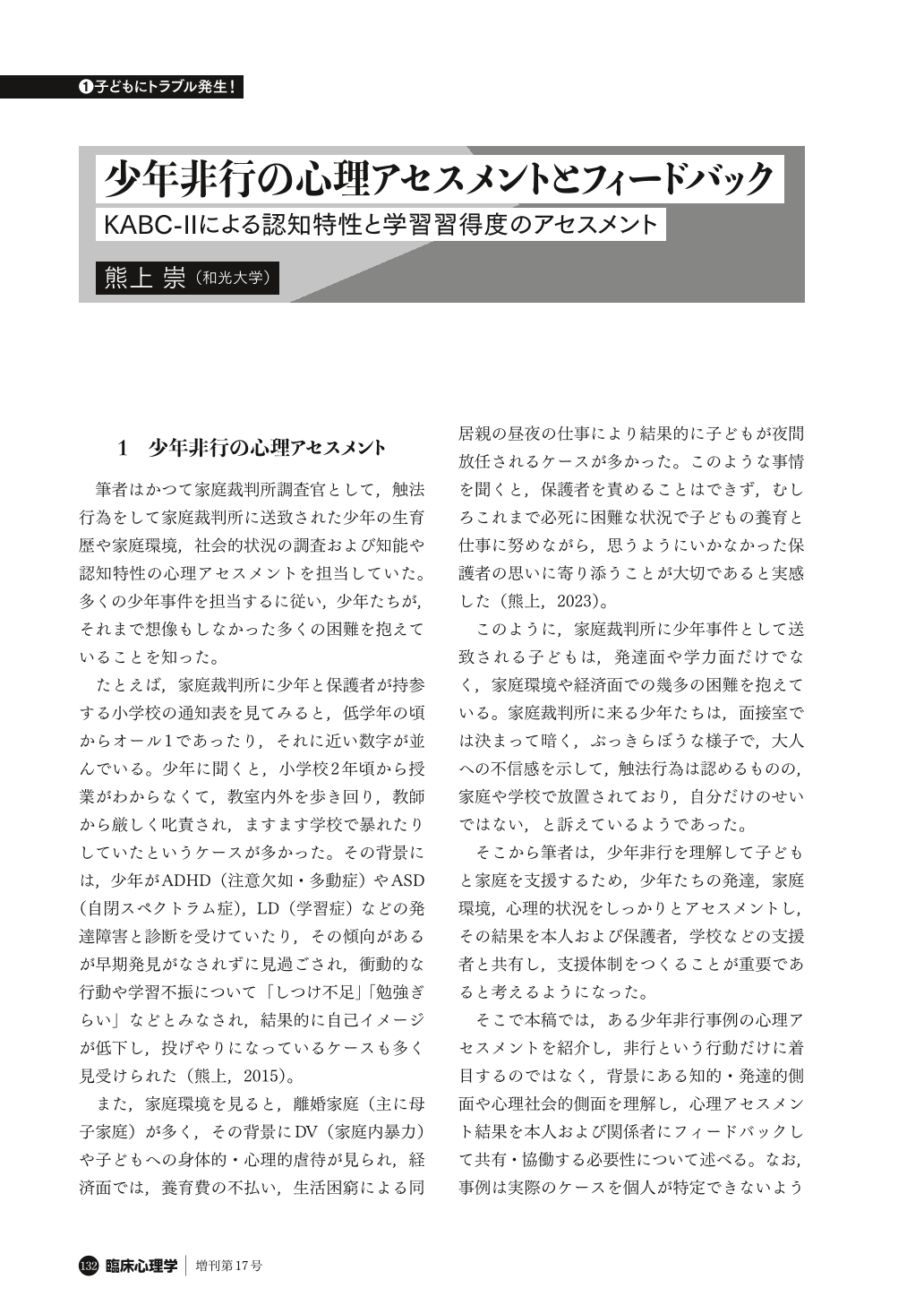
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


