- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
社会的な交流は日常生活の大きな一部である。そのため,社会的交流の阻害が精神的な不調,特に社会的適応力と強く関わる気分障害に繋がることは不思議ではない。今回紹介するKämpf & Kanske(2023)では,社会的交流の阻害を「多様な社会的文脈や要求に柔軟に適応するために行動的・認知的・情動的能力を統合する障害により,特定の社会的文脈の基準に従って否定的なものと判断される行動結果が生じること」としている。
模倣(mimicry)は,対人コミュニケーションにおいて意識的・無意識的に常に生じている。模倣には,言語的な側面(例:相手と似た言葉やアクセントを使う)と非言語的な側面(例:相手と一致する表情やジェスチャーを示す)の両方が含まれる。模倣には大きく分けて2つの機能があるとされる(Olszanowski & Wróbel, 2024)。ひとつは他者との間に親和性や共感を醸成する機能であり,もうひとつは他者の感情をより深く理解することを助ける機能である。これらの機能はいずれも円滑な社会的交流に寄与するものである。今回紹介するKämpf & Kanske(2023)では,気分障害を持つ人が社会生活のなかで直面する問題が,模倣によって説明される可能性を模索している。なお,ここで紹介される「模倣」は,表情模倣(facial mimicry)に限られる。Kämpf & Kanske(2023)ではDSM-5に沿って気分障害を分類しているが,先行研究の結果をより簡潔にまとめるため,本稿では気分状態を「抑うつ状態」「躁状態」の2つに区分する。また,紙幅の都合で,Kämpf & Kanske(2023)で紹介されている文献は割愛し,紹介者が追加した文献のみ引用文献として付す。
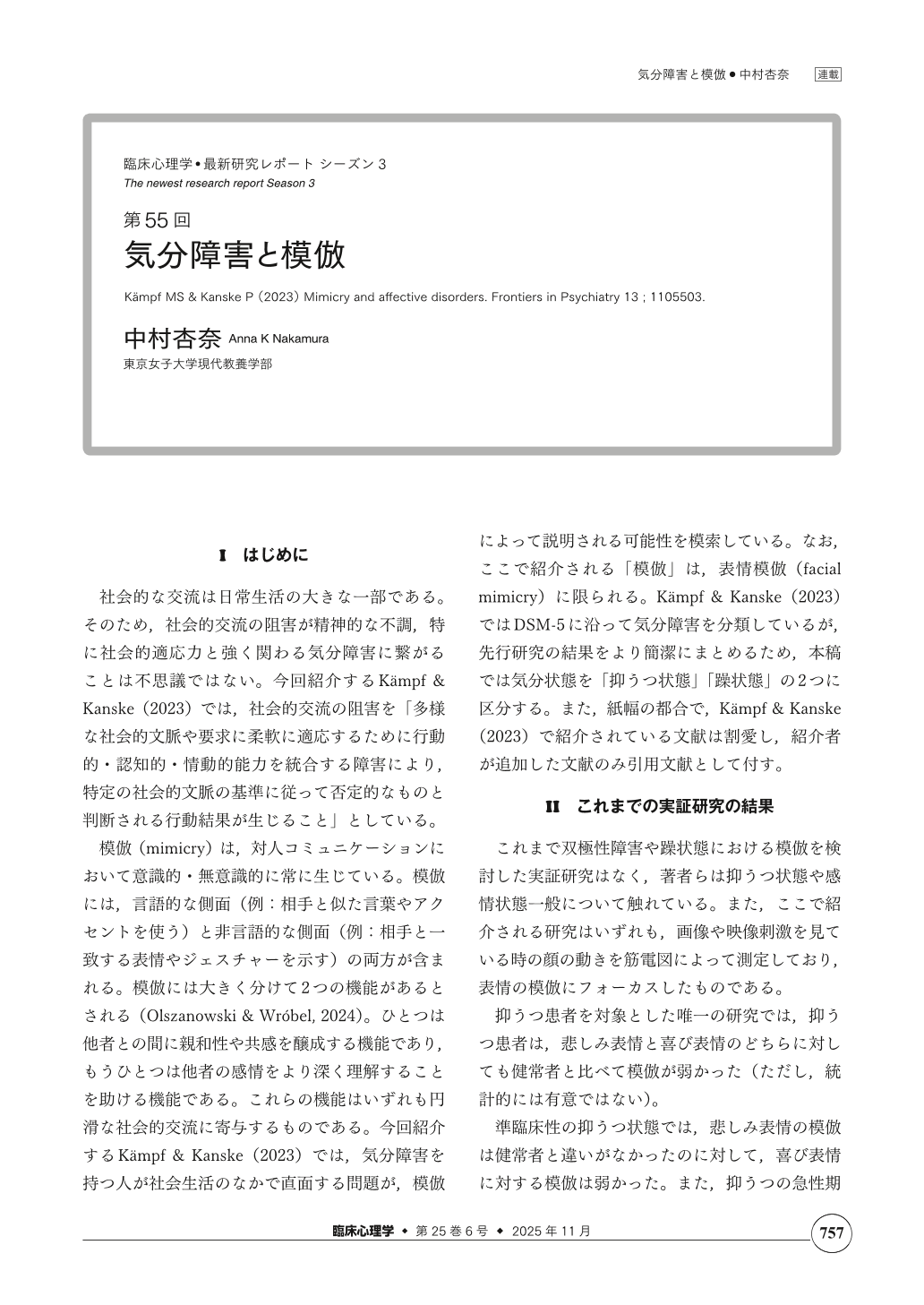
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


