投稿論文 症例研究
同一治療者による親子それぞれへの心理的介入の試行 親子同席面接、親子逐次面接、そして個人心理療法へ
仲谷 隆
1
1早雲会北条クリニックおおの
キーワード:
チック
,
怒り
,
親子関係
,
共感
,
自己概念
,
心理的ストレス
,
ライフスタイルの変化
,
同一化(心理学)
,
表情
,
心理学的面接
,
不登校
,
心理社会的介入
Keyword:
Psychosocial Intervention
,
Facial Expression
,
Empathy
,
Life Change Events
,
Self Concept
,
Phobic Disorders
,
Parent-Child Relations
,
Identification, Psychological
,
Interview, Psychological
,
Anger
,
Stress, Psychological
,
Tics
pp.83-92
発行日 2022年2月5日
Published Date 2022/2/5
DOI https://doi.org/10.69291/J00762.2022084357
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
思春期の発達課題の一つに第二の個体化があり、親子の関係を再定義するためにも家庭内での世代間境界の形成が必須となる。その方法には、親面接を中心に行う技法も、親子関係へ直接介入する技法もある。年齢不相応に親子の分離が困難な事例などさまざまな事情により、理想的な治療構造を設定できないこともある。しかし心理面接が始まることで親子共に変化し成長することも少なくない。筆者は子どもの発達と家族状況の進展に応じて治療構造を変化させることは有用と考える。その場合には、外的葛藤と内在化された葛藤の解消を目標に行い、治療者が親子それぞれと話し合って共に構造を選ぶことが必要である。本論では筆者が一人である思春期男子とその両親への心理的介入を行った症例を発表した。この症例は両親の関係に巻き込まれている家庭状況と自己主張ができないという男子自身の課題を扱う必要があった。筆者はまず外的葛藤に介入するための面接構造を設定し、家庭状況が整ってから内在化された葛藤に取り組む面接構造へと変化させた。一人の治療者が親子それぞれに関わることや面接構造を変化させることは、親子の力動に巻き込まれて逆転移が生じやすく、治療関係や治療者自身に混乱を生じる可能性はある。しかし治療者が発達促進を目指すという一貫した目標をもって親子と理解を共有して取り組むことができれば、思春期の第二の個体化を促す可能性が示された。
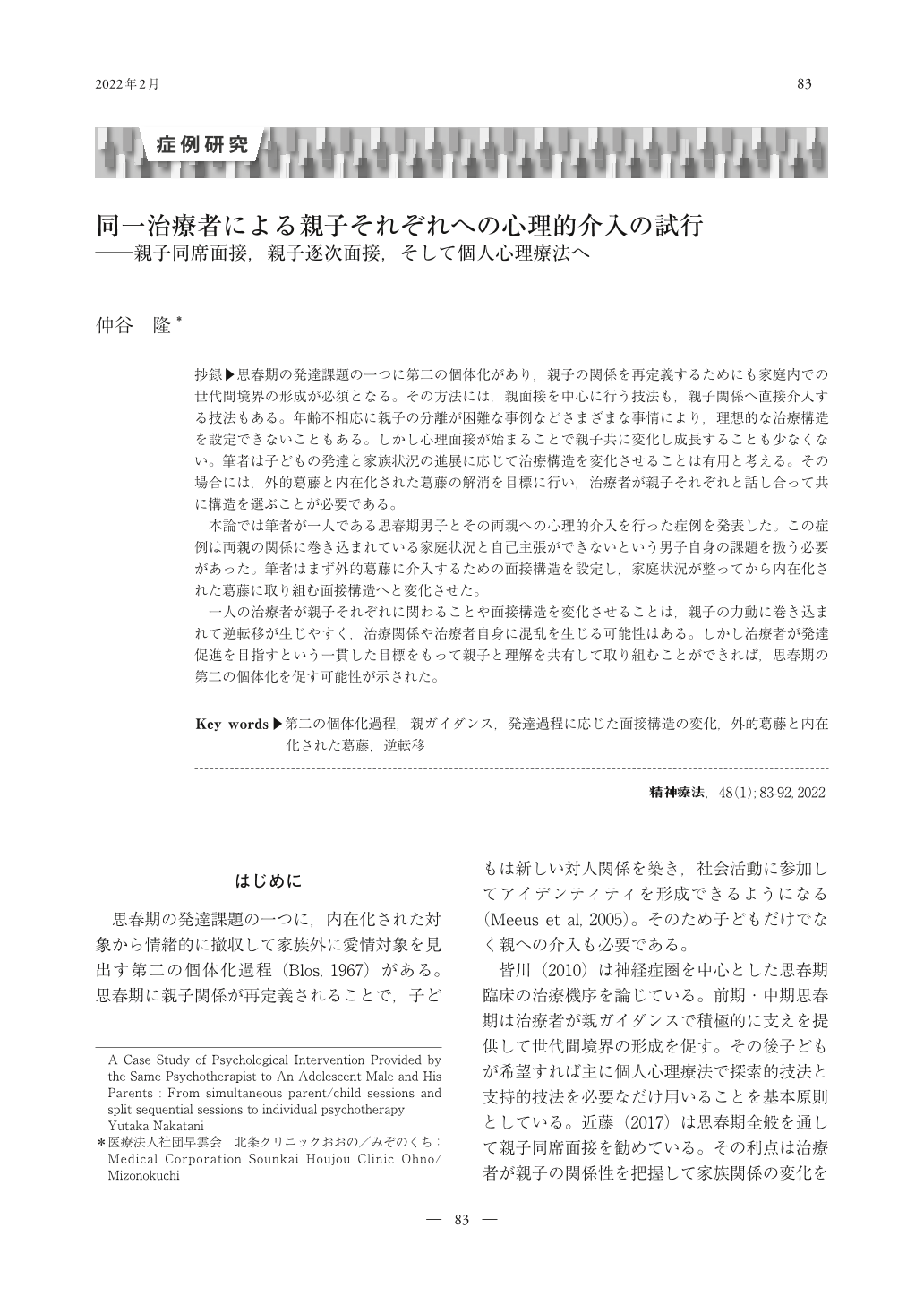
Copyright© 2022 Kongo Shuppan All rights reserved.


