- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
生き物の定義でよく知られているのが次の3つだという.
①複製能
②外環境から隔離された内環境
③代謝能
あるいは最新の定義としては,イギリスの遺伝学者によるもの.
①自然淘汰を通じて進化する能力をもつ
②境界をもつ物理的な存在である
③化学的・物理的・情報的な機械である
(ポール・ナース*1,2021年)1)
ポール・ナースの定義(仮に定義2とする)を,最初の定義(定義1とする)と比較してみる.
定義2の②は,定義1の②に該当する.定義2の③のうち化学的・物理的な機械は,ほぼ定義1の③の代謝能に対応している.ただし,定義1には情報的,つまり遺伝情報に基づくという概念は含まれていない.
また,定義2の「進化」の項目は,定義1にはない.単に複製能を有するだけでなく,「自然淘汰を通じて進化する能力をもつ」という生命の定義,遡ればダーウィンの進化論にもみられ,実は新しくて古い.
定義1,2に加え,生命を定義した書籍を,自分の本棚で探してみた(表1)1-3).
これらの著者のなかに,ノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者,シュレーディンガー*2がいた.彼は専門の物理学に留まらず,生物を論じた古典的名著3)を著し,生命を「負のエントロピーを食べるもの」と定義した*3.
それよりはるか昔,驚くことに2300年も前,プラトンの弟子である古代ギリシャの哲学者アリストテレスも,生命の定義を記している2).
彼は,さまざまな領域を体系的に研究し,哲学を科学的探究として確立したことから学問の父,「万学の祖」と呼ばれる.なかでも,生物学,動物学では,解剖や発生の観察を通して顕著な成果を残している.
彼の師であるプラトンは,身体と霊魂(プシュケー)を切り離された存在としてとらえ,心身二元論を唱えた.一方,アリストテレスは,霊魂を独立に存在するものとは考えず,身体に内在し,感覚,運動,思考といった機能を可能にする,すべての生き物の生命活動を担う原理としてとらえた.
この身体と不可分な生命の原理は,「こころ」の概念にも通ずる.
私は,からだを支える根本にある「こころ」を生命の定義と考える.
「こころ」と,解剖で目に見える「脳」との違い*4.
ヒトでは,「こころ」はその行動の根元にあり,社会さえもつくってみせる.
われわれのすむ惑星,地球の生命は,この「こころ」でできている,といえないか.なんという驚き.
ヒトが「こころ」の指令によってとる行動の根拠には,数え切れないほどの酵素などタンパク質の働きがある.それを設計するのが遺伝子,さらに,遺伝子の本態として発見されたDNA.
今回のD’StoryのDは,このDNA.そして,そのDNAがもたらす変化,進化という考え方を提唱したイギリス人,同じくDを名字にもつDarwinへとつながるお話.さらに,3つ目のDはダーウィン主義のドーキンス Dawkins.
ドーキンスって誰? ダーウィンほどには知られていないものの,ダーウィンと同じくイギリス出身で,ただしドーキンスは21世紀に生きる人.
ダーウィンの進化論における遺伝の担い手はDNA.そのDNAが実は“利己的”であるとの視点から,豊富な観察例に基づいて構築された動物の行動理論は,1976年の発表以降,いまだ大きな影響を与え続けている4).
DNA,Darwin,Dawkinsの三題噺,はじまりで~す.
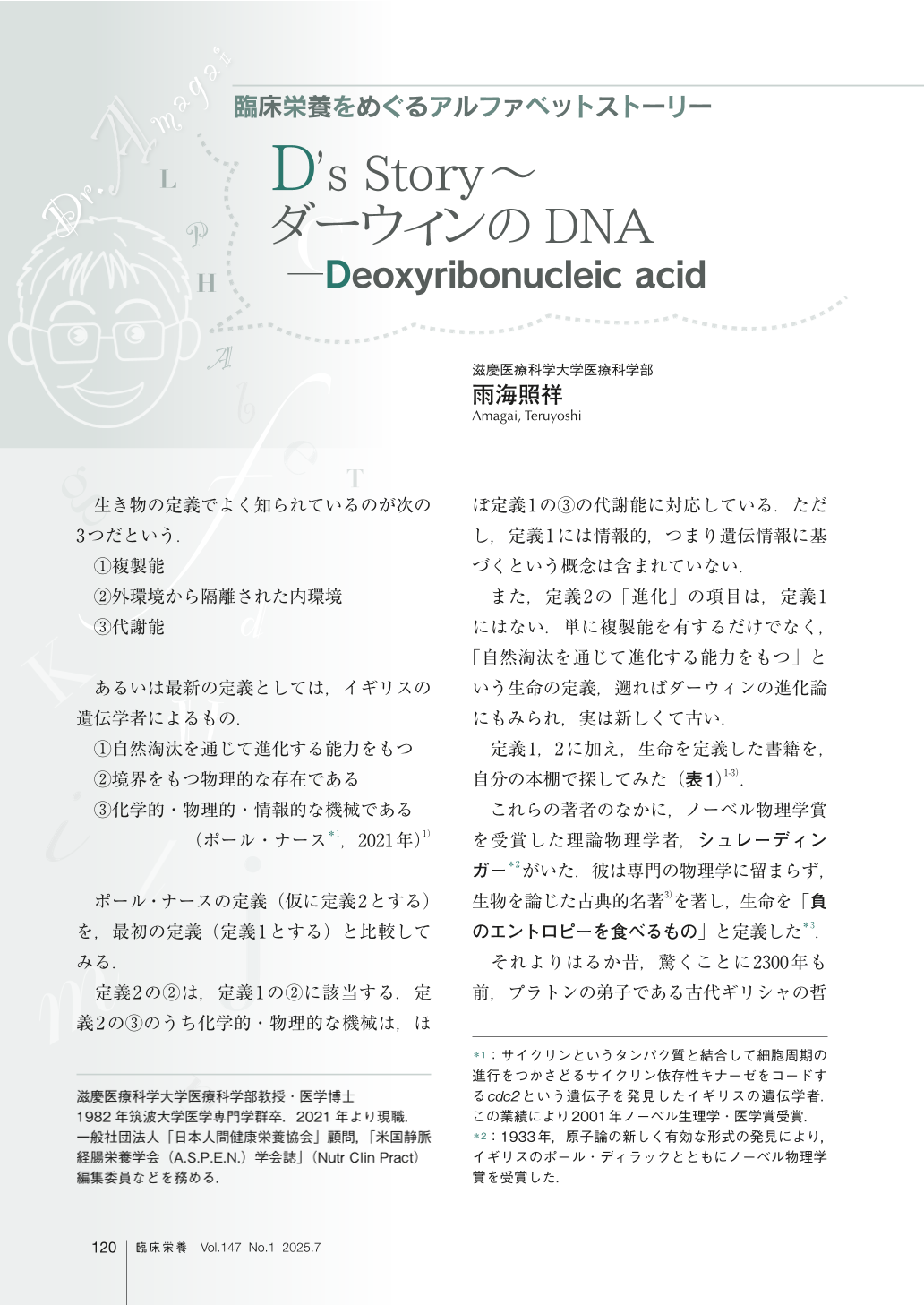
Copyright © 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All Rights Reserved.


