Japanese
English
連載 細胞を用いた再生医療の現状と今後の展望――臨床への展開・Vol.11
培養自家骨膜細胞を用いた顎骨再生医療の臨床実用化における課題と取り組み
Clinical implementation of jaw bone regeneration using cultured autologous periosteal cells:challenges and strategies
永田 昌毅
1
Masaki NAGATA
1
1新潟大学医歯学総合病院高度医療開発センター
キーワード:
培養骨膜細胞(CPC)
,
顎骨再生
,
歯科インプラント
,
歯周病
,
咬合機能回復
Keyword:
培養骨膜細胞(CPC)
,
顎骨再生
,
歯科インプラント
,
歯周病
,
咬合機能回復
pp.663-669
発行日 2025年2月22日
Published Date 2025/2/22
DOI https://doi.org/10.32118/ayu292080663
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
SUMMARY
顎骨は,歯性疾患一般,腫瘍性疾患,外傷,先天性疾患等で様々な形と大きさの欠損を生じる.それらの再生治療は整容と機能回復治療の基礎である.筆者らは,顎骨から採取した自家骨膜を培養することで製造した「培養自家骨膜細胞」による顎骨再生医療に取り組んでいる.名古屋大学のグループがイヌにおける動物実験段階1)からヒトにおけるPOC試験2)を報告した再生医療技術を新潟大学において導入し,2007年から小範囲の歯槽骨欠損に対する臨床試験を77症例に実施した3,4).また,2016年からは再生医療等安全性確保法下の第2種再生医療として39症例の患者に治療を実施し,臨床試験と治療を合わせて延べ116症例の実績を有している(図1).5例では感染によって移植材の同化と骨再生が得られなかったが,111症例で骨再生が得られた.そのうち110症例には歯科インプラントによる咬合の回復治療が行われ,残り1症例では歯周病で失われた歯周組織再生によって噛み合わせの安定化が得られた.培養骨膜による骨再生医療では5カ月で骨形成が迅速に進行するとともに,再生骨は3年で正常な歯槽骨と同等のCT値構成の骨質を獲得する.これは一般的な自家骨移植では得られない排他的な効果である.再生医療の臨床実用では,治療工程や手続きの煩雑さ,高い治療コストが患者と医療従事者の双方にとって負担となるが,他の治療法では得られない正常骨再生効果は選択肢として価値があり,安定した臨床実用の普及に向けた継続的な開発が推進されている.
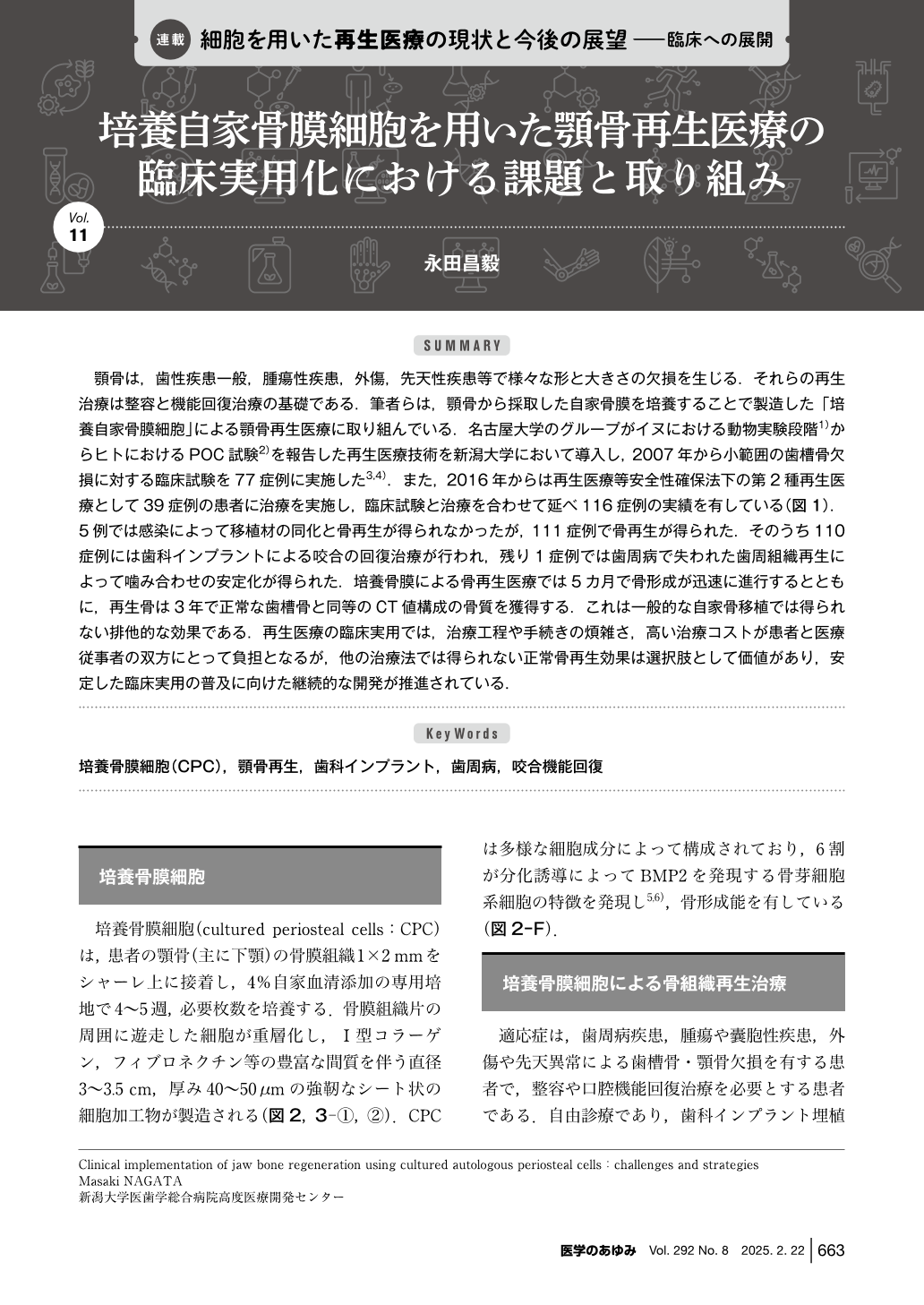
Copyright © 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All Rights Reserved.


