Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
1 はじめに―高尿酸血症と慢性腎臓病
血清尿酸値は,尿酸産生量と腎臓を中心とした尿酸排泄能のバランスにより決定される。正常な体内での尿酸動態は,1日約700 mgが肝臓などで生成され,腎臓から尿中(約7割)または消化管から便中(約3割)に排泄され,血中の尿酸量は常に一定になるようにコントロールされている。慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者では,一般的には腎機能低下が進むにつれて近位尿細管での分泌能が低下することで高い頻度で高尿酸血症が認められる。さらにCKDが進行するにつれ処方頻度が増えてくる利尿薬も尿酸の再吸収を増加させることで高尿酸血症を誘発する(尿酸排泄低下型)。また,過食や高プリン食・高脂肪食,運動不足などの生活習慣は体内での尿酸産生の増加(尿酸産生過剰型)や腎臓での尿酸再吸収の増加をもたらし高尿酸血症につながるが,これらの生活習慣はいずれもCKDのリスク因子として重要である高血圧や肥満,耐糖能異常や脂質代謝異常の病因にもなる。また近年新たな分類として腎外排泄低下型という病型も提唱され1),透析患者のように腎排泄量が極端に低下すると代償的に消化管からの排泄が増加したといった報告もみられる。この腎外排泄の主体として現在知られているトランスポーターがATP-binding cassette subfamily G member 2(ABCG2)であるが,CKD患者は全尿酸排泄における腎外排泄の比重が大きいため,ABCG2の活性低下による尿酸上昇の影響を受けやすい2)。このように,CKD患者では単純な排泄低下型のみならず,産生過剰型あるいは腎外排泄低下も合併する混合型の高尿酸血症である場合も少なくないため,CKD患者においては尿酸産生抑制薬の果たす役割も依然重要である。一方で,高尿酸血症自体も痛風結節や尿酸結石の形成といった尿酸塩の析出にかかわるだけでなく,腎障害や心血管系合併症リスクの増加との関連が示唆されている3)。これらのことからCKDと尿酸は双方向性の関係と捉えることができる。『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン』4)では,「腎障害を有する高尿酸血症の患者に対して,腎機能低下を抑制する目的に尿酸降下薬を用いることを条件付きで推奨する」としている。
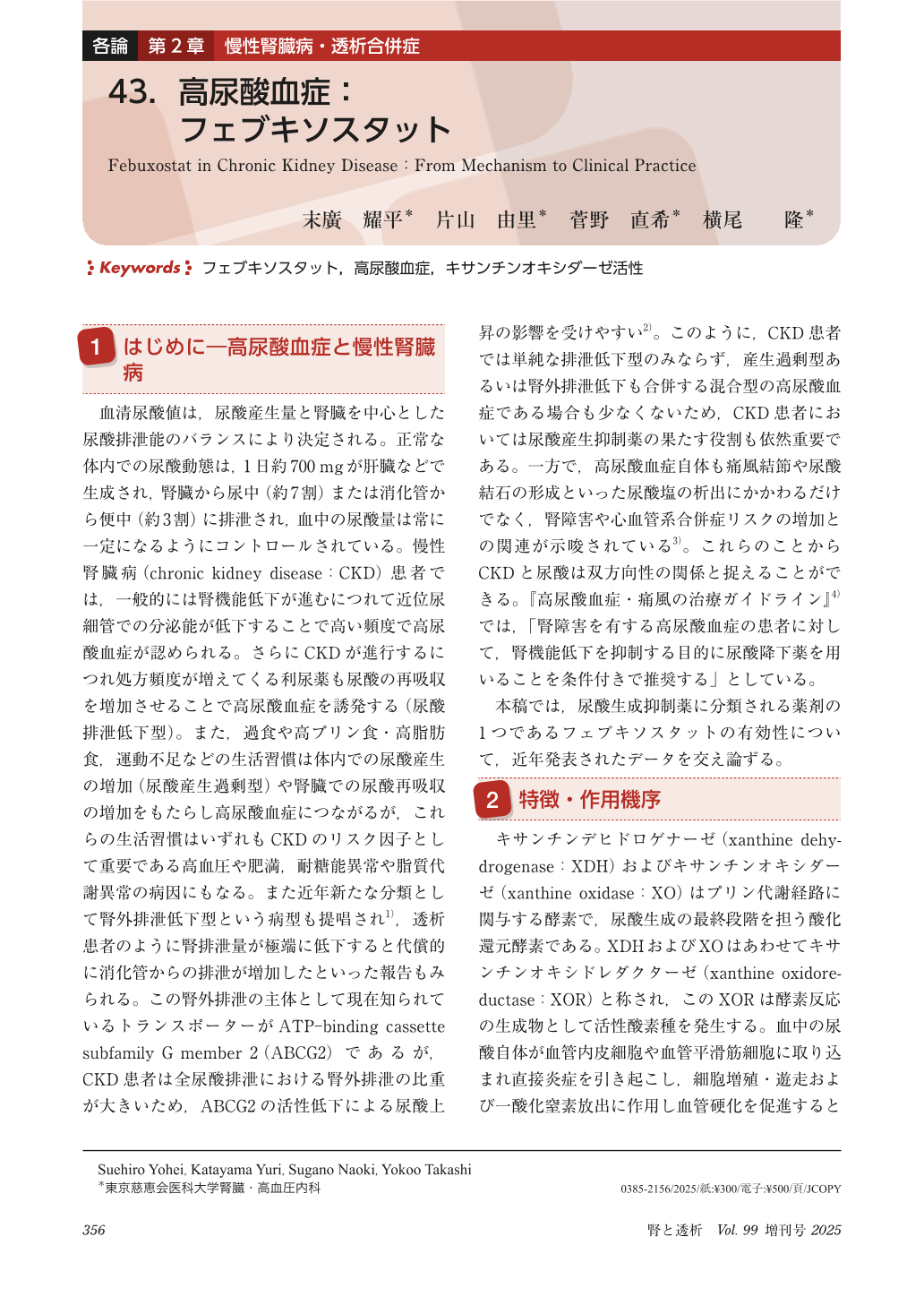
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


