話題
痛みの国際シンポジウム
横田 敏勝
1
Toshikatsu Yokota
1
1滋賀医科大学生理学教室
pp.76-78
発行日 1983年2月15日
Published Date 1983/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.2425904508
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
昔懐しいいろはカルタに「わが身をつねって,ひとのいたさをしれ」というのがあった。我が身を抓って生きているのを確かめたというのも,よく聞く話である。痛みは生きていることの証しであろう。生れつき痛みを感じない先天性無痛症の患者は,体のいたるところに傷痕や痣をもち,火傷を負っても,肉の焦げる匂いがするまで気付かない。度重なる骨折で関節も変形している。小さな傷口に感染があっても,本人は気付かず,敗血症による全身症状がでて,周囲の人々が慌てるという始末である。痛みは,体に危害が加わったことを知らせる警告信号で,健康な生活を送るのに不可欠であることがわかる。しかし,分娩時の痛みに一体何の意味があるのであろうか,また余命いくばくもない人の痛みにどんな利益があるのであろうか。必要な痛みと,不必要な痛みとがあるのではあるまいかという素朴な疑問が生じるのは当然である。
産みの苦しみは子宮の収縮によるもので,最も激しい痛みの1つに数えられるが,産み終えると止んでしまう。多くの母親はやがてその苦しみを忘れて,次の子を産む。尿管結石の痛みも激痛に相違ないが,石が尿管を通過すると消え失せる。このような一過性の痛みは急性痛と呼ばれる。ところが,これとは別に,何週間,何ヵ月,ときには何年も続く痛みがある。われわれはこれを慢性痛と呼んでいる。関節リウマチや癌による痛みなどがこれである。
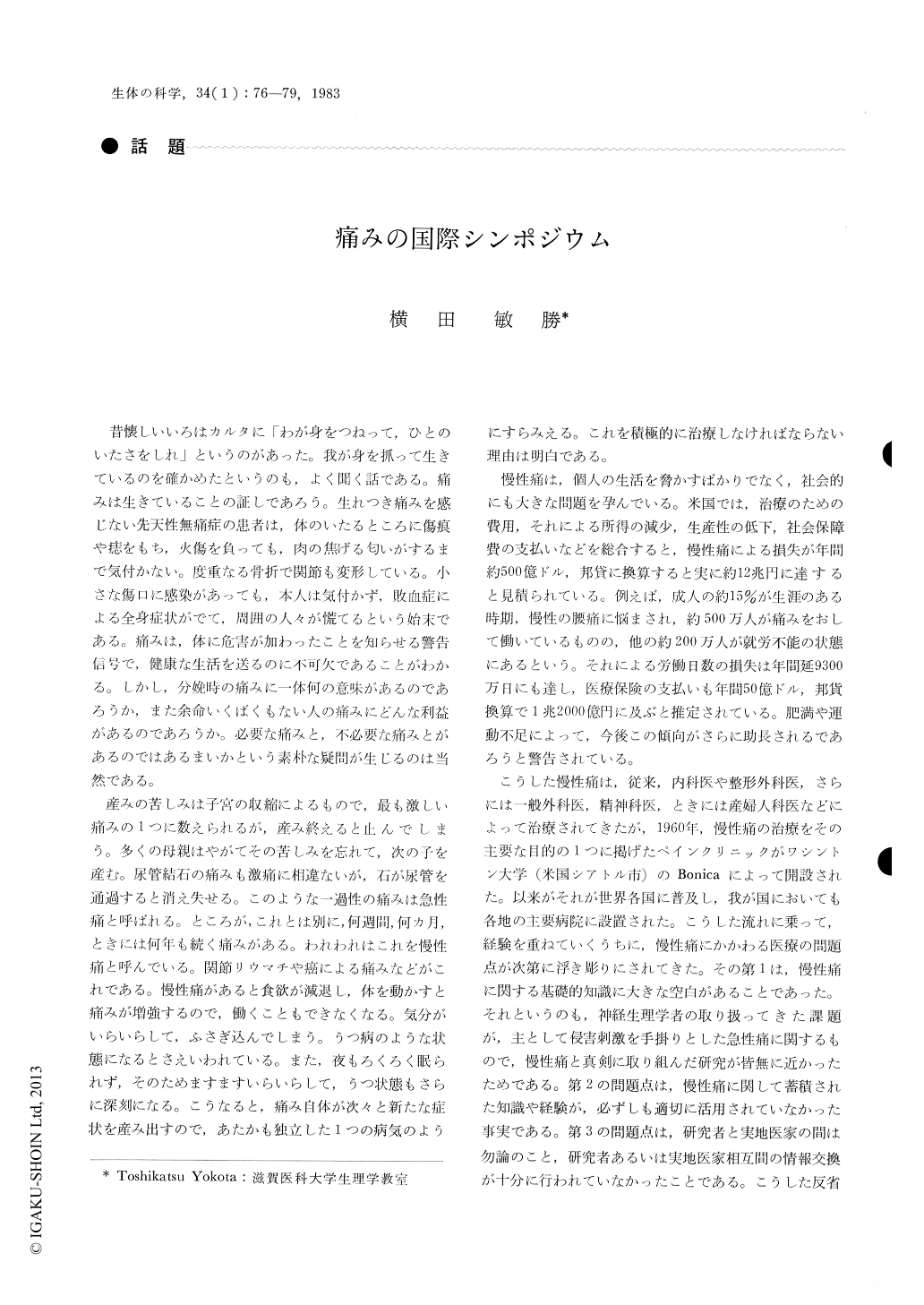
Copyright © 1983, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.


