- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
今回の特集は,構造生物学の分野で活躍している若手の方や,それを細胞レベルにまで広げようとしている方々に執筆をお願いした。構造生物学というと,数年前まではX線結晶解析と核磁気共鳴(NMR)が主に使われていたが,今回の特集をみてもわかるように,クライオ電子顕微鏡が大きな役割を果たすようになってきている。電子線直接検知型カメラが商用化されたことと,解析ソフトウエアの進歩により,2013年ごろからクライオ電子顕微鏡の解像度革命が始まった。日本では,誰もが使える形で十分な最新型クライオ電子顕微鏡が整備されていなかったため,この波に乗り遅れていた感が否めなかったが,2017年以降,文部科学省や国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)のサポートもあり,クライオ電顕ネットワークという形で共同利用施設として広く使われるようになってきた。今回の特集で執筆をお願いをした方々のなかにも,共用の電子顕微鏡を使って結果を出している方々が多い。
もう少し広い視野で見ると,構造生物学がビッグサイエンスになりつつあると感じている。ここで言う「ビッグ」は,3つの意味がある。1つは金銭的な面で,クライオ電子顕微鏡をはじめとする最先端機器は高額であると同時に維持費も掛かり,とても1つの研究室で維持管理をすることができない。もう1つは,データのサイズで,数テラバイトにも達するデータを処理する必要があり,いわゆる生命科学の知識だけでなく,情報科学,物理学など幅広い知識を学ぶことが重要になってきている。そして3つめは,扱う対象が大きくなっていることである。これまでは,X線結晶解析とNMRは多くの場合,1分子に対して使われてきたが,クライオ電子顕微鏡はもっと大きな複合体や細胞レベルの構造も見ることができる。しかし,そこで使われている手法の一つ,クライオ電子線トモグラフィーについては,まだ多くの技術開発や応用分野を開拓する必要がある。ぜひ,色々な分野の研究者がこの特集を読んで,自分の将来の研究に構造生物学を取り入れていただければと考えている。
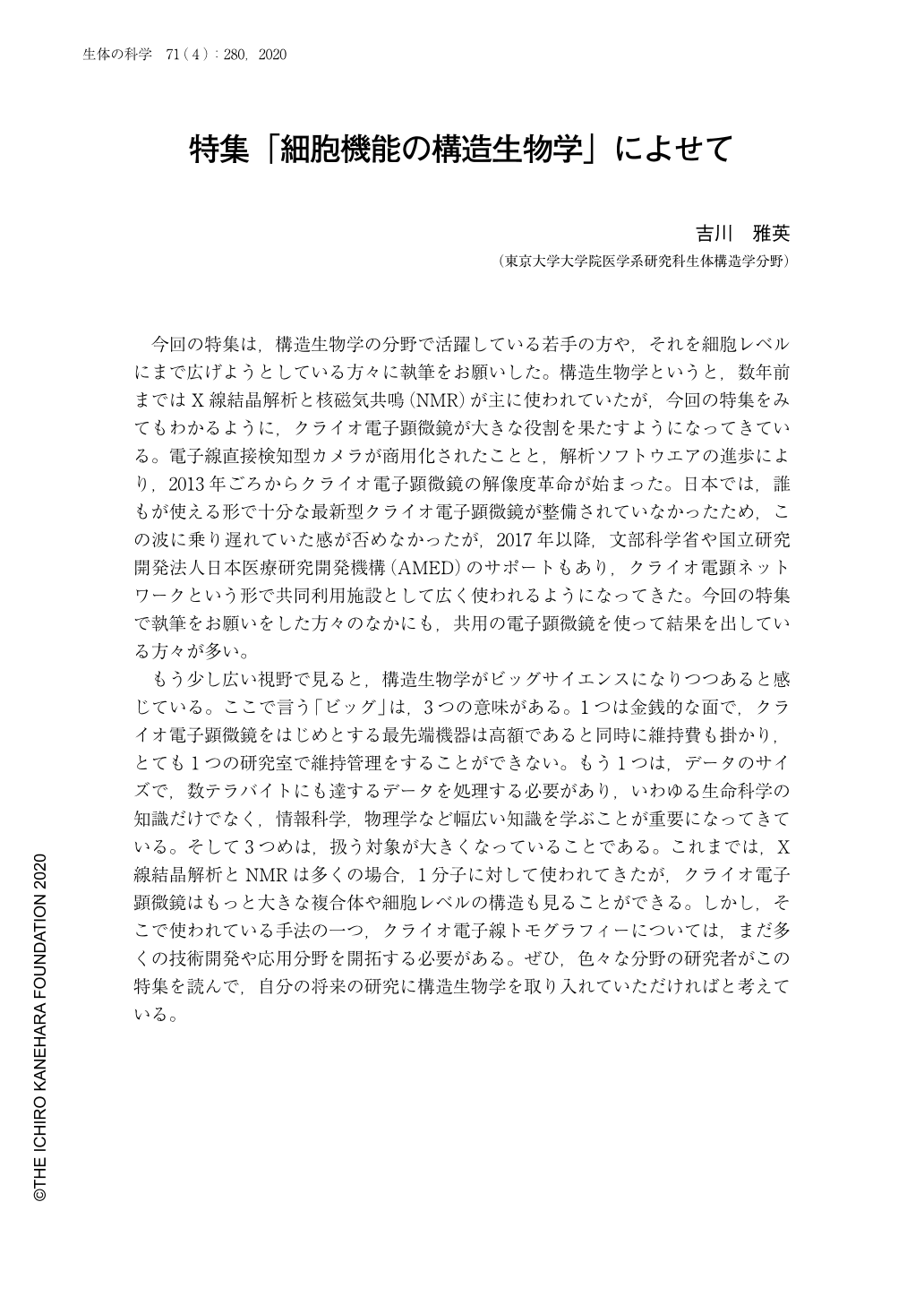
Copyright © 2020, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.


