- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
米国医学研究所(IOM*1)では,医療の質を「個人および集団に対する保健サービスが,期待した健康アウトカムを達成できる可能性を上昇させ,かつそれが最新の専門的知識に沿っている程度」と定義している1)。つまり,医療実践が過去のエビデンスに基づく標準治療に合致している度合いを高めることは,医療の質向上につながるといえる。そして,自身の診療現場で医療の質の尺度である質指標quality indicatorを測定し,エビデンスと実践の乖離を把握してその改善を試みることが,まさに医療の質改善活動の1つとなる。
例えば,AHA/ACC*2の心筋梗塞の質指標に関する報告2)では,急性心筋梗塞で入院した患者で「退院時にアスピリンやβ遮断薬,高強度スタチンが処方されていること」が質指標の一部となっている。医療の過程を示すプロセス指標ではあるが,これらの薬剤を投与することで急性心筋梗塞後の患者の予後というアウトカム指標を改善させるエビデンスが存在するため,標準治療となっているのである。これは,米国臨床薬学会(ACCP*3)の示す急性期/病棟薬剤師の医療の質指標3)では,「有効性,安全性」ドメインの「薬物療法のレビュー」や「再入院の減少」の指標に関連する内容となる。
注意すべきは,患者の個別性に応じて,必ずしもそのプロセス指標を満たすことがアウトカム指標の改善につながらない場合もあり得ることを理解し,個別に対応することが求められる点である。そこで,根拠に基づく医療evidence-based medicine(EBM)のスキルを活用すると,プロセス指標の根拠となっているエビデンスの内容を吟味し,アウトカム指標の改善に寄与する程度を確認して意思決定に活用したり,質指標では対応しきれない目の前の患者の個別性に対応するエビデンスを収集したり*4することができる。また,質指標が提示されていない疾患や病態に対しても,医療者が標準治療やEBMを実践することが医療の質向上につながることを認識し,それを追求することが求められる。
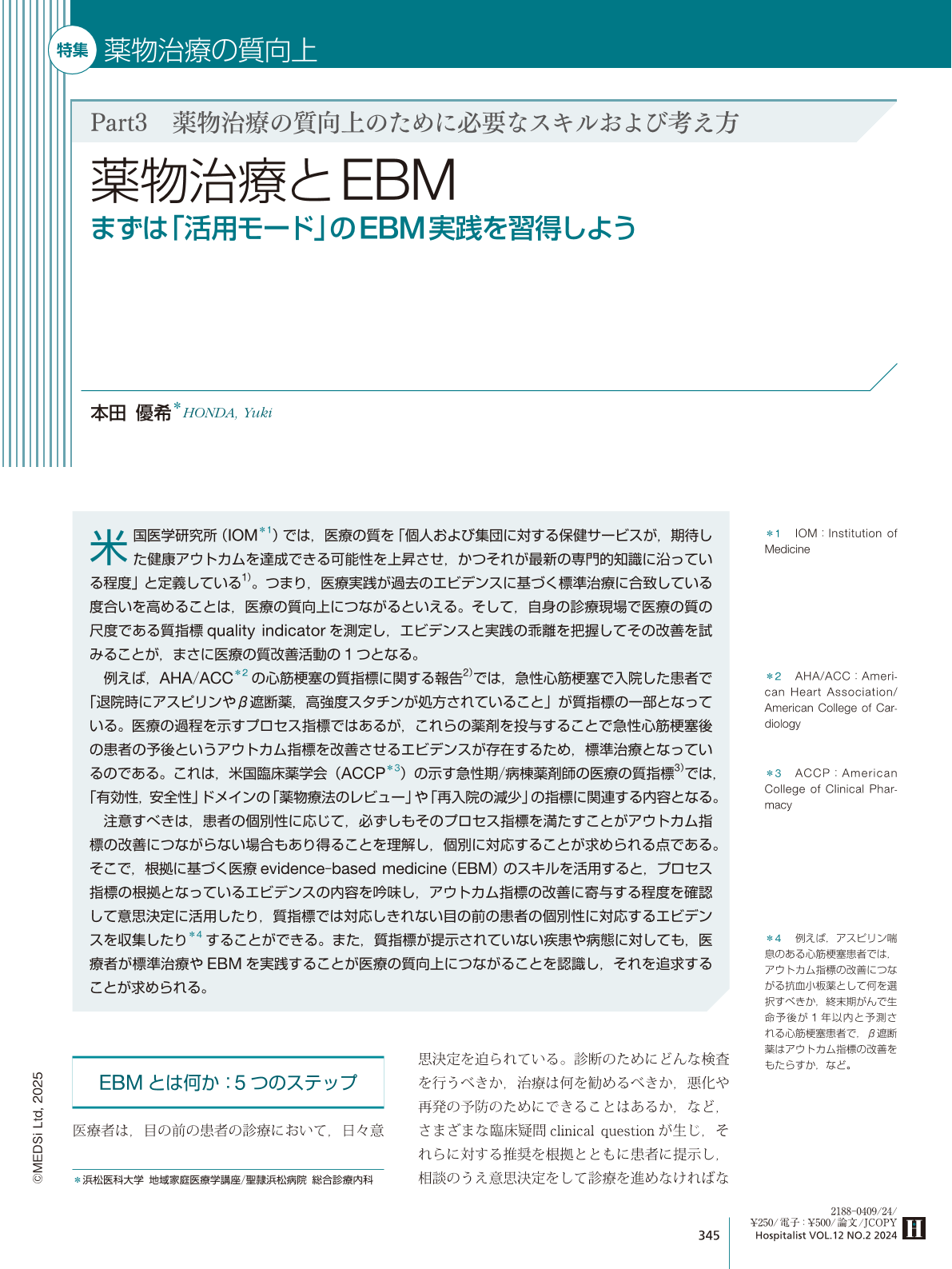
Copyright © 2025, MEDICAL SCIENCES INTERNATIONAL, LTD. All rights reserved.


