- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
東北大学教授 目黒謙一先生は,長年にわたり認知症医療の発展に貢献され,病気療養中の2023年秋に逝去された。目黒先生の偉大なご功績に深く敬意を表し,心から哀悼の意を表する。喪失感は大きく,いまだに時間が止まっているように感じている。
目黒先生に初めてお会いしたのは,1998年春,山鳥重教授の東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学講座の研究室であった。当時,目黒先生は助手をされており,私は大学院生だった。それから約25年半にわたり,目黒先生のご指導を受けながら研究・臨床・教育活動を行ってきた。
目黒先生は,2005年11月に東北大学大学院医学系研究科に設置された高齢者高次脳医学寄附講座教授に就任され,以来,18年近く研究室を統括された。2014年4月に同サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター(CYRIC)高齢者高次脳医学寄附研究部門教授,2019年4月に同未来科学技術共同研究センター(NICHe)高齢者高次脳医学研究プロジェクト教授を歴任された。「高齢者高次脳医学(Geriatric Behavioral Neurology)」は,目黒先生が考案された名称である。研究室の開設時からの目標は,「脳科学に基づく地域における認知症対策」であり,目黒先生はこの目標を実践されてきた。
目黒先生は,数多くの優れた研究業績を積み重ねてこられた。また著書も多く,論理的な文章の随所に,認知症の地域医療への情熱が感じられる1-8)。目黒先生は,宮城県大崎市田尻地区の保健医療福祉の統合型施設,スキップセンターで所長を務められ,認知症医療学の実践と認知症対策の組織改革についてのご経験を著書にまとめられた5)。また,東日本大震災の復興支援活動を行い,その活動を著書にまとめられた6)。また,大学院講義としてInternational Post-Graduate Program in Human Security(Health Resilience in Aging Society)をご担当され,講義内容を教科書として出版された7)。
目黒先生は国際的な研究活動も多く,フランス国立衛生医学研究所・CYCERON(PETセンター),ブラジル・サンパウロ大学医学部神経内科,米国・ワシントン大学アルツハイマー病研究センター神経内科に留学された。ブラジルでは,ブラジル在住の日本人移民高齢者を対象に医療協力調査として認知症調査を実施した4,9,10)。目黒先生は,臨床的認知症尺度(Clinical Dementia Rating:CDR)を開発したJohn C. Morrisワシントン大学教授と親交があり,CDRワークシートの日本語訳を作成する許可を得て,CDR解説の書籍を出版された1,3)(Fig. 1)。目黒先生は軽度認知障害(mild cognitive impairment:MCI)の概念について,地域調査では狭義の健忘型MCI11)に該当する高齢者は少ないことを指摘し,認知症の予後予測には健常と認知症の境界領域であるCDR 0.5の評価が有用であることを示唆された1,12)。
また,台湾やアジアの認知症研究グループと長年の親交があり,日本台湾認知症研究会を日本と台湾で定期的に開催し,共同研究やアジア認知症学会(Asian Society Against Dementia:ASAD)の活動を行い,台湾からの留学生の研究を指導された。コロナ禍の2021年11月に仙台で開催された第15回アジア認知症学会国際学術大会(The 15th International Congress of the Asian Society Against Dementia)では,目黒先生が大会長となり,高齢者高次脳医学の研究室が主催事務局となった8)。
本論では,「地域に根ざした認知症研究」をテーマに,地域調査による認知症対策,心理社会的介入の試み,認知症のQOLの新たな概念について,目黒先生の数多くの研究成果の中から,その一部を紹介する。
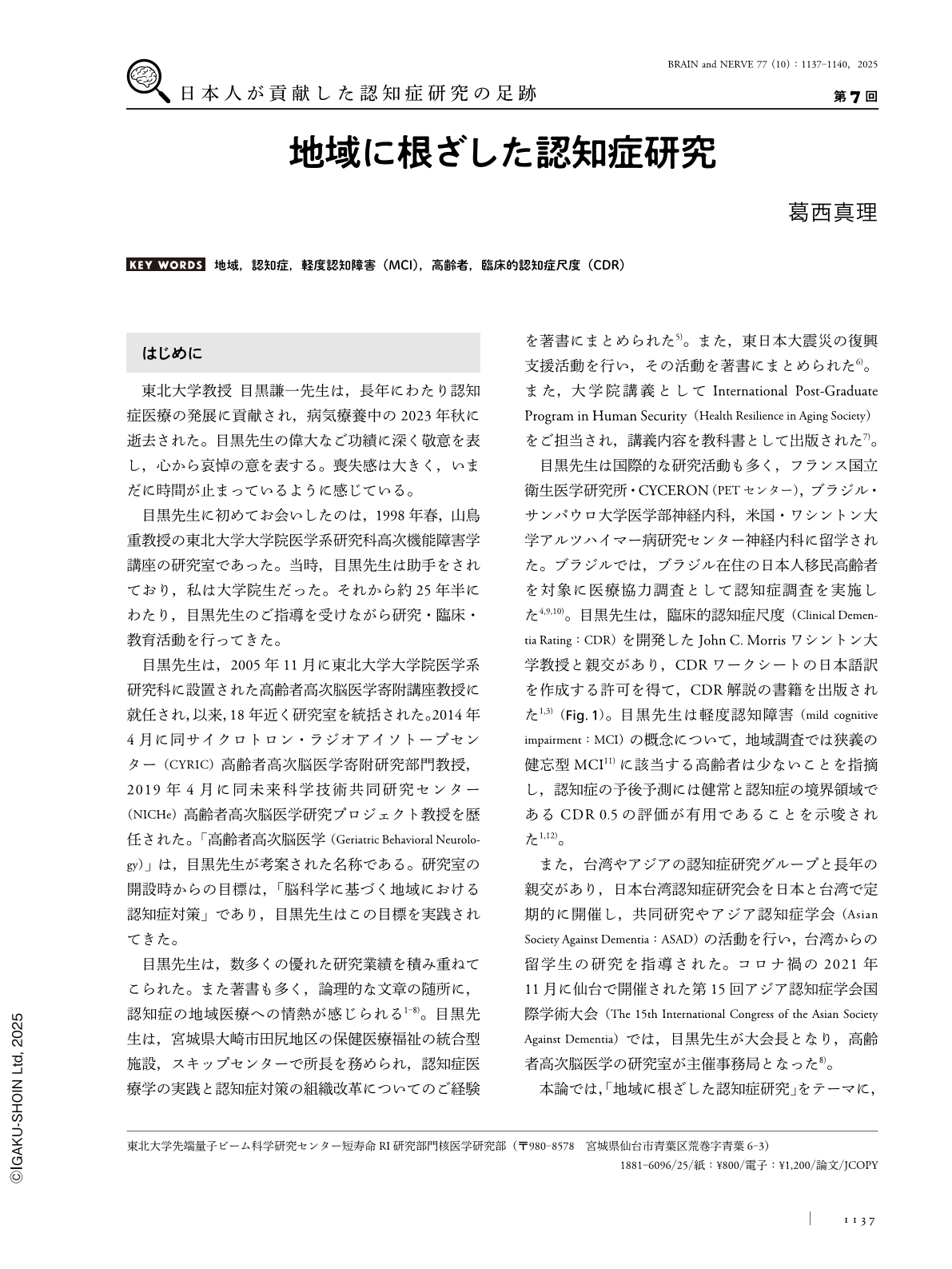
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


