研究
手術後患者の痛みの訴えと性格特性との相関についての一考察
小南 吉彦
1
1早稲田大学心理学教室
pp.366-385,389
発行日 1972年7月15日
Published Date 1972/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1681200301
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
Ⅰ 痛みの本態について
―その生体心情と自我感情―
1.はじめに
はじめに,日常のごくありふれたできごとから考えていってみよう。
戸外で元気よく駆けまわっていた子供が,石にけつまずいて転び,生爪をはがしてしまった。自分の方も転がるようにしてその場に駆けつけた親の脳裏に,一瞬ひらめいて走る想いは,「あっ,痛かったな」ということであり,その想いは,間髪を入れずそのままことばとなって口をついて出る。それは,このわが子が痛い想いをすることは,親のこころにとっても傷であって苦痛なのであるから,そうなるのである。まさにその子供の傷の痛みと同様に,あるいはそれ以上に親は痛んでいる。しかもそれは単に"心理的に痛い"とわれわれがよく言うところの,ことばの上の比喩ではなくて,文字どおり生理的な痛みが親の肉体の中をつき走っている。つまり,親の足の指先の筋をめぐる血管は強く収縮し,その収縮痛が現にそこで起っているのである。このような形で,痛みというものは他人に≪伝わる≫ものであって,病人の苦痛をとりまく人間関係は,この痛みの伝達をその基盤として展開されている。それを無視しては,痛んでいる病人に対する医療も援助も,あるいは看護もケアーも共感もありえないのではないだろうか。
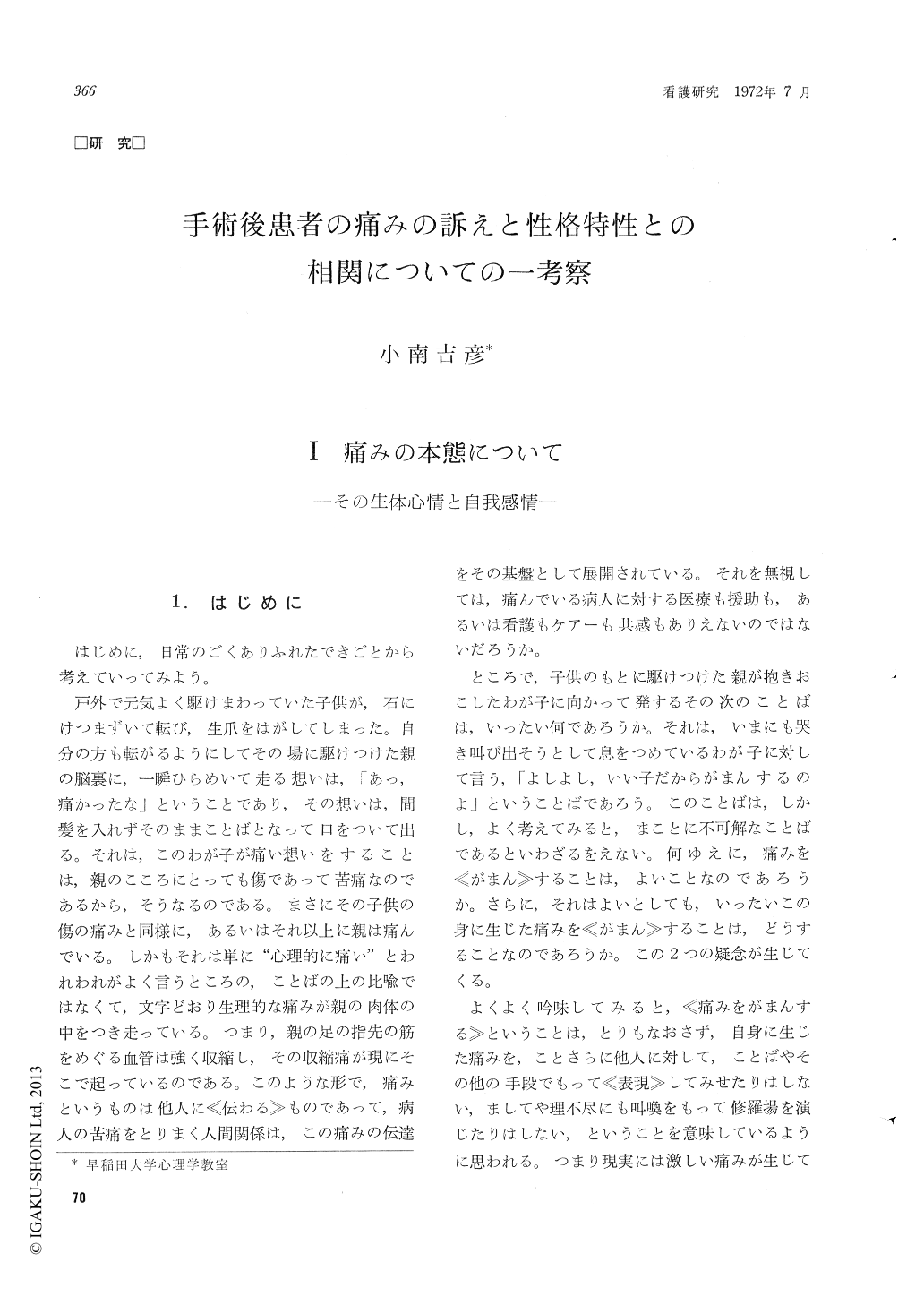
Copyright © 1972, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


