特別寄稿
医療機関内での助産婦産科の試み
品川 信良
1
,
桜庭 広次
1
,
石上 博
1
1弘前大学医学部産科婦人科学教室
pp.638-643
発行日 1978年10月25日
Published Date 1978/10/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611205443
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
「一歩誤まれば,死につながりかねないような医療関係の行為は,然るべき設備や人手のあるところで行なわれることが望ましい」数世紀にわたる経験と,いたましい数々の犠牲の結果,先進的な国々の人々は,こう固く考えるようになった。その結果,外科的な手術などが自宅や野外で行なわれることは,いまでは原則としてあり得ない。この考え方は分娩に対しても,大幅にとりいれられた。そして,自宅分娩というものが,大幅に減少しつつあることは,周知のごとくである。しかし,だからといって,"自宅分娩"が,全然ゼロになったのかというと,そうでもない(殊に世界的にみるならば,全分娩の過半数を占めているものは,依然として"自宅分娩"である,と推定されている。またアメリカやイギリスには,新しい視角から,自宅分娩を見直しているものも少なくない)。
自宅分娩を少なくしようという運動は,同時に,"産科医が大幅にタッチする分娩様式"というものを生みだしていった。その頂点に立った国がアメリカであることも,周知のところであろう。多くの西欧諸国や日本が,自宅分娩を減少はさせながらも,助産婦の役割というものを,どこかに残そうと努力してきたのに対し,アメリカは長い間,助産婦の役割を,積極的には認めようとしなかった。
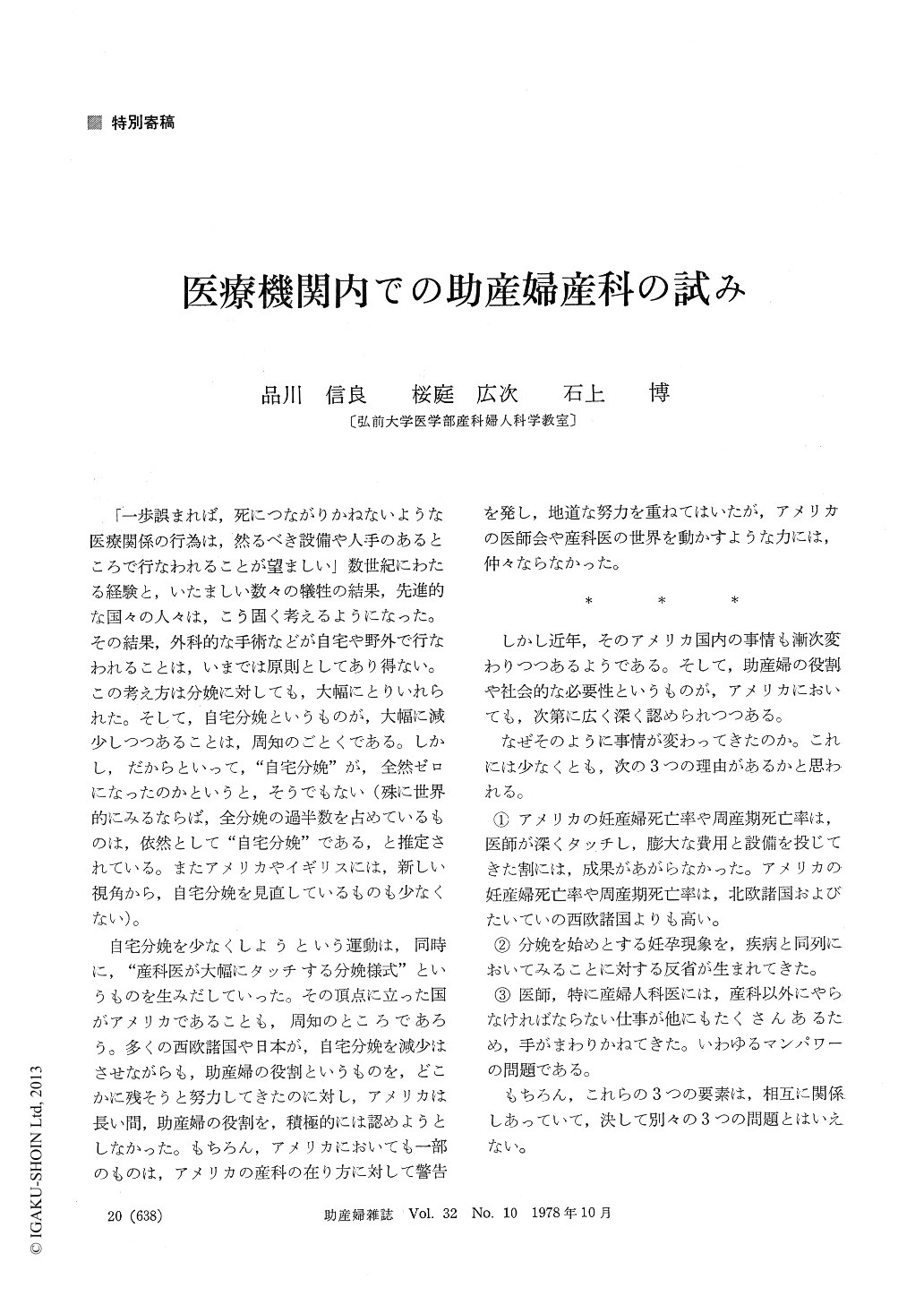
Copyright © 1978, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


