シリーズ・先天性遺伝性疾患の診断に役だつ検査・12
出生前診断
大和田 操
1
Misao OWADA
1
1日本大学医学部小児科学教室
pp.1805-1811
発行日 1985年12月15日
Published Date 1985/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542912835
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
治療法がなく,予後不良な遺伝性疾患や染色体異常症である可能性の高い妊娠の場合に,胎児が異常か否かを出生前に診断し,その発生を予防する試みは,すでに1950年代に始まった1).初期には,主として伴性遺伝性の予後不良な疾患のハイリスク妊娠に際して羊水穿刺を行い,得られた細胞の性クロマチンを検査して性別を判定することにより行われていたが,その後,細胞培養の技術の進歩に伴い,採取した羊水細胞を培養して染色体分析が行われるようになった.また,同時期に,Nadler2)は,培養羊水細胞の酵素活性を測定することにより,先天性代謝異常症(以下代謝異常症と略す)の出生前診断が可能なことを初めて報告した.その後,今日に至るまでの十数年の間に約30種に及ぶ代謝異常症について羊水診断が試みられてきた.
もちろん,西欧でも,わが国でも,出生前診断が行われた絶対数の90%以上は染色体異常症のハイリスク妊娠におけるものであり,代謝異常症に関するものは数%にすぎないが,予後不良で,現時点では治療が不可能な疾患の発生を予防する役割を担っている.現在行われている代謝異常症の出生前診断に用いられている方法は,細胞培養も含めて必ずしも容易ではなく,日常一般検査として取り上げることは難しいが,その概略について述べてみたい.なお,遺伝性疾患の出生前診断については優れた教科書があるのでそれらを参照されたい3,4).
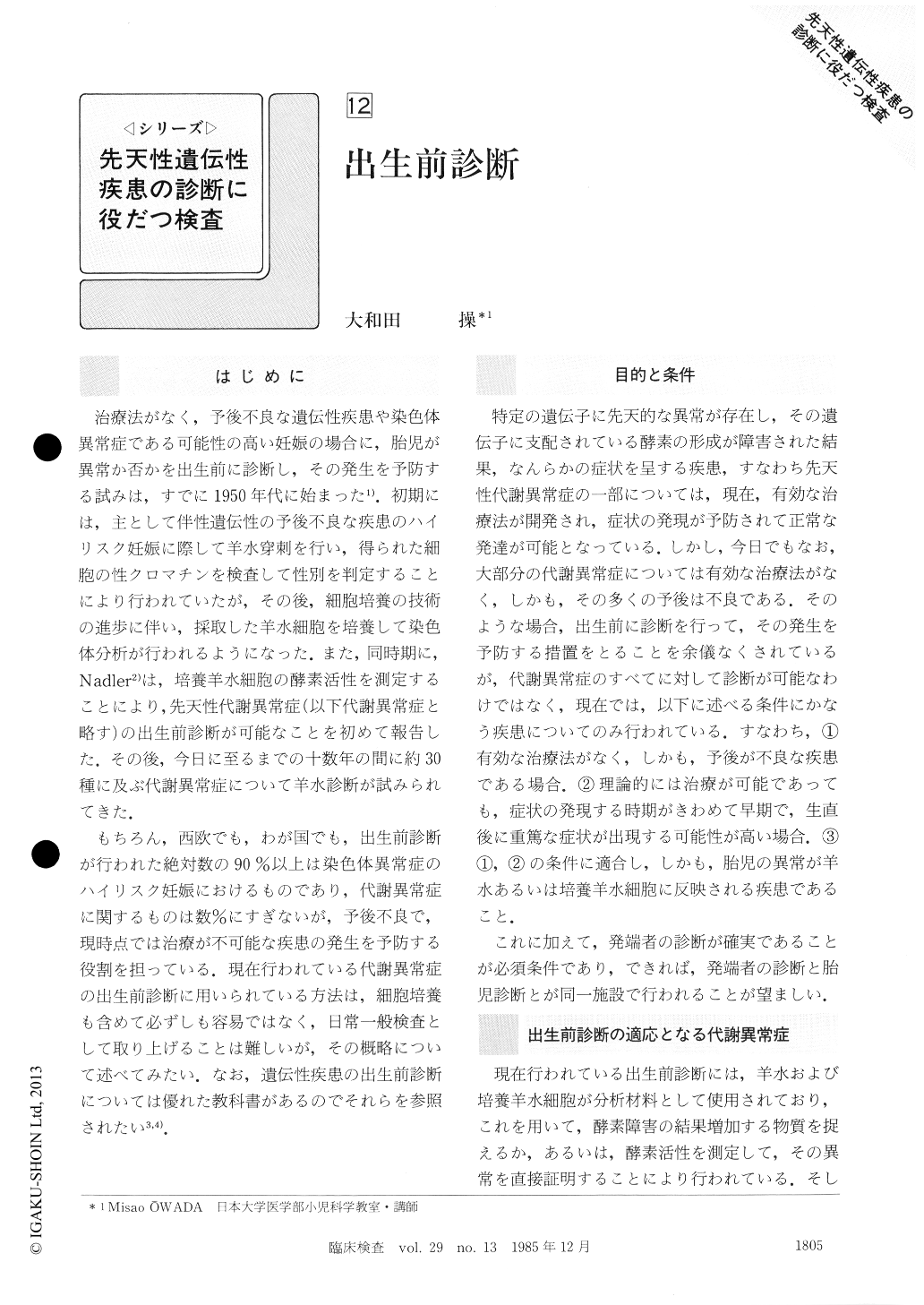
Copyright © 1985, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


