明日への展開--ヒューマンバイオロジーの視点から 遺伝
染色体と染色体異常
前田 徹
1
Tohru Maeda
1
1北里大学医学部産婦人科学教室
pp.759-763
発行日 1984年10月10日
Published Date 1984/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409207064
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
染色体は遺伝子の担い手であり,あらゆる遺伝情報が特殊な暗号で記されたマイクロフィルムのようなものと考えてよい。ヒトの遺伝子の数はおよそ3万,あるいはそれ以上と推定されており,1個の体細胞に含まれる全長2mにも達するDNAの鎖の上に存在する。染色体の基本的構成成分であるDNAは,デオキシリボースとリン酸とが交互に連なった2本の柱と,その間を結ぶ4種の塩基(アデニン,チミン,グアニン,シトシン)とから成る二重ラセン構造を形成することは,ワトソン・クリックのモデルとして有名である。それぞれの塩基は特定の相手としか結合しないという性質があり,これはDNAの自己複製,あるいはRNAによる遺伝情報の転写や蛋白質の合成のときに非常に好都合な性質である。染色体が遺伝に重大なかかわりを持つことはいうまでもないが,染色体に関する知見の増大や,臨床医学における有用性が認識されるようになったのは比較的最近のことである。1950年代後半から1960年代にかけてはヒトの体細胞に含まれる染色体数の決定や,その形態の観察が可能となり,古典的染色体異常症候群がいくつか発見されている。1970年代に入ると新しく開発された分染法の応用による新しい知見が相次いでいる。これらの進歩は染色体分析技術の改良に負うところが多い。最近では染色体分析は臨床検査の一部として産婦人科領域でも日常診療のなかに定着しつつある。本稿では染色体に関する基本的な知見を一般臨床に必要と思われる範囲内で解説する。
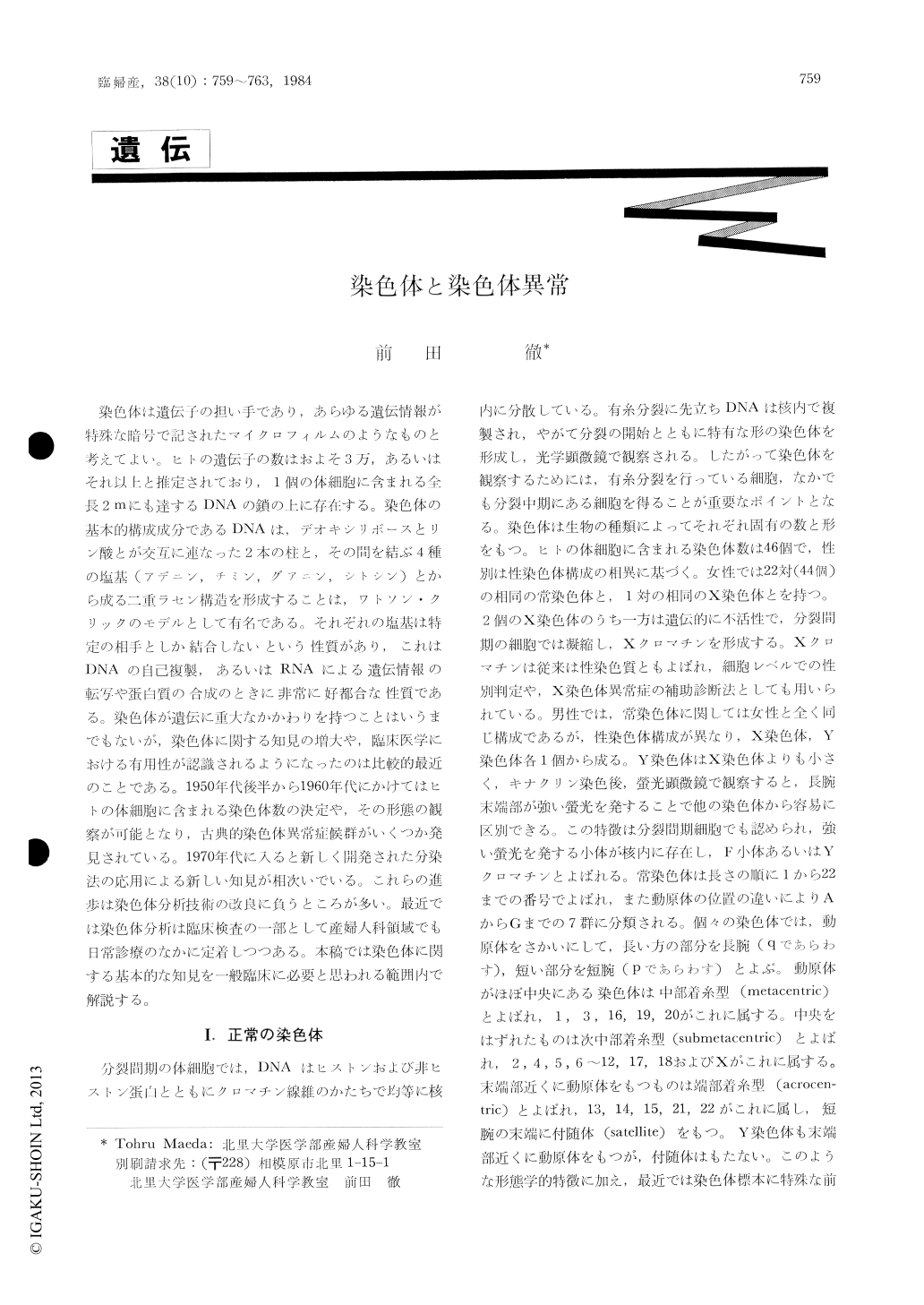
Copyright © 1984, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


