- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
子宮の生理的位置(形態)は周知のごとく浮遊性前傾前屈であり,直腸膀胱など子宮周囲臓器の状況,腹腔内圧,体位などにより変化するが,これらの動機が消退するともとに戻る。したがつて診察直前に排尿させるなど,子宮変位を起こす動機を少なくした状態で診断すべきであり,かつ数日おきに反復診察して後転が持続的であることを確かめるべきである。かくして後転が一時的でなく,病的な状態であることがわかつても,それによると思われる特別の苦痛を訴えていない場合には,子宮が移動性であればもちろん,癒着性であつてもしいて直ちに処置する必要はない。また苦痛がなければ患者が治療することを納得しがたいので,実際に治療の対象になるのは自覚症状の伴うものに限られる。その場合,治療はまず対症的なものを試みるのが常道である。特に本症と併存することが多いparametritis posterior (Schultze),後子宮旁結合織内瘢痕(伴)が直腸診で認められるときには,理化学的療法をまず試みて自覚症状の消長をみる。これは手術の必要度,手術効果の推測,術式の選定工夫などに役立つ。parametritisposteriorのときには,仙骨子宮靱帯から基靱帯にわたつて触れる索状体が,硬く弾力性がなく,側上方に圧上すると主訴と同様の腰痛を訴える。この種の腰痛は,子宮位置矯正術だけでは消退ないし軽減せず,むしろ増悪することさえある。よつて,かかるときは子宮の位置を矯正するとともに,腟式ないし腹式に後子宮旁結合織内の索状瘢痕を切断することが必要である。
また手術するに先立つて後転子宮の用手整復を試みることは,手術法の選定その他に欠くことができない。用手整復ができるかどうかは,1回の診察で直ちに判断できないことがある。特に肥満患者では日を改めて数回試みるべきである。内手(著者は通常左示指のみである)と外手(子宮底に向けてあてるだけで,直接子宮底にあてることはたいていできない)との間で子宮を動かしてみて,移動性が多少でもあれば用手整復を試みる。内手の補助のもとに子宮底を外手の指頭で掬うことは,多くの場合にできない。よつて本症の場合,強く前方(恥骨結合下)に偏在する子宮腟部を内手で後力に圧迫し,同時にそれを助けるように外手で子宮底を起こす気持で圧迫する。このとき真正面から子宮を起立させようとするよりも,内外手で子宮腟部と子宮体を互いに反対側方に圧迫しながら,子宮を側方から回転起立させるような気持で行なつた方が成功しやすい。これが成功しないときは,内手の1指を2指(示,中指)にし,その間に子宮腟部をはさんで強く側後方に圧迫して子宮の回転起立を促す。この方法では,どちらかといえば内手が外手よりも大きな役目を果たすので,腹壁が脂肪で肥厚し,外手の指頭が十分深く子宮体に接近させられぬときに,特に試みる価値がある。用手整復ができたら,そのために疼痛などの苦痛が起こらぬかに注意する。ときにはペッサリウム挿入などで1〜2日間正常状態を保持させて苦痛の有無を調べることが,手術法の選定などに必要である。
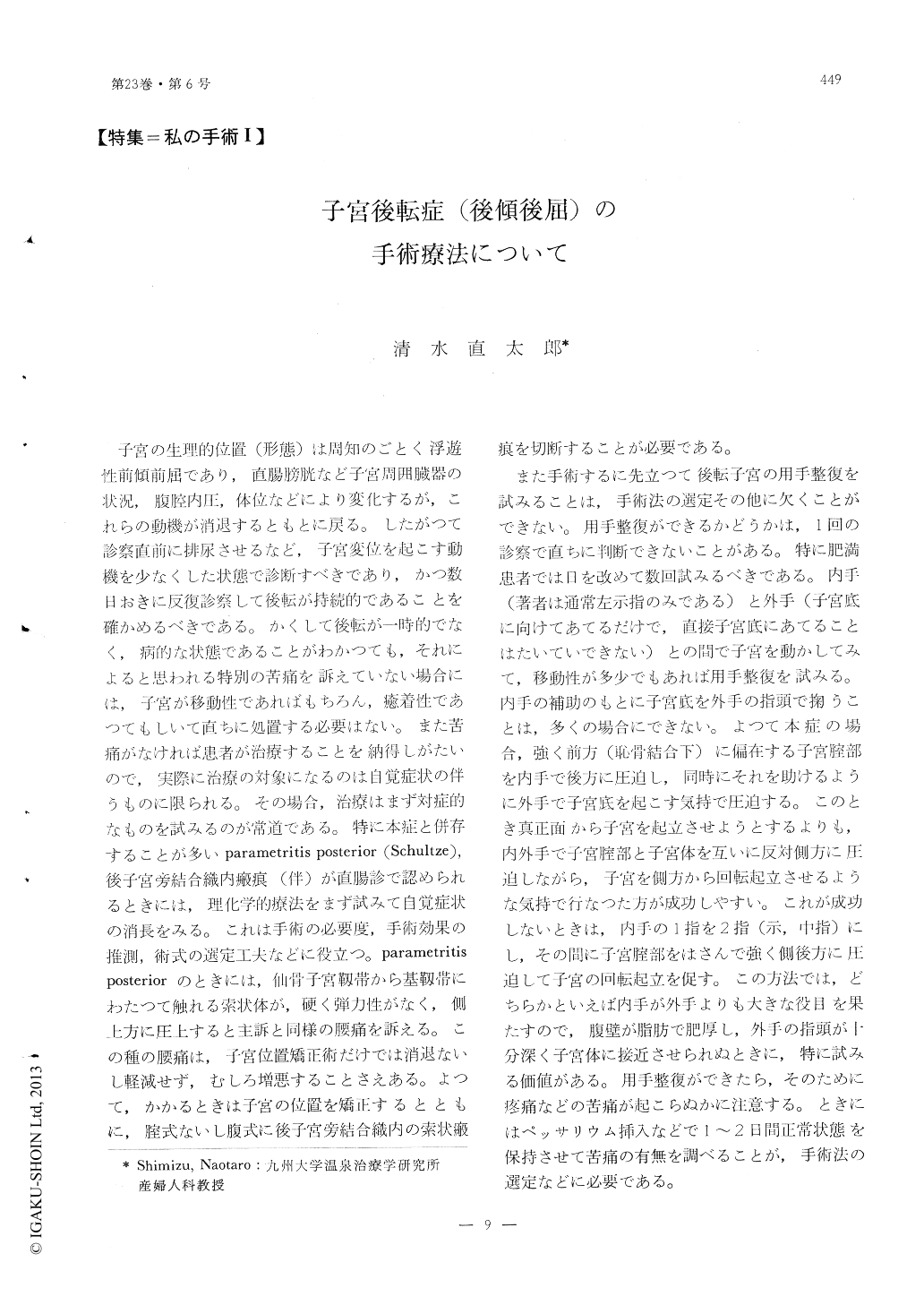
Copyright © 1969, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


