- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
妊娠中毒症時の胎児死亡ないしは発育障害に対する子宮胎盤の役割を論ずるに先立つて,正常妊娠時に胎児に対する物質輸送の媒体となる子宮胎盤血行(胎盤の母体側血行)について少し述べたい。
絨毛間腔の構造と血行については,従来,形態学的に研究されたSpannerの説が有力であつた。すなわち,子宮筋層から進入する子宮胎盤動脈はラセン状になつて脱落膜(基底板)に入つて絨毛間腔に開口し,そこから絨毛間腔に入つた母体動脈血は絨毛の間を上昇し,絨毛膜板下に至り,胎盤中隔と絨毛膜板との問の間隙を越えて胎盤の辺縁部をとりまく絨毛の少ない空隙部—周縁洞(randsinus, marginal sinus)に集まり,そこから子宮胎盤静脈となつて母体大循環に去つて行く,と説明され,胎盤の母体側血行は胎盤全体として1個の血行単位をなすと考えられた。しかしヒトやサルについてin situにおけるレ線生理学的な研究の進歩によつてSpannerの説は修正されるようになり,現在ではおよそ次のように考えられている。すなわち,絨毛間腔に開口するラセン動脈は口径約1mmで総計150〜200個に達し,動脈開口からは約80mmHgの圧力で母体動脈血が噴流(jet)をなして流入し(Borell's jetと呼ばれる),絨毛の間を勢いよく上昇した動脈血は絨毛膜板から反転して絨毛の間をゆつくり下降し,約8mmHgの圧となつて基底板に開口する子宮胎盤静脈に入つて去つて行く。この際,中隔を越えて他区画の絨毛間腔に流入する血液はほとんどなく,胎盤中隔によつて区切られるひとつひとつの絨毛間腔は独立した血行単位を形成することになる。このことは,胎盤梗塞が何故に限局性にあらわれるかという疑問に説明を与えるものであり,また梗塞が起こつても原則として他区画の胎盤単位(placentom)には進展せず,胎盤の機能は全体として大きな影響を受けないということになる。また絨毛間腔の母体側血流方向は絨毛内の胎児側血流と常に反対方向をとることになるので,一種の向流現象(counter flow)を形成し,母児間物質交換は能率よく行なわれることになる。非常に興味あることは,レ線造影によつて見られる各胎盤単位の出現のしかたであつて,決して全部が同時に出現するのではなく,at randomにそちこちと出没することである。これは多分ラセン動脈への血液流入が血管運動の差によつてまちまちなためによるのだと考えられる。そしてまた,子宮胎盤血流量は血管収縮性昇圧剤に敏感に反応,減少することが知られており(いわゆるネオシネジン・テスト),これらのことは妊娠中毒症における胎盤血行動態の変化およびそれに伴う胎盤自体の変化の発生機転を考える際に大きな暗示を与えるものである。このほかに子宮胎盤血行は子宮の収縮にも強い影響を受けることが知られている。なお,諸文献の実験成績を総合すれば母体側胎盤血流量は毎分600ml,絨毛間腔圧は子宮の非収縮時に10〜20mmHg,収縮時に60〜80mmHg,子宮静脈圧8mmHgとされる。
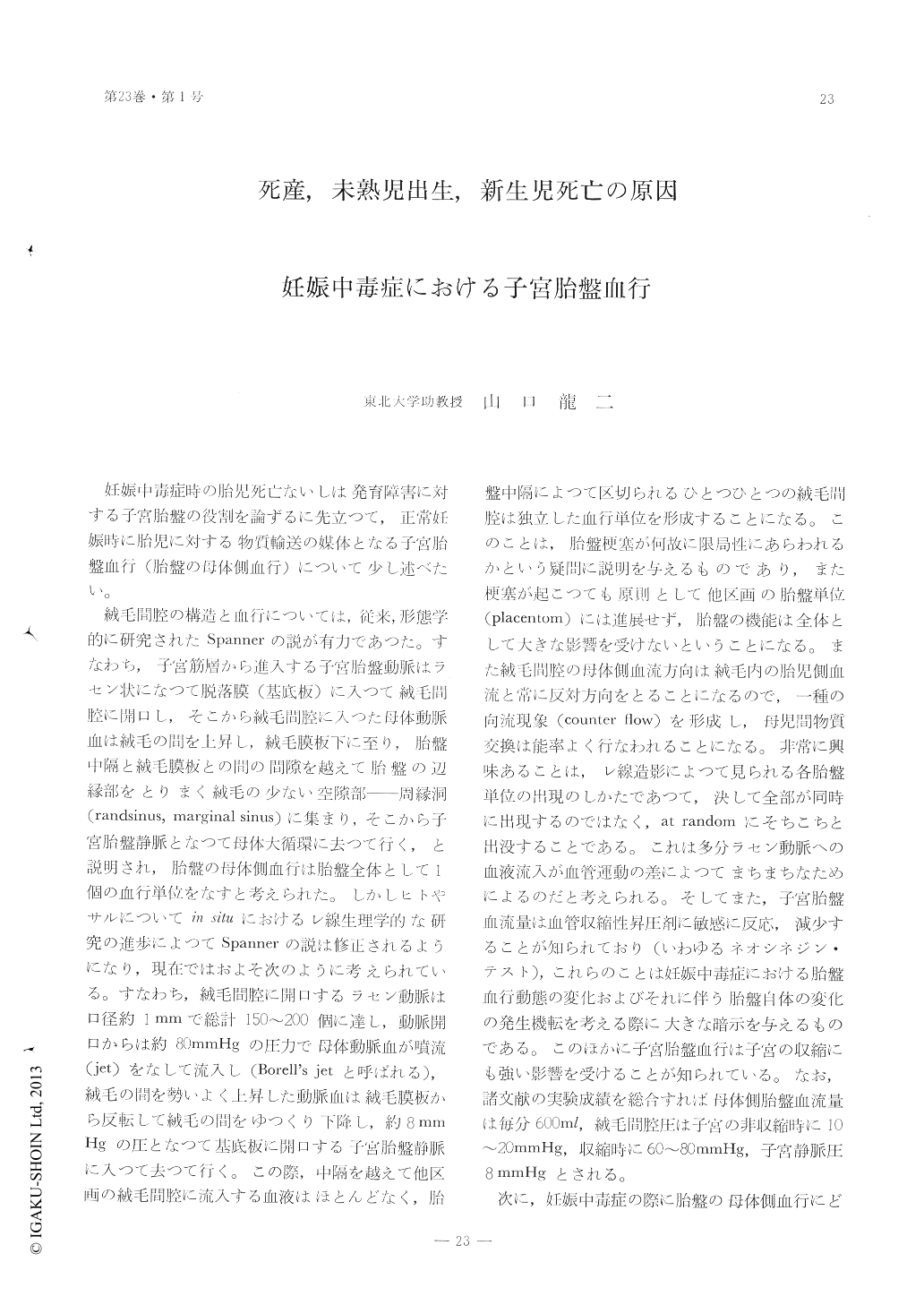
Copyright © 1969, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


