今月の臨床 不育症診療─その理論と実践
不育症外来における検査の手順
三木 明徳
1
,
石原 理
1
1埼玉医科大学附属病院産婦人科
pp.1102-1105
発行日 2004年9月10日
Published Date 2004/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409100596
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
全妊娠の10~15%は自然流産に終わる1).一昔前のように女性が一生涯に出産する児の数が10人近くあった時代には,流産は誰でもが経験するありふれた現象であった.しかし現代日本において女性が一生涯に出産する児の数は2人を割り込んでおり,流産を経験することなく全出産を終了する女性が多い.さらに昭和30~40年代までは妊娠6週以前を確実に診断する方法がなかったため,初期流産は月経が数週間遅れただけと認識されていた.しかし,妊娠検査薬の改良とその一般市販化により誰でも初期のうちに妊娠の診断をすることができるようになった.月経が予定日より1日遅れただけでも市販の妊娠検査薬で陽性と出れば妊娠と判断される.そして産婦人科を受診し子宮内に胎胞(GS)が認められるが,GSの成長がみられない場合は流産と診断されるわけである.このように,検査方法が進歩したため流産と診断される女性の数は増加した.
一方,流産に関する情報は核家族化の進行のためにさらに減少している.また,ほかに流産を経験した女性を身近に探しても流産経験を語る女性は少なく,無事に赤ちゃんが生まれたという話のみが耳に入ってくる.きまじめな女性であるほど妊娠のごく早期に何か胎児に悪いことをしたのではないかと気にかかり,流産したことを自分の責任だと思い悩む.お腹のなかの胎児を喪失したという虚脱感はきわめて大きなものであり,一度の流産でも悩み,落ち込み,相談に来る女性も多い.二度,三度と続くとなおさらである.習慣流産外来の存在意義は,まず第一に,このような女性に流産に関する正しい情報を与え,不安を取り除くことにある.
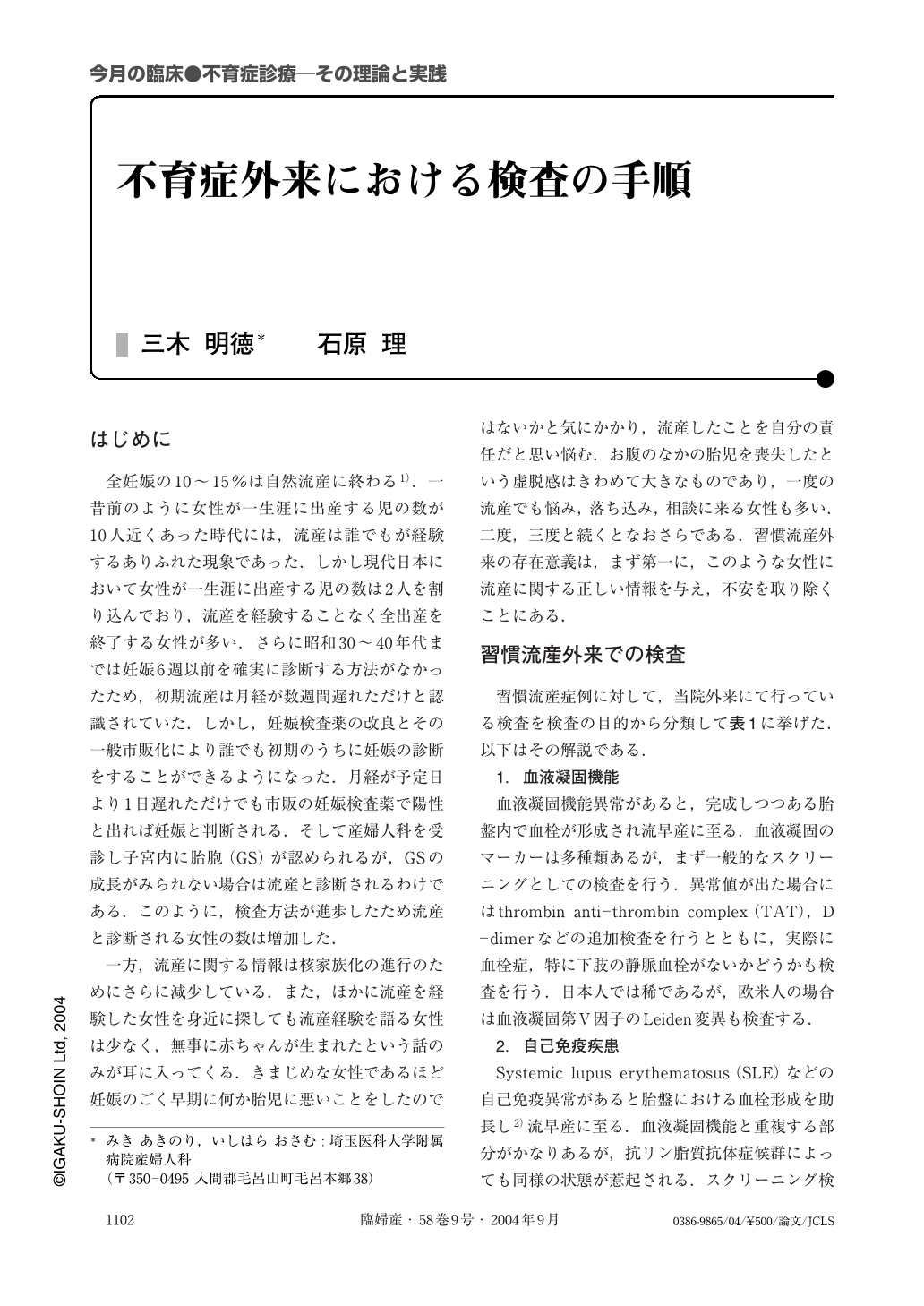
Copyright © 2004, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


