特集 光と精神医学
特集にあたって
内山 真
1
1日本大学医学部精神医学系
pp.871
発行日 2019年8月15日
Published Date 2019/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405205875
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
日長時間が短縮する冬季になると抑うつ状態を呈する季節性うつ病が同定され,この治療として高照度光療法の有効性が報告されてからおよそ40年になる。その後,季節性うつ病に関しては,疫学的なエビデンスや高照度光療法の有効性について研究が行われてきた。さらに,非季節性うつ病に対する高照度光療法の有効性,双極性障害に対する光制限の有効性など,光が広く気分障害の治療に応用可能であることが分かってきた。しかし,光を応用した治療技術については,その生物学的な根拠が明確でなかったことや朝早い時刻の実施がうつ病患者では困難であることなどから,実地臨床における気分障害の非薬物療法としての位置が確立されてこなかった。
高照度光療法における抗うつ効果の作用機序については,既に神経連絡が明らかになっていた睡眠や概日リズムに対する影響を介した作用と考えられてきたが,臨床研究が進むにつれ気分に対する光の直接的な作用を想定しないと説明困難な現象が報告されるようになった。さらに,ヒトを用いた基礎的および臨床的研究から,不安や認知機能に対する影響についても明らかになってきた。2010年以降になって,動物において,網膜の最表層にある光感受性網膜神経節細胞(intrinsically photosensitive retinal ganglion cell:ipRGC)から直接に海馬や扁桃体に投射する経路が発見された。あらためて光の抗うつ効果や認知機能に対する効果について再評価が行われるようになってきた。
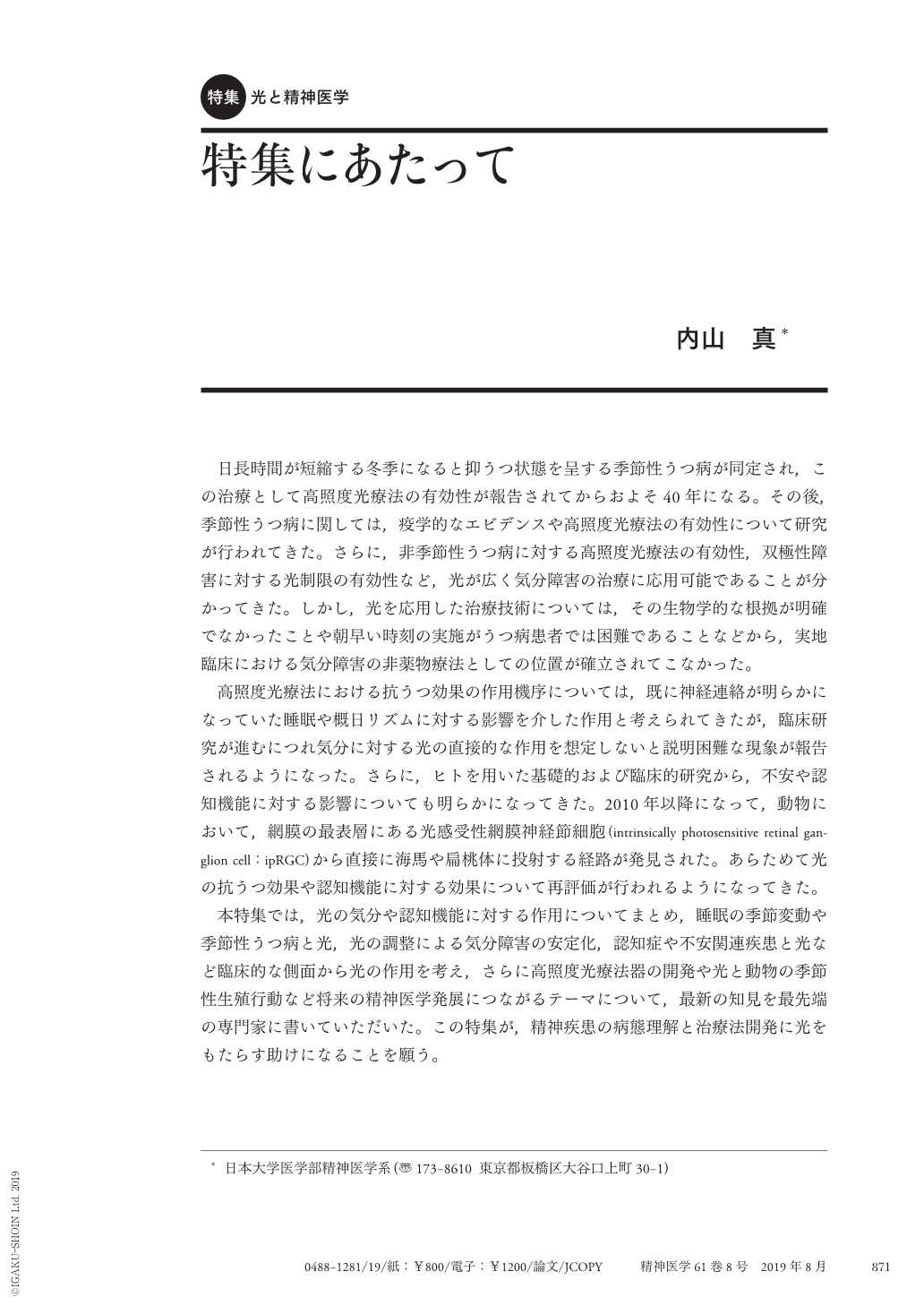
Copyright © 2019, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


