Japanese
English
特集 聴覚失認
小児の聴覚失認の問題点
Controversy on Auditory Agnosia of Children
加我 君孝
1
,
田中 美郷
1
Kimitaka Kaga
1
,
Yoshisato Tanaka
1
1帝京大学医学部耳鼻咽喉科学教室
1Dept. of Otorhinolaryngology, Teikyo Univ. School of Medicine
pp.407-411
発行日 1983年4月15日
Published Date 1983/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405203572
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.はじめに
小児の聴覚失認は,患者が発育途上にあるために成人の場合とは異なり,詳細な神経心理テストの協力が得られないことが多く,診断の難しいことが大きな特徴である。診断が確定すると,次には,どんなコミュニケーション手段を習得させるか,教育の方法の難しさに遭遇する。聴覚的・視覚的あるいは触覚的なコミュニケーションの手段のいずれを選択するにしろ,内言語を習得するための,critical age以前に,先天性あるいは後天性難聴児と同様に,早期発見,早期言語教育が必要となる。
幼小児では,先天性あるいは発達性と後天性の2つのタイプに,従来の報告を分けることができる。前者は1930年のWorster-Drought and Allen25)による"congenital auditory imperception"以後,報告が多く2,3,8〜11,13,24,26),本邦でも1960年代より報告があるが15,17〜22,27),田中らの指摘するように,末梢性感音難聴を誤って聴覚失認語聾としている場合が少なくない7,14)。これは外国の報告でも同様である。一方,後天的聴覚失認や感覚性失語症の研究は1957年のLandauの報告8)以来,少なくないが,従来,小児失語症として報告された症例の中には失語というよりも聴覚失認と見なすほうが適当と思われるものも少なくない。
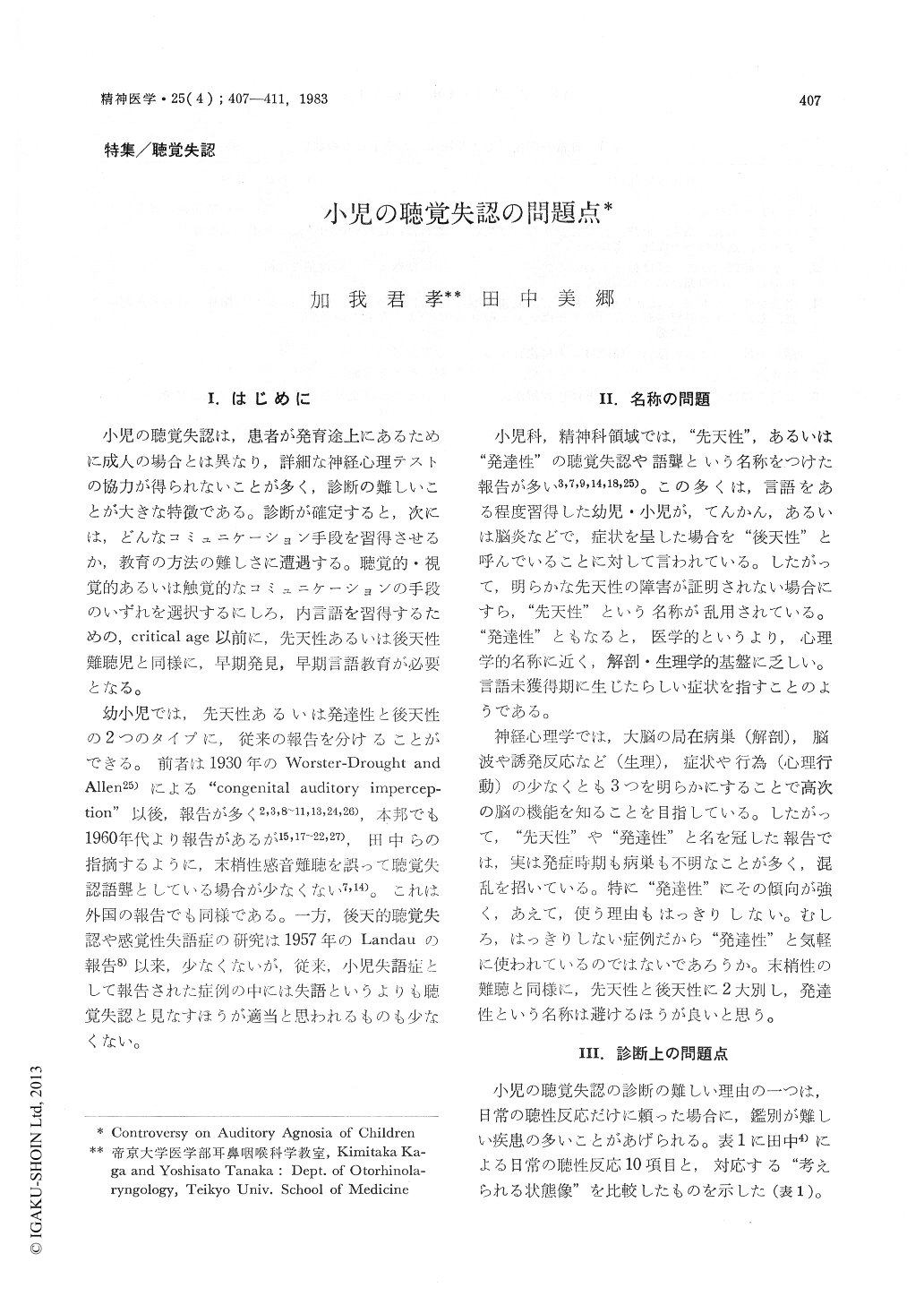
Copyright © 1983, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


