Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.はじめに
向精神薬,ことに中枢神経遮断剤といわれる抗精神病薬が登場して以来,精神医学の今日の中心課題である精神分裂病についての研究は大きく飛躍し,新しい学問を発展させた。その精神薬理学は生化学の研究とあいまって,Carlsson, A. ら2)やSnyder, S. H. ら28,29)により,フェノチアジン系薬物が脳内のドーパミン受容器を遮断し,抗分裂病効果をもたらすという今日ではほぼ認められた事実を明らかにした。こうして,精神分裂病のドーパミン仮説が研究検討されているのである。その他の神経伝達物質についても精力的に研究がなされていることは周知のとおりである33)。
他方,臨床面ではPeterson, D. B. 19)(1964)が退院は早くなったが再入院率もまた高くなったことを報告していることからも,こうした薬物が急性期精神病状態に対する効果を持つことは認められる一方,精神分裂病そのものを治癒するものではないことが示唆された。May, P. R. A. 35)(1971)は明確に「薬物は治癒をもたらさない」と述べている。また,Goldberg, S. C. 10)(1972)は急性分裂病状態の患者に対し,フェノチアジン薬剤の効果を予測する因子を研究したが,失敗に終わっている。一般に向精神薬に対する反応性に極あて個体差が大きいことが認められており,西園14,16,17)は非薬因子の重要性を指摘した。その中でも患者のパーソナリティの違いによる反応性を重視している。
この点について,Curry, S. H. 3)に始まる血中濃度の測定から臨床効果を予測し,投与量を決定しようとする研究も盛んになっている。高橋31)は,最近では,代謝産物の多いクロールプロマジンから,ブチロフェノンの血中濃度測定に関心を向け,向精神薬療法をより科学的なものにしようとしている。しかし,現在のところ,血中濃度自体も同一投与量に対する個体差が大きく臨床効果との相関を明確にはなしえていない。われわれの研究21)では,血中濃度とパーソナリティ傾向との間の相関が,個々の症状との相関よりも強いことが示唆された。
このように,向精神薬は精神医学全体に強烈な変革をもたらしたのであるが,これが真に精神分裂病の理解や治療を進展させるために,もうひとつ不可欠の研究があるのである。それはいうまでもなく,精神分裂病者の臨床的観察である。精神薬理学の精神分裂病の理解にしても,急性期と慢性期というような病相のちがいによって神経伝達機構の異常にもちがいがあることは当然考えられるところであろう。また,急性期のすべての症状がドーパミン仮説のみで説明しえないし,大月18)の述べるように,いくつかの神経伝達物質の関与が仮定されるのである。また,血中濃度と臨床効果を対比する際にも,従来のように精神医学的な症状や適応レベルを指標とすること自体に無理がある可能性もあるであろう。
このように考えてくると,元来,精神分裂病という診断そのものが,目でみて量的に測定されるという科学的な診断基準に基づくものではないのである。この精神医学の宿命ともいうべき疾病概念の曖昧さのために,治癒の程度を測る尺度も定まらないといってよいであろう。
たしかに,精神医学的な諸症状,つまり不安,強迫,躁うつ的気分の変動や状況によっては幻覚の体験すらいわゆる健常者にもあるのである。では,社会適応の側面から測定しようとしても,健康と不健康の区別はやはり不明瞭なのである。仕事中毒というコトバもあるように,いくら社会的な成功をおさめているかにみえる人でも,それだけでは健康とはいいがたいであろう。1例をあげれば,社会的に有能であった人が老後にうつ病に陥るかもしれないのである。このことは,精神分裂病者が一時的に症状もなく回復したかにみえていても,再発を繰り返すという現実を思い出させるのである。いいかえれば,今日の精神医学は精神分裂病といわれる現象をまだまだ表現しきれていないのである。臺32)はこうした現実をふまえて履歴現象と機能的切断症状群という分裂病の生物学的理解を述べている。
このことは,種々の治療手段を用いて精神分裂病者を治療へと導びこうとする際,われわれ精神科医が日常自問していることと思うのである。しかし,何を正常と考え,病者の何が病理性の本態と考えるかは,暗黙裡に了解し合ってはならないと思うのである。
そこで筆者は,精神分裂病者との対人関係すなわち,「かかわり合い」という側面から精神分裂病者の病理を理解する試みをしてみたい。心理的にちぢこまった状態の分裂病者は,何事にも口が出せないし,手が出せない。幻覚,妄想の中にいる慢性の病者はかかわり合いという点では,両手が切断されているにも等しい。あるいは,一方通行のかかわりでしかない。相互にやりとりができるような両手でしっかりと手をとり合った関係とは異なるのである。この「かかわり合い」の様相をみることが,病理性の深さ,再発への抵抗力,治療の進展の具合,薬物をはじめとするその時々に必要な治療手段の選択,医師のとるべき態度などを決定する指標となると思うのである。そのためと,筆者の非力もあって,薬物療法が現実に筆者の診療を支えてくれているにも拘らず,そのこと自体に充分な論及ができないことをお許し願いたい。
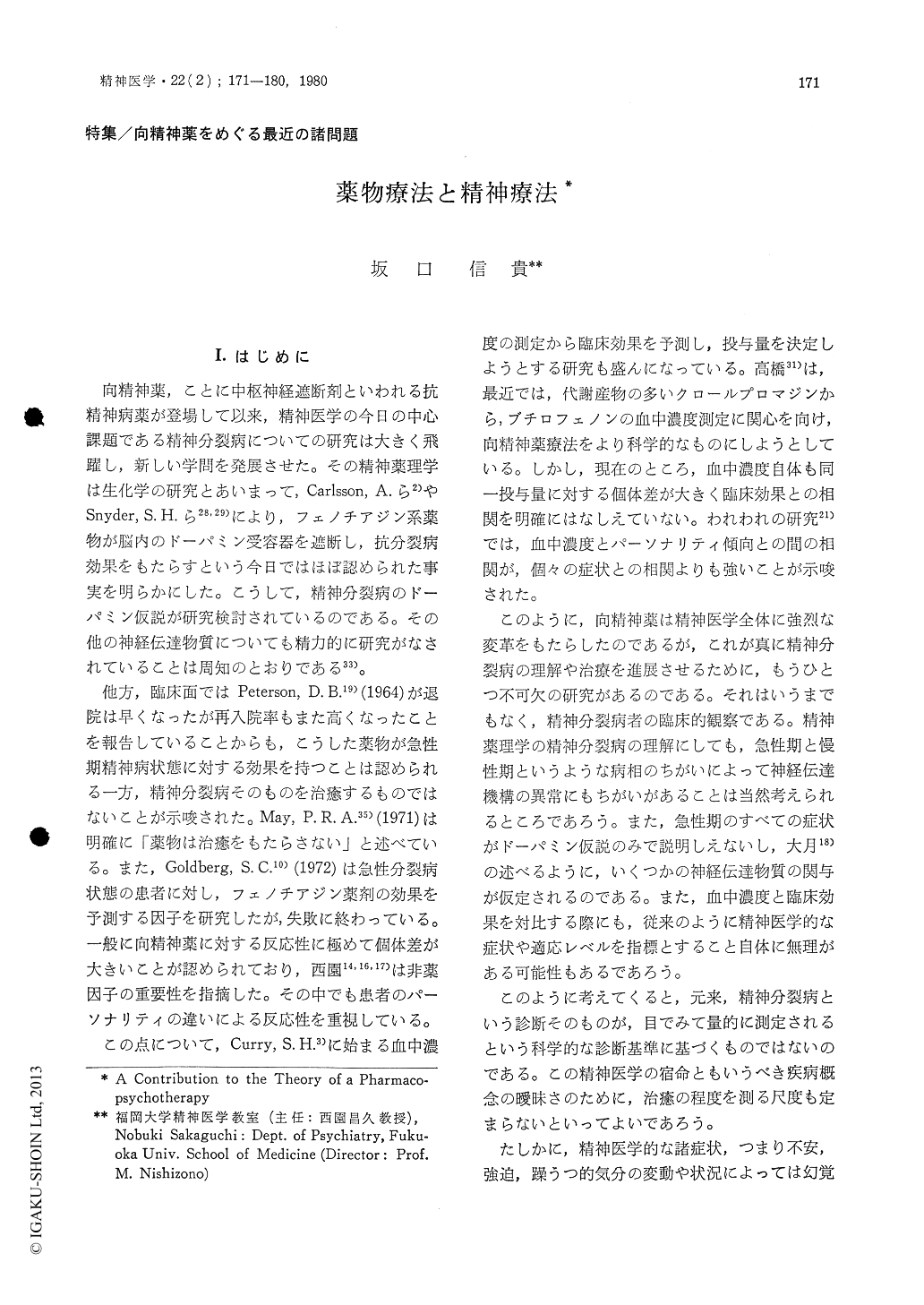
Copyright © 1980, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


