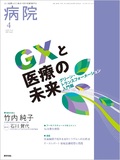連載 ケースレポート
地域医療構想と病院・64
新しい地域医療構想の考え方(1)—慢性期患者の増加に対応した病院機能の検討,地区診断
松田 晋哉
1
1福岡国際医療福祉大学ヘルスサービスリサーチセンター
pp.316-323
発行日 2025年4月1日
Published Date 2025/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.038523770840040316
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
- サイト内被引用
■はじめに
高齢化の進行は,医療と介護の複合ニーズを持った「慢性期」の患者を増加させる.そのような慢性期の患者は「入院,介護施設入所,在宅」のいずれかでケアされる.この3つのサービスの組み合わせのありようは,当該地域の人口構造,医療介護提供体制の状況によって決まる.地区診断に基づいて,この組み合わせを考えることが,地域医療構想・介護保険事業計画などの重要な役割となると筆者は考えている.新しい地域医療構想の検討では,高度急性期,急性期,包括期(従来の回復期),慢性期の病床区分に加えて,自施設の病院機能(高齢者救急や在宅医療支援,専門的な医療の提供など)を検討することが求められる.これらの病院機能は,地域の外来,在宅,介護の状況と密接に関連するため,新しい地域医療構想調整会議では,外来や在宅,介護の関係者も交えて議論が行われることが必要となる.こうした広範囲にわたる議論が,整合性をもって行われるためには,各地域の医療介護のサービス提供体制,特に慢性期の状況がどうなっているのかという地区診断を,将来予測も含めて行う必要がある.そして,この地区診断はすでに公開されている情報を用いることで相当程度可能になっている.今回は2回に分けて,事例も含めてその考え方について論考する.1回目の本稿では慢性期の検討方法について述べてみたい.なお,考え方の詳細については既報1)を参照されたい.
本稿の記述は筆者の私見であり,筆者が所属する委員会や厚生労働省の見解ではない.したがって,記述内容に関する一切の責は筆者に帰するものである.
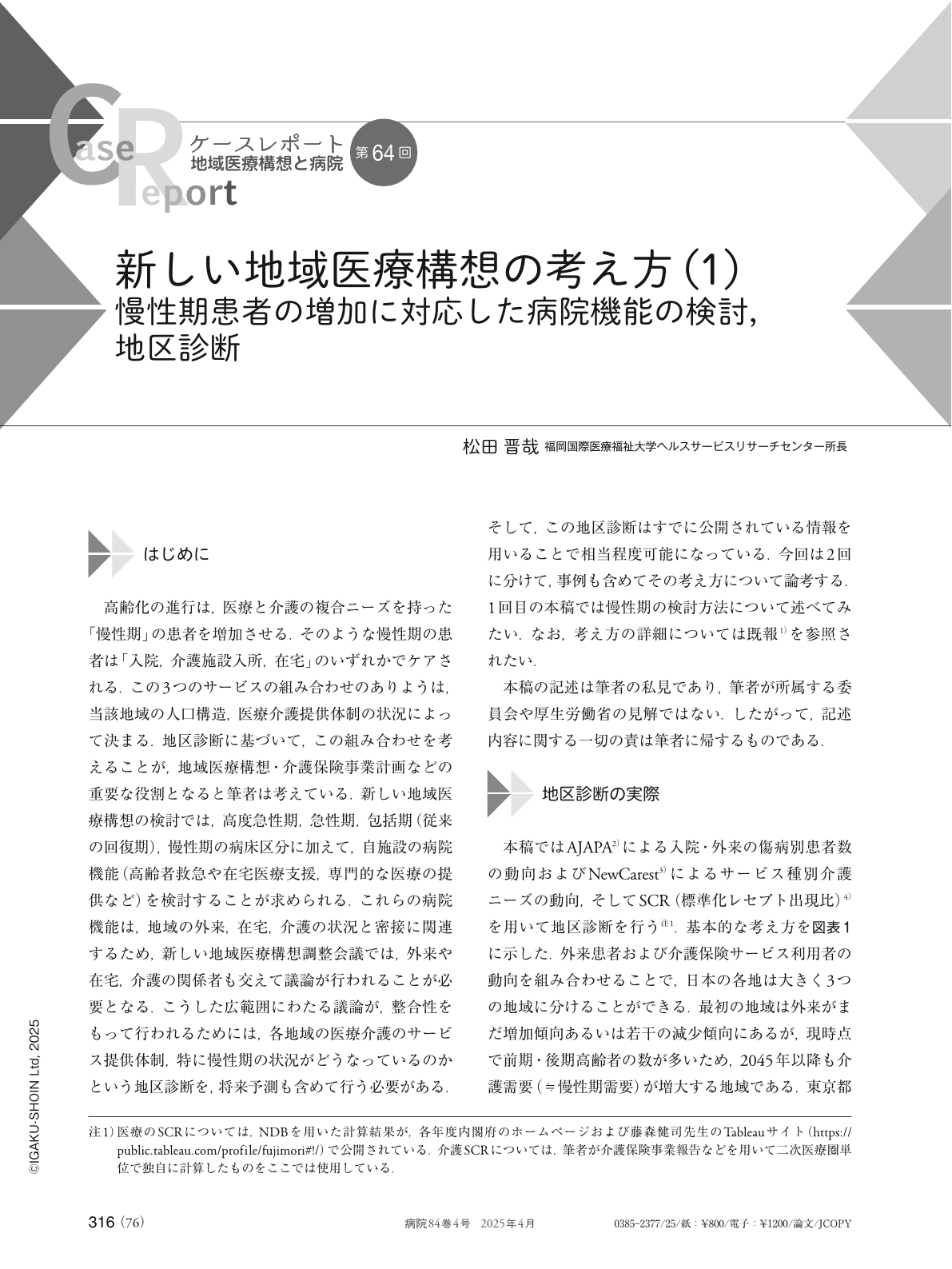
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.