- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I 「生活」という接点
筆者は刑務所と,非行少年を主な対象とする児童福祉施設である児童自立支援施設に勤務している精神科医である。その関係から,もちろん村瀬先生の著作や講演に触れさせていただく機会はあったが,先生と筆者との直接の接点は,決して多くない。十数年前に村瀬先生と田中康雄先生の共同研究であった児童自立支援施設に関する厚生労働科学研究に参加させていただいたときがひとつ,もうひとつが2024年,村瀬先生が理事長を務められていた日本心理研修センター(当時)における公認心理師実務基礎研修検討委員会で司法・犯罪ワーキングチーム(チーム長:橋本和明)にその一員として参加させていただいたときの,2つに過ぎない。
後者において,筆者の「司法・犯罪関連施設における生活と関係性の治療的意味」というタイトルの講義の後半部分で村瀬先生と対談(正確にはインタビューと言うべきだろう)をさせていただいた。それは,ワーキングチームでの協議の際,犯罪者・非行少年を扱う場においても生活と関係性という視点が重要であることを伝えるべきとしたときに,村瀬先生に強く賛同していただいたからである。また先生が筆者の勤務する北海道家庭学校をはじめ,社会的養護の施設のことを常に気に掛けてくださっていたからでもあった。ではなぜ,村瀬先生は施設のことを強く意識されていたか。それは少し逆説的に聞こえるかもしれないが,社会的養護の施設にこそ先生が考える「家庭生活」が色濃く残されているから,ではなかったろうか。
「生活」という言葉に抱くイメージは,それこそ百人百様であろう。それは当然,自分の子ども時代の家庭生活に影響される。村瀬先生の場合,その著作で時に振り返っておられる幼い日々の生活がベースとなっているだろう。子どもに対して愛情深くきめ細やかに注意を払う大人がいること。倫理的に間違ったことを子どもがすれば,それに対して大人がきちんと指導をすること。はっきりとしたルーティンが存在し,それを守ることを非常に大切にする生活(余談だが,村瀬先生の感性と文章には,幸田文のそれと重なるものがあるように感じる。世代は違うものの,戦前のいわゆる「良家の子女」が受けた,非常に賢明な親による生活に根付いた家庭教育の成果というものを感じさせられる(幸田,1955))。
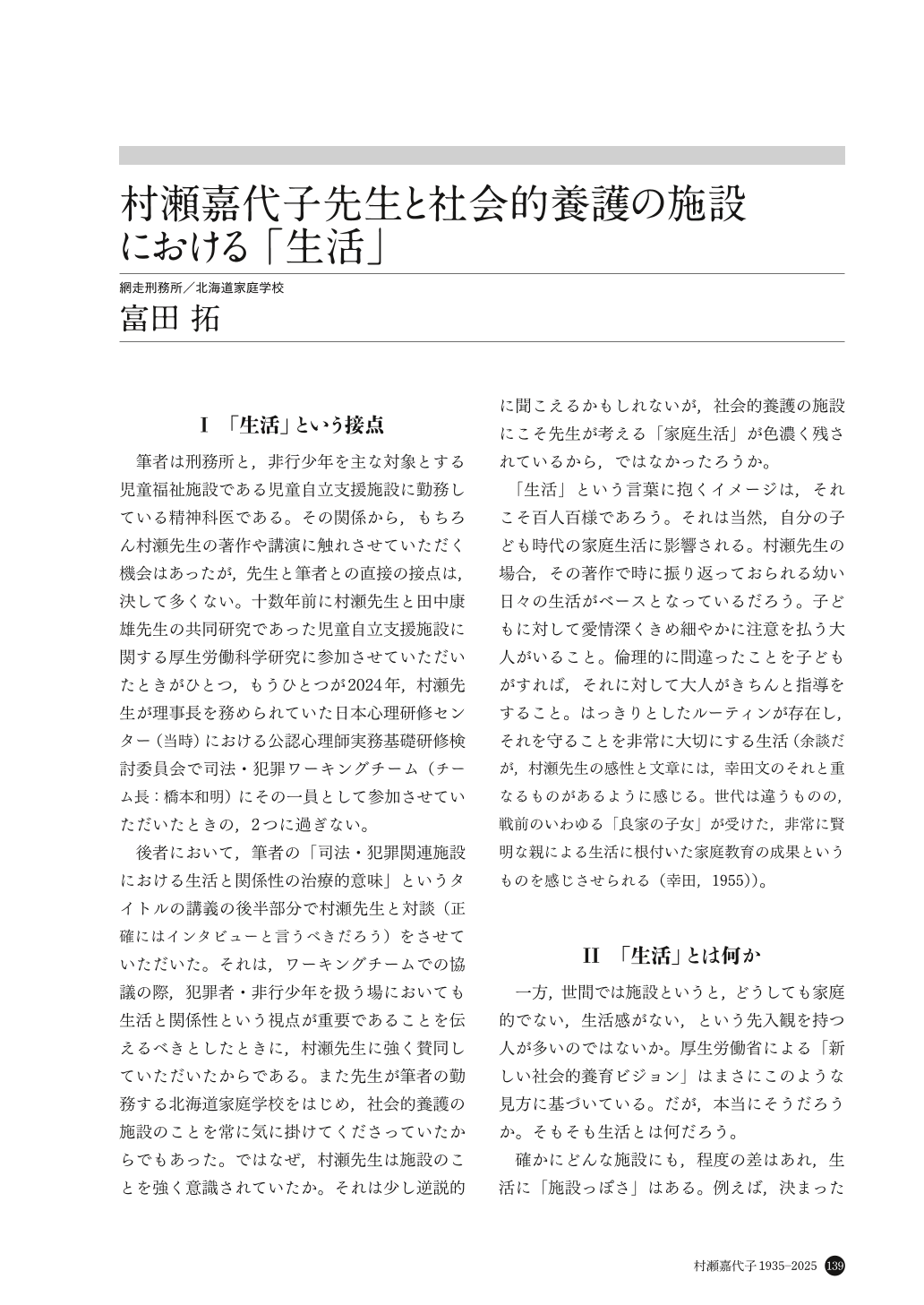
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


