投稿論文 論説
認知再構成法 認知行動療法の技法をアップデートする
毛利 伊吹
1
1上智大学
キーワード:
感情
,
心理的ストレス
,
ストレス障害-心的外傷後
,
医療従事者-患者関係
,
レジリエンス(心理学)
,
楽観性
,
認知再構成法
,
信念
,
ストレングス(潜在能力)
Keyword:
Emotions
,
Professional-Patient Relations
,
Optimism
,
Cognitive Restructuring
,
Stress Disorders, Post-Traumatic
,
Stress, Psychological
,
Resilience, Psychological
pp.553-562
発行日 2023年8月5日
Published Date 2023/8/5
DOI https://doi.org/10.69291/J00762.2023252191
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
認知再構成法は,認知行動療法における代表的技法の一つであり,Aaron T Beckによってうつ病への認知療法が開発された当初から,主要な技法として位置づけられていた。その後,認知行動療法の進展に伴い認知再構成法も変化しており,この技法への基本的な理解を適切に更新することが求められる。そこで本論文では,認知療法に関する彼の初期の著作を振り返りながら,この技法の主な論点を取り上げ,実践上で重視すべき点を検討した。その結果,認知再構成法の標的となる認知の特徴として,非機能的あるいは不適応的,そして現実的という点に注目すること,認知の変化において内容だけでなく,機能の変化も重視するという基本を改めて強調した。加えて,現実的という特徴に着目する実践上の意味を述べた。また比較的近年,重視される点として,認知への変化を促すためには体験的介入などによる感情の活性化が欠かせないこと,および,新たな適応的信念を作り上げる際に,本人の強みや価値に焦点をあてることを紹介した。さらに考察では,認知行動療法におけるセルフマネジメントと「セラピー」という二つの視点を用いて認知再構成法を捉え,前者はクライエントが,外的な現実とは異なるこころの世界が自分にあることを知った上で,その探求を保留して,まず現実的な問題への対処に取り組むものであり,後者はその人の特性とも呼べる信念への変化を促すべく時間をかけて行われるものであると整理した。
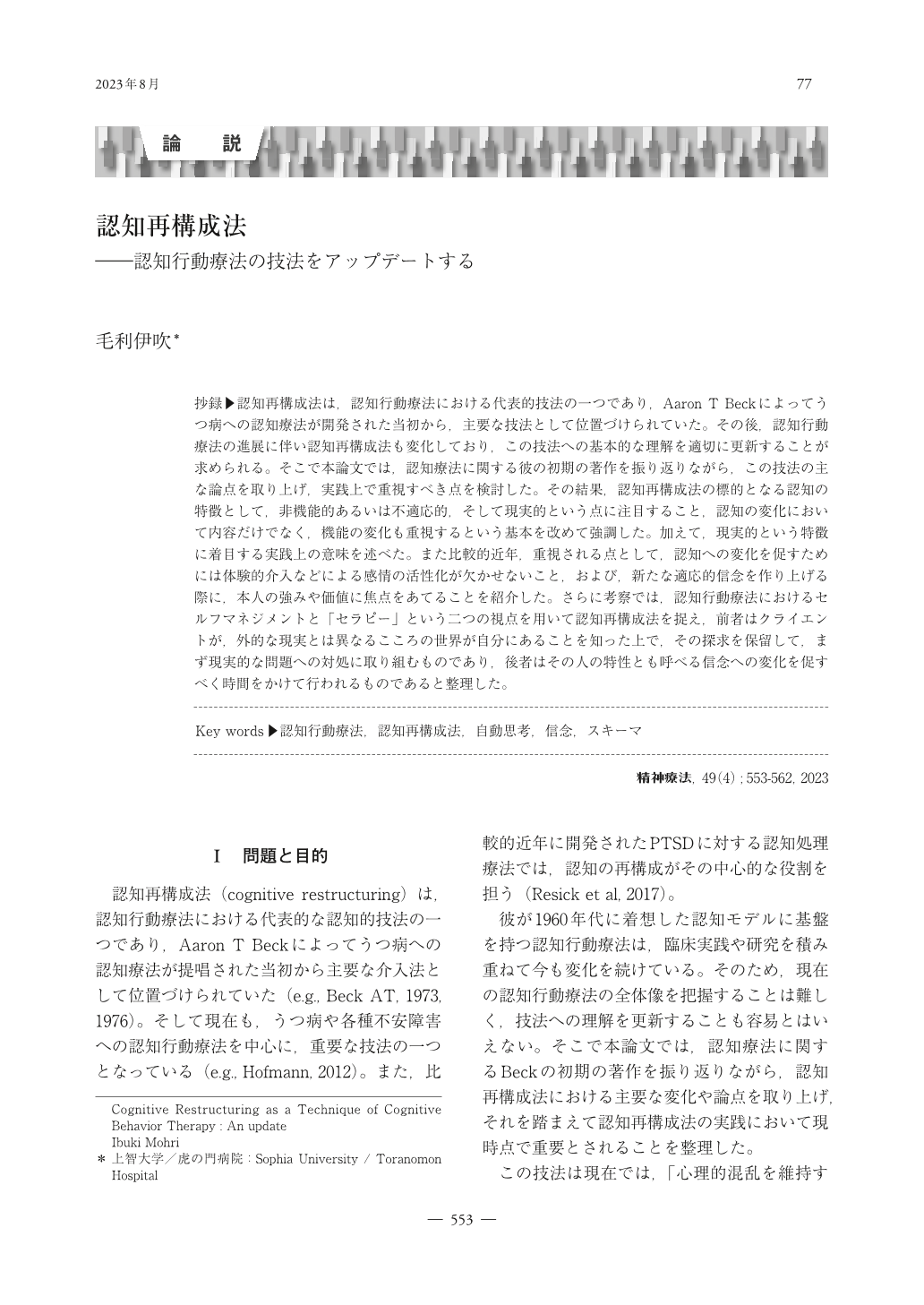
Copyright© 2023 Kongo Shuppan All rights reserved.


